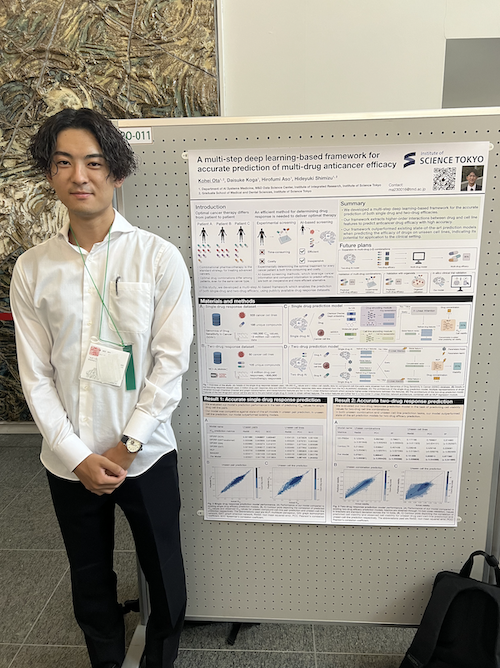2025年バイオインフォマティクス学会年会 参加報告
この度、2025年9月3日から5日にかけて名古屋大学にて開催された2025年日本バイオインフォマティクス学会年会 (IIBMP2025) に参加してきたので、その感想を報告する。本学会年会への参加は、初めて学会参加であった一昨年、そして海外学会との共同開催により初の国際学会参加となった昨年の年会に続き、今回で3回目となった。本報告では、今回の学会参加で得られた知見や感想について、特に自身の研究発表について詳述しつつ報告する。
今回の学会参加における最大の出来事は、学部生時代以来となる口頭発表の機会をいただいたことである。前回は3分程度の短いflash talkであったが、今回はハイライトトラックのセッションにおいて発表時間17分、質疑応答5分というかなり長い時間を頂戴した。発表内容は、私が学部生時代から継続して取り組んできた、先日プレプリントとして公開したAIを用いたオミクスデータ解析手法に関する研究である。学部生時代の発表が研究の初期構想段階に関するものであったのに対し、今回は論文としてまとまった内容について、その核心を深く、かつ分かりやすく伝える必要があった。私にとっての課題は二つあった。一つは、17分間という時間の中で、詳細な研究内容を盛り込みつつも聴衆を飽きさせない、一貫したストーリーを構築すること。もう一つは、本学会の主流であるゲノム解析や構造生物学とは少し異なる、機械学習と代謝システム生物学を融合した自身の研究分野の面白さと重要性を、専門外の聴衆にもいかに明確に伝えるかという点であった。これらの課題を克服するため、研究室で複数回のリハーサルを重ね、先生方や学生の皆からスライド一枚一枚に至るまで詳細なフィードバックをいただいた。その甲斐あって、本番では自分自身が完全に納得できる内容と構成で発表を遂行することができた。そして、大変光栄なことに、本発表に対して後藤修賞 (最優秀ハイライトトラック) を授与されるという望外の評価をいただいた。私が聴講した他のハイライトトラックの発表は、どれも非常にインパクトが高く、かつ独創的な研究ばかりであった。そのような優れた発表の中でこのような賞を賜ったことは、望外の喜びであると同時に、身の引き締まる思いである。発表準備を通じて、どのようなストーリーで語れば研究の面白さが伝わるか、どのような表現や図解を用いれば専門外の研究者にも本質を理解してもらえるかを徹底的に考え抜いた経験は、自身の研究を俯瞰的に捉える能力とプレゼンテーション能力を大きく成長させてくれたと確信している。意義のある課題設定とそれを裏付ける結果が伴っていることは研究の前提であるが、その上で、成果をいかに他者に伝え、その価値を共有するかは科学者にとって極めて重要な責務であり、また、そのプロセス自体を自分が面白いと感じられる人間であることを再認識できたことは、大きな収穫であった。
今回の学会では口頭発表に加えてポスター発表も行った。複数の実験から得られた結果を、限られた紙面の中でいかに取捨選択して、数多くあるポスターの中で立ち止まってもらえるような面白くかつ見やすいポスターを作成するかが工夫のしどころであり、これまでの学会でも意識してきたことであった。今回の学会ではそれらの工夫が功を奏したのか、2日間にわたるポスターセッションでは、幸いにも発表時間中は人が途絶えることなく、様々な分野の研究者の方々に研究を紹介し、数多くの好意的な感想や建設的な意見をいただくことができた。特に他分野の研究者とのディスカッションでは、自分が思いつかないような課題設定や問題・解析方法を知ることができ、大変楽しい時間であった。一方で、他の優れたポスター発表を数多く拝見する中で、自身のポスターの構成やデザインにはまだ多くの改善点があることにも気づかされた。
今回の学会参加で、自身のキャリア観や研究者としての心構えに最も強い影響を与えたのが、慶應義塾大学名誉教授である冨田勝先生によるJSBi名誉会員就任記念講演「AI時代における人間研究者の役割 ~脱優等生のススメ~」であった。恥ずかしながら、私は事前に先生のことを存じ上げていたわけではなく、タイトルに惹かれてなんとなく参加したセッションであったが、その内容は私の心に深く刻み込まれるものとなった。先生のご経歴は、「先読み」と「越境」そのものであった。1980年代の第二次AIブームの最中に人工知能を学ぶために修士課程から渡米し、カーネギーメロン大学で博士号を取得された後、ヒトゲノム計画に衝撃を受け、バイオインフォマティクスという言葉すらなかった時代にコンピュータ科学と生命科学の融合領域に飛び込まれた。その後、日本に戻り、医学博士号まで取得されている。先生は、私が現在取り組んでいる代謝モデリングやメタボロームを含むマルチオミクス研究のまさに先駆者であり、当時はまだ異端であったその研究分野で、周囲からの厳しい批判や逆風にいかに向き合ってこられたか、その実体験に基づくマインドセットに関するお話は、臨場感があり大変面白かった。「自分の研究が批判されても、それに絶対的な自信があれば、落ち込んだり腹を立てたりする必要は全くない。」や、「無理だと言われたことこそがチャンスであり、失敗する可能性の方が高いかもしれないが、その分成功すれば真のイノベーションを生み出せる」などの先生の実体験をもとにしたメッセージは、大変説得力があり、熱意に溢れていた。中でも、「夢中は努力に勝る。夢中になれることを見つけるのは難しいが、試す価値はある」という言葉は、私自身がこれまでの経験を通じて大切にしてきた価値観を、まさに言い表すものであった。これらのメッセージは、日々の研究を推進し、自身のキャリアパスを考える上で大きな原動力となり、指針を形作るものとなった。
その他にも、本学会では多岐にわたる分野の発表から多くの刺激を受けた。特に興味深かった発表の一つが、四肢動物の脊椎 (背骨) の数が生物種ごとにどのような規則性を持つかを解析した研究である。従来、哺乳類では胸椎と腰椎の合計数が種を超えて保存される (胸椎が多い種は腰椎がその分少ない) 傾向にあることが知られていたが、本研究では鳥類において、頸椎と胸椎の合計数、そして腰椎・仙椎・尾椎の合計数が比例するという、哺乳類とは異なるパターンが見出されたことが報告された。脊椎の発生と形態形成には、体の前後軸に沿った位置情報を規定するHox遺伝子群が深く関与していることが知られている。この遺伝子群は鳥類にも保存されているにもかかわらず、なぜこのようなパターンの違いが生じるのか、その分子基盤に非常に興味をそそられた。また、この研究では各生物種の脊椎骨数についてのデータを収集するために古い文献を探して参照したり、博物館に足を運んでは標本を数えたりしていたそうだ。このように地道で根気のいる作業から新たなデータを生み出し、未知の知見を明らかにされたことに、深く感銘を受け、自分もこのような営みを忌避してはいけないと決意した。医学に関連した研究としては、2型糖尿病 (T2D) に関するゲノムワイド関連解析 (GWAS) の発表が印象的であった。T2Dは近年、複数のサブタイプに分類されることが知られており、その一つを規定する因子としてBody Mass Index (BMI) が挙げられる。本研究では、バイオバンクのデータをBMIで層別化してGWASを行い、ゲノム配列パターンに基づいたポリジェニックリスクスコア (PRS) を構築し、その予測精度を検証していた。その結果、BMIが低い、つまり痩せている患者群のPRSの方が、T2D発症の予測精度が有意に高いという結果が得られた。これは、一般的に生活習慣病とされるT2Dにおいて、痩せているにもかかわらず発症してしまっている人々は、遺伝的素因がより強く関与していることを示唆しており、将来的にPRSを臨床応用し、個人の遺伝的リスクに基づいた予防医療や治療戦略を立てる上で、有用な情報となる。さらに、ランチョンセミナーで耳にした「心理的安全性 (psychological safety)」についても印象に残っている。これは、チーム内において、メンバーが対人関係のリスク (無知だと思われたり、叱責されたりすることに対する不安) を恐れることなく、安心して発言や行動ができる状態を指す。セッションでは心理的安全性が高いことが重要なのは言うまでもないが、一構成員の働きかけだけでその改善を図ることは難しいなどの議論があった。この成立には指導的立場にいる人間の協力や理解が不可欠であるため、自分がそのような立場になった際はこの考えを忘れてはいけないと改めて認識した。
総括すると、今年度の学会参加は、自身の研究成果を多くの方に向けて発表し、栄誉ある賞をいただくという大きな経験に加え、第一線で活躍する研究者の哲学や、多様な分野の興味深い研究に触れることのできる大変有意義な機会であった (もちろん毎度のことであるが)。来年度以降も参加し、バイオインフォマティクスの潮流を捉えつつ、新たなテーマで発表を行う所存である。
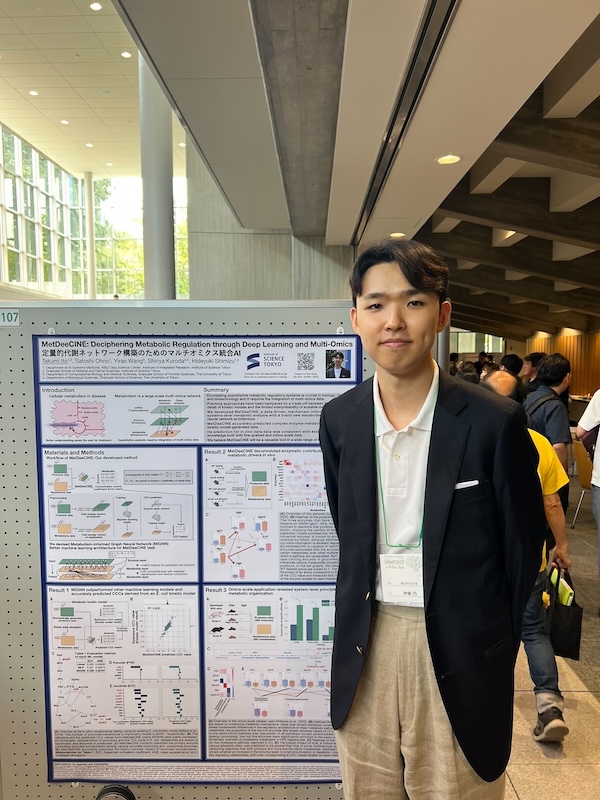
9/3~5に名古屋大学豊田講堂で開催されたバイオインフォマティクス学会 (IIBMP) にこの度参加し、ポスター発表を行った。ポスター発表を行ったのは今回で2回目だったが、聴衆の皆様から非常に示唆に富むご指摘を多く頂け、自分の研究を見直し、より改善していくための非常に貴重な経験になった。以下では、学会全体の印象、現状のホットトピック、印象に残った発表やセミナーの内容を軸に、本学会での学びについて述べていきたいと思う。
まず、学会初日に掲示されているポスターを見て、学会の特性上当たり前かもしれないが、全体を通して、臨床的実用性や治療法の開発などを目指している研究というよりかは、インフォマティクス的に、モデルの性能指標改善や最新手法の導入や開発にフォーカスした研究が多く、修士時代に自分が参加してきた臨床に近い研究が多い学会とは違い、より新鮮な気持ちになった。また、RNAに関する研究や、機械学習や言語モデルを用いて解析や手法の開発を進めている研究が非常に多く見受けられたのも特徴的であった。これらの特徴は、日本のバイオインフォマティクス研究における最近のトレンドを表しているのかなと考えている。一方、自分の行っている抗体関連の研究については、自分のポスターを含めて学会全体で数個ほどしか見受けられず、あまりホットトピックではない印象を受けた。ただ、個人的な感想としては、競争者が少ないため、これはチャンスだと捉え、自分の研究を盛り上げていこうというモチベーションに繋がった。
ポスター発表を聞いた中で、特に印象に残ったポスターは、Prefix-tuningを用いたRNA生成モデルの構築に関するポスターである。この研究は、既存のRNA配列生成モデルを「Prefix-tuning」と呼ばれる手法でファインチューニングすることにより、RNA binding proteinライクなRNA配列を生成可能な生成モデルを構築することを目指していた。Prefix-tuningによってファインチューニングしたRNA配列生成モデルから生成されたRNA配列は、生得的な配列の情報をうまく反映している結果ではなかったが、生成モデルの構築にPrefix-tuningを用いる手法の応用可能性や実装容易性に非常に感銘を受けた。このように本学会で得た知識や最新手法の応用を、自分の研究に積極的に取り入れ、さらに洗練させていきたいという刺激を受けることができ、とても良い経験になった。
次に、本学会の口頭セッションとして一番印象深かったのは、慶應義塾大学先端生命科学研究所の冨田勝先生による「脱・優等生のススメ」と題した講演である。冨田先生の本講演は、日本の科学、ひいては社会全体が抱える構造的な問題を鋭く指摘しており、自分みたいな「優等生」に対して強烈なメッセージを叩きつけるような、非常に情熱的な講演であった。
冨田先生は、「失われた30年」と表現されるような日本の長期にわたる停滞の原因を「優等生が増えすぎたからだ」と主張されていた。ここで言う「優等生」とは、既存のルールの中で高得点を取ることに長けているが、自ら問いを立て、リスクを恐れずに未知の領域に踏み出すことはしない人材のことである。私自身、失われた30年と表現される日本の衰退・世界の科学技術における日本のプレゼンス低下に非常に危機感を感じ、日本の科学技術に少しでも貢献したいと思って博士課程へ進学したため、この主張を聞いて、「優等生」な道を歩んできた自分は急に横から殴られたかのような衝撃と焦りを受けた。
冨田先生自身の人生の歩みは、まさに「優等生」の対極に位置するものであった。インベーダーゲームに熱中した少年時代からAIの黎明期を過ごしたカーネギーメロン大学時代までの軌跡。38年も前に医師と患者の会話を想定し、場面を限定した日英翻訳モデルを開発した先見の明。ヒトゲノム計画を機にバイオインフォマティクスに参入し、当時主流であった「RNAのループ構造が転写を終結させる」という定説に対し、計算科学的なアプローチから「一部の原核生物ではそうだが、全てではない」と異を唱え、実験科学者たちから「実験もしないで人のデータをいじった結果は、生命科学研究ではない」と猛反発を受けた経験。これらのエピソードは、常に常識を疑い、誰もやらないことに価値を見出して挑戦し続けてきた冨田先生の反骨精神の現れであり、長時間にわたる講演であったが、すっかり聞き惚れてしまった。
また、冨田先生が開発した仮想細胞シミュレーション「E-CELL」のお話や、山形県鶴岡市に研究所を設立し、網羅的な代謝物解析「メタボロミクス」を世界に先駆けて提唱した話も、冨田先生の脱優等生の哲学を体現しているエピソードであった。当時は「仮説もなしにデータを取るのは邪道だ」と批判されたオミクス解析が、今や生命科学の標準的なアプローチとなっている事実は、先生の慧眼を雄弁に物語っており、非常に感銘を受けた。「普通はゼロ点、みんなと違うことをやる」という冨田先生の信念は一貫しており、本講演を受けて私の人生に対する価値観を見直すきっかけになった。
どんなに強力な技術や知識も、それを使う人間が「面白い」「これを解き明かしたい」と夢中になれなければ、単なる道具に過ぎない。常識を疑い、誰も行かない道を行く勇気と、そして何よりも対象への尽きない好奇心と情熱。それこそが、科学を前進させる真のエンジンなのかもしれないと深く思い至った。このような示唆を得られただけでも本学会に参加した意義があった。
最後に、私自身のポスター発表について述べる。私が清水研究室に来てから本格的な学会でのポスター発表は今回が初めてであった。また、私のポスター内容は本学会ではかなりマイナーな研究分野の内容であり、さらにポスターの掲示場所も会場の端の見えにくい場所というのもあって、聴衆が来てくれるのか非常に心配であったが、それは杞憂であった。ポスター発表は1日目午後と2日目午前の2回行ったが、2回とも多くの人がポスター発表を聴きに訪れてくれた。1日目の午後には、ポスター発表開始時間の15分前から、複数人が私の発表をポスター前で待っており、緊張と共に自分の研究に興味を持ってくれている嬉しさも覚えた。ポスター発表の時間は50分であったが、それでは足りないくらい多くの人が発表を聞いてくださり、建設的な意見や質問を投げかけてくださった。発表を聞いてくださった多くの人に「この研究とても有意義で面白い、良い仕事になりそう」などとお褒めの言葉を頂いた。これまで半年の期間ではあるが、清水研で一生懸命研鑽した成果を認められている気がして、とても誇らしい気持ちになった。本学会で頂いた意見や質問を自分の研究発展のための更なる糧にして、素晴らしい仕事ができるよう、精進していきたい。
閉会式には、ポスター発表における受賞者の発表があった。とても名誉なことに、私のポスターが優秀ポスター賞に選出された。これまでの努力が報われた達成感を得たとともに、自分の研究をより発展させ、日本の科学技術に貢献していこうというモチベーションが高まった。今回の学会では、清水研のメンバーの全員がポスターや口頭で受賞しており、非常に全国的にもレベルの高い環境に身を置いて研究を行うことができていることを実感するとともに、彼らとより切磋琢磨し、これからの研究生活をより充実したものにしていこうと改めて決意した。
最後に、今回のバイオインフォマティクス学会への参加では、バイオインフォマティクスという学問領域の広範さや、その驚異的な発展速度、バイオインフォマティクス研究者たちの研究レベルの高さを体感することができ、非常に貴重な機会となった。本学会で得た知見と刺激を胸に、常識にとらわれず、自らの知的好奇心に忠実に、倦まず弛まず、研究の道を歩んでいきたいと強く決意した。このような貴重な経験の機会を頂けたことに、心より感謝を申し上げます。
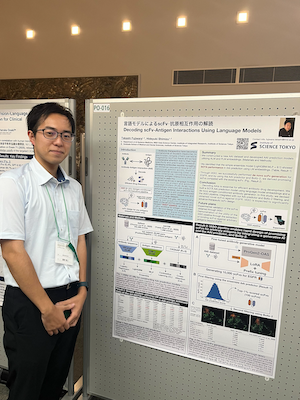
この度、2025年9月3日から5日にかけて名古屋大学豊田講堂・シンポジオンにて開催された「2025年日本バイオインフォマティクス学会年会・第13回生命医薬情報学連合大会(IIBMP2025)」に参加し、ポスター発表を行いました。今回の発表にあたりご支援いただいた皆様に感謝申し上げますとともに、学会を通して得られた学びを共有させていただきます。
今回の学会は4会場で参加者が605名ということで、自分が学部時代に参加してきた薬学系や疫学系の学会と比べると小規模ではありましたが、学生やアカデミア研究者だけでなく多くの企業関係者もポスター発表を行っていて、口頭発表やポスターセッションでは活発な議論が交わされていました。自分の中では、バイオインフォマティクス学会では情報科学的な手法に特化した発表がほとんどだと思っていました(し、実際にこういった発表が多くを占めていました)が、医療への応用を目指した研究も意外に多く、情報科学と他分野の融合が近年ますます重要視されているのだなと強く感じました。
ポスターセッションでは、「ドラッグリポジショニングを目指したマルチモーダル・知識グラフの構築」というタイトルで、博士課程に進学してから新たにスタートさせたテーマ(これまで見逃されてきた薬物間相互作用を見出すための知識グラフを構築する試み)の概要について発表しました。製薬企業の方々をはじめとして様々な職種の方に発表を聞いていただき、製薬企業の方とは各社でのドラッグリポジショニング研究の取り組みや現状についての具体的な話も交えつつディスカッションをする大変貴重な機会となりました。
この学会で特に印象的だったのは、参加者が交流に対して非常に積極的であったことです。自分がこれまでに参加してきた学会では名刺交換をすることは稀でしたが、今回は相手から積極的に名刺を渡してくださったり、学会後であっても情報提供やディスカッションの場を設けてくださったりするなど、学生にも開かれた雰囲気を強く感じました。おかげで、2日間に渡って行われた合計100分のポスターセッションでは20枚以上用意していた名刺がなくなるほど多くの方にポスターを聞いていただき、鋭く厳しいご指摘も含めて非常に有意義な議論ができました。また、自分から他のポスターセッションを見に行き、ディスカッションさせていただけたことでもとても勉強になり、新たな繋がりも生まれました。
知識グラフやデータベース構築に関する発表は少数でしたが、ライフサイエンス統合データベースセンター(DBCLS)の方々をはじめ、産官学問わず多くの専門家やデータベースを扱っている方が参加されていたことも印象に残っています。研究で悩んでいた疾患名のグルーピングについて、指定難病名のグループ化を行っている先生に相談することができ、貴重なアドバイスをいただけました。同じようにデータベース構築に取り組んでいる方からも、今後の研究の発展に役立ちそうなデータベースの情報を教えてもらうなど、建設的なコメントや助言を多数得ることができたのは今回の学会に参加して得られた大きな収穫でした。
特に感銘を受けたのは、冨田勝先生のJSBi名誉会員就任記念講演「AI時代における人間研究者の役割〜脱優等生のススメ〜」です。ヒトゲノム計画の中でバイオインフォマティクスに参入し、周りの研究者から「データ解析だけで(実験もせずに)得られた結果は生命科学研究ではない」と批判されながらも自身の道を切り拓かれてきた冨田先生のお話は、既存のルールの中で高得点を取ることだけで満足し、リスクを恐れずに未知の領域に踏み出そうとしない「優等生」に対しての強いメッセージが込められていました。自身が出演したTV映像を流すなど、聴衆を飽きさせない工夫も挟みながらわかりやすくメッセージを伝える冨田先生の話のうまさに惹き込まれてしまい、講演後にはラボのメンバーと共にしばらく放心状態になってしまいました。既存の枠組みに囚われず(=脱優等生)、自身の道を切り拓いて成功を収めてきた冨田先生の生き様は、リスクを恐れずに未知の領域へ踏み出すことの重要性を示しており、博士課程で清水研に飛び込んできた自分にとってすごく刺激になりました。また、冨田先生が設立し、「メタボロミクス解析」を提唱することになった鶴岡サイエンスパークで10月に発表することができることにもすごくご縁を感じました。
また、漢方薬成分の代謝産物を既存の代謝産物予測モデルに比べて高精度に予測したポスター発表も印象的でした。学部時代から漢方薬の作用機序は明らかになっていないものも多くあると感じており、そのために重要になる漢方薬の代謝産物を高精度に予測したいというモチベーションは自分にとってはすごく納得のいくものでした。また、既存のインシリコ代謝産物予測手法を漢方薬成分に適用しても、構造のデータが限られている現状では予測が難しいという課題を解決するために、自然言語処理を用いた文献マイニングによって対象化合物や関連化合物の代謝情報を抽出して、構造情報を補完することでカスタムデータベースを作成し、既存の代謝産物予測モデルと統合することで、従来手法では予測できなかった代謝産物の予測を可能にするというアプローチは、目的と計画性、そして実行力がうまく融合された、非常に合理的な研究だと感じました。
ありがたいことに、閉会式では優秀ポスター発表賞をいただくことができました。セッションの中でいただいた質問の多くは普段のグループミーティングでラボの皆様からいただいているご指摘を踏まえて答えられるものが多かったですし、今回のポスターに限らず清水先生をはじめとしたラボの皆様にたくさん鍛えていただいたからこそ、自信を持って発表できたと感じています。また、鈴岡さんからのアドバイス「学会発表ではできるだけ名前を覚えてもらえるように名刺を交換し、その日のうちにメールでコンタクトを取るようにする」を実践できたことも、受賞に繋がった一因だと考えています。まだまだ研究を始めたばかりでデータも出ていないところではありますが、今後は研究をさらに進めることで(自己アピールだけでなく)研究的に面白いと思ってもらえるように頑張ります。
今回、清水研究室に参画して初めての学会発表に参加させていただきました。これまで参加したことがある学会に比べても、バイオインフォマティクス学会は非常に活発な議論が行われており、自分の研究にとっても、人脈形成の面においても得られるものがとても多かったと感じています。また、一言でバイオインフォマティクスといっても、自然言語処理から臨床応用に至るまで自分の想像以上に幅広い分野から発表されており、ポスターを見て回るだけでも各分野での最新の知見をシャワーのように浴びて大いに学ぶことができました。もちろん全てのポスターの詳細を理解しきれているわけではありませんが、清水研でのこれまでの勉強会で少しは触れたことがあるものがとても多く、研究内容を追っていくことができたものが多くあったことが嬉しかったです。一方で、今回の学会を振り返ってみると、自分が面白そうだなと思って見に行ったセッションは自分の研究に近い分野(データベース構築や臨床への応用を意識した研究など)に少し偏ってしまっていたという反省点もあります。今後の研究を進めていく上では有意義でしたが、自分の分野とは少し違う分野から新しい視点を入れることも重要だと思うので、今後の学会では異なる分野の発表も積極的に聞き、議論をできるよう勉強を重ねて、自身の研究にも新しい視点を取り入れる場にしていきたいと考えています。
この度は、このような貴重な機会とご支援をいただきまして、改めて感謝申し上げます。
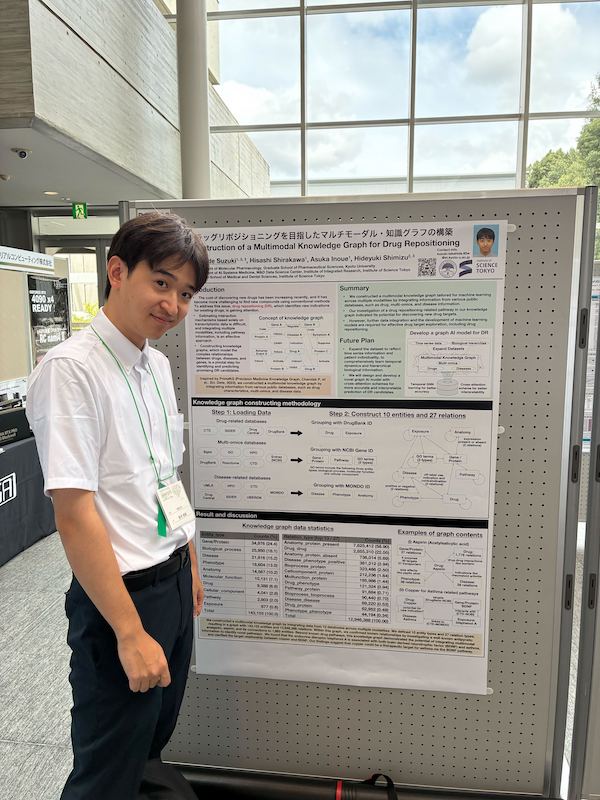
2025年9月3日から5日にかけて名古屋大学豊田講堂で開催された第13回生命医薬情報学連合大会(IIBMP2025)に参加したため、本報にて簡単に報告する。本大会のテーマは「生命・医薬科学とその先へ越境するバイオインフォマティクスVer2.0」であり、現代の生命科学が直面する多様な課題に対し、バイオインフォマティクスがいかにして境界を越え、新たなソリューションを創出していくかという未来志向の議論が活発に行われた。多様な背景を持つ参加者が集い、多くの知見を得る貴重な機会となった。
初日は、小谷元子氏による基調講演で数理科学の大きな潮流に触れた後、ポスター発表を聴講した。170を超えるポスターが掲示されており、その規模に圧倒されたが、事前に抄録で確認していたAptamer設計や独自のRNA言語モデル開発など、個人的に関心を持っていた分野の発表を複数聴くことができ、有意義な時間であった。バイオインフォマティクスという言葉でまとめられる分野は非常に幅広いため、当初は自身の専門外の発表まで理解できるか不安があったものの、実際には問題なく内容を把握し、発表者と建設的な議論も行うことができた。日頃の清水研でのJCやML/CSなどの勉強会、GMで他の学生の研究についても議論をしている経験を通じて培われた基礎学力と応用力が、自身の確かな力となっていることを実感する機会でもあった。
ランチョンセミナーでは、Science Aid株式会社提供の「AI scientist」に関するセッションを聴講した。第一部、筑波大学の史蕭逸氏による「30代のための研究自動化」では、新人PIが直面するタスク増大という現実的課題に対し、AI活用が研究者の創造的な仮説立案や戦略策定の時間をいかに創出するかが、具体的な実例と共に示された。第二部、山田涼太氏による「ライフサイエンスのためのAIエージェント」では、文献調査から仮説生成までを自律的にこなす「AI Scientist」の登場が紹介され、研究プロセスを根底から変える可能性が示された。これは単なる作業代替ではなく、AIが研究者のパートナーとなる時代の到来を予感させるものであった。AI scientistに関する論文の増加は認知していたが、その実態を十分に把握できていなかったため、本セッションで具体的な実例や技術的潮流を学べたことは大きな収穫であった。特に StanfordのBiomniはSlack communityも非常に盛り上がっており開発者からのサポートも手厚いとのことであり、自分も動かしてみようと考えている。
午後には本学会最初の口頭発表・ハイライトトラックを聴講した。中でも、東京大学医科学研究所の伊東潤平先生による、タンパク質言語モデルを活用したインフルエンザウイルスの抗原性予測「PLANT」の発表が特に印象的であった。免疫学における古典的かつ重要な課題に最新のAI技術がブレークスルーをもたらす可能性を目の当たりにした。研究者として、自身の研究がどう社会に役立つかを考えることは非常に重要であり、伊東先生の研究はまさに研究成果を通して社会が問いかけるクエスチョンに対して的確に答えを出していく姿が非常に印象的であった。
夕方のポスターセッションでは自身の研究成果を発表した。セッション中は予想以上に多くの方に訪れていただき、特に免疫学の研究をしておられる研究者の方とは非常に深い議論を交わすことができた。新たな視点からの質問をいただいたり、これまで考えていなかった解決策をご提案いただいたりと、非常に有益な時間を過ごせたことは大きな成果である。
二日目午前に受講した、理化学研究所の尾崎遼先生が企画したワークショップ「実験自動化のためのインフォマティクス」では、「実験行為そのものの自動化」に関する多様な知見を得た。前述のランチョンセミナーが「思考の自動化」に焦点を当てていたのに対し、本ワークショップではロボットによる実験スケジューリングやデジタルツインといった最先端の取り組みが紹介された。これらの技術はウェットとドライの境界を完全に融解させるインパクトを持つ。「自律的研究サイクル」の実現は、研究の再現性を飛躍的に向上させ、人間には不可能であった規模と速度でのデータ生産を可能にするだろう。これらの取り組みが想像以上に実用段階に近づいていることを知り、強い関心を抱くと同時に、この分野の技術動向を継続的に追う必要性を痛感した。ちょうど9月にはラボラトリーオートメーションの月例勉強会が開催されるとのことであり、そちらでより知見を広げたいと思う。
午後には、河⼝理紗先生(東⼤薬・京⼤iPS研)が企画した「Bio x Info EXPO 若⼿クロストーク」に参加した。以前別の機会に河口先生のプレゼンテーションをお聞きする機会があり、それが非常に印象的なものであったため、本セッションは特に楽しみにしていた。発表内容では、YongJin Huan氏(京都⼤学)による「⽣化学反応ネットワークの構造に基づく細胞表現型のマーカー分⼦の同定」が、数理科学を用いて生命科学の重要課題に取り組む好例であり、まさに本学会がテーマとした「越境」の実例として特に興味深かった。本セッションの登壇者はいずれもACT-X「⽣命と情報」領域に参画する優秀な若手研究者であり、そうしたメンバーがチームとなって一つのセッションを開催している姿にはとても刺激を受け、そのような優秀な若手研究者の輪に早く自分も入りたいと痛感した。
以上のように、本学会では多くの収穫があったが、最終日の閉会式では、170件を超えるポスターの中から優秀ポスター発表賞(5名)の一人に選出していただけた。聴衆から自身の発表を評価されたことは大変光栄であり、今後の研究活動への強いモチベーションとなった。
今回のIIBMP2025は、バイオインフォマティクス分野の現在地と未来を鮮やかに描き出す、非常に刺激的な大会であった。最先端の科学技術に触れるだけでなく、分野の垣根を越えた交流や、若手研究者のキャリア形成といったテーマにも光が当てられており、自身の立ち位置と未来を考える貴重な機会となった。本大会の成功に尽力した大会長の白井剛氏をはじめとする実行委員会、そして有益な知見を共有した全ての講演者、発表者に心より感謝の意を表する。ここで得た学びとインスピレーションを糧に、今後の研究活動に一層邁進していく所存である。
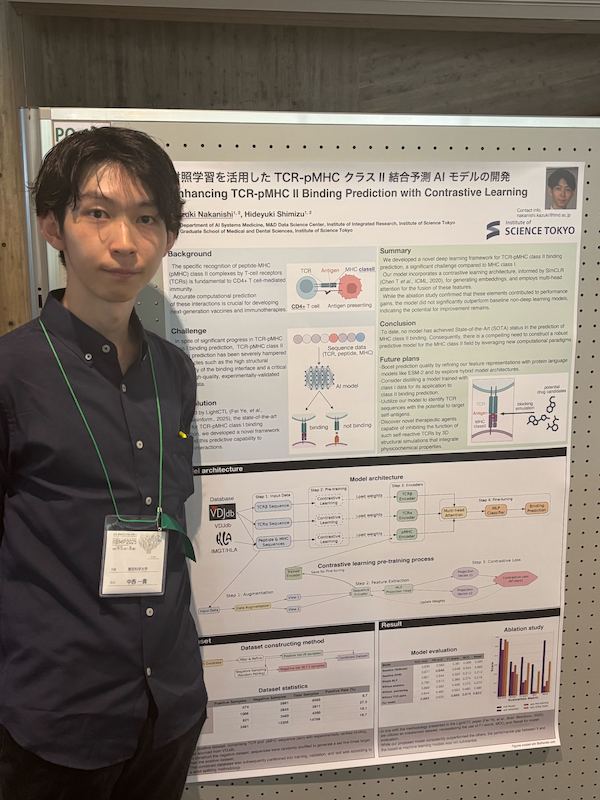
2025年9月3日~4日に愛知県の名古屋にて開催された日本バイオインフォマティクス学会年会に参加した。本学会では、空間オミクス解析やラボオートメーションなどの技術、大規模言語モデルを用いた機械学習など、さまざまなトピックを扱っていた。また、量子アニーリングをはじめとした量子計算技術を用いた研究も複数あり、最先端の研究に触れることができた。以下では本学会を通して特に印象に残った発表や印象に残った事項を報告する。
数多くの発表の中で特に印象深かったものは、九州大学の加藤幸⼀郎先生による「生体高分子の量子化学計算を可能にするFMO法と機械学習の融合」と東京大学の⽔野忠快先生による「潜在的⾔語構造に基づく⽣命科学データのパターン認識」、早稲田大学の浜田道昭先生の「RNA創薬を加速するバイオインフォマティクス技術」に関する口頭発表である。
加藤先生はタンパク質などの大きい分子に対して量子化学計算をする研究に取り組んでいる。創薬における分子シミュレーションでは、一般的に古典力場計算が用いられるが、これは原子を点電荷として扱うため、分極効果や電荷移動といった電子状態の変化を正確に記述できない。また、量子化学計算は電子状態を直接扱うため高精度だが、計算コストが分子サイズの3乗以上に比例して増大するため、タンパク質のような数千〜数万原子からなる巨大分子への適用は事実上不可能であった。この「精度と速度のトレードオフ」が長年の課題であった。そこで、加藤先生は創薬研究等で重要となる生体高分子の挙動を精密にシミュレーションするため、量子化学計算手法である「フラグメント分子軌道(FMO)法」と機械学習を融合させるアプローチを提案した。FMO法は巨大分子をアミノ酸残基などの小さな「フラグメント」に分割し、フラグメント単体(モノマー)およびフラグメント対(ダイマー)の量子化学計算を行うことで、系全体の電子状態を近似する日本発の手法である。これにより、計算コストを大幅に削減しつつ、量子化学レベルの精度を維持することを可能にした。個人的に興味深いと感じた工夫は学習ターゲットを単純な「全エネルギー」ではなく、より物理的な意味を持つ「結合エネルギー(全エネルギーから孤立原子のエネルギーを差し引いたもの)」とすることで、異なる分子サイズ間での学習を可能にし、コンフォメーション変化に伴う微小なエネルギー差の予測精度を向上させた部分である。
水野先生は生命科学情報の潜在表現抽出と活用に関する研究に取り組んでいる。今回は「化合物言語モデル」と「オミクスデータ解析」の2つのテーマについて講演された。前者では、化合物言語モデルの学習において、モデルがキラリティの認識を苦手とすること、そしてデータベース毎に標準とされるカノニカルSMILESの定義が異なることに起因する表記の揺らぎ(例:芳香環のケクレ構造表記)が、物性予測精度を低下させる原因となることを実証した。後者では、従来の細胞比率推定法(デコンボリューション)が抱える、実験条件の違い(バッチ効果)に対する脆弱性という課題を取り上げられた。この解決策として、組織の遺伝子発現データを「文書」、遺伝子を「単語」とみなし、潜在的ディリクレ配分法(LDA)を応用した。各細胞種に特異的なマーカー遺伝子リストのみを事前知識(ガイド)として利用する新しい手法を開発し、参照データなしでバッチ効果に対して頑健な細胞比率推定を実現した。このアプローチの有効性は、薬剤性肝障害モデルマウスのデータ解析において、薬剤投与後の免疫細胞集団の動的な変動を詳細に捉えることで示された。自然言語処理という異分野の技術を、化学構造と遺伝子発現という全く異なるデータに巧みに応用し、それぞれの分野で重要な知見を引き出されている点が非常に印象的でした。特に、単にモデルを適用するだけでなく、その挙動を深く分析し、「データ表現の重要性」や「バッチ効果への頑健性」といった実用上の本質的な課題を解決するアプローチは、信頼性の高いモデルを構築する上で大変示唆に富むものだった。
浜田先生はRNAアプタマー創薬とRNA標的創薬の研究に取り組んでいる。第一に、RNAアプタマー創薬に関して、先生が開発された一連の技術「RAPTシリーズ」が紹介された。従来のアプタマー探索では、SELEX法などで得られた膨大な配列候補の中から有望なものを選び出す必要があった。初期のRAPTは、配列全体ではなく、機能に重要な「ローカルな配列」と「構造情報」に着目し、有望なアプタマーを効率的にランキングする手法として開発された。しかし、この手法は既存の配列から「選ぶ」ものであり、限界があった。そこで、AI技術を導入し、実験データには存在しない全く新しい高機能なアプタマー配列を「生成」する手法として「RAPT-Gen」が開発された。RAPT-Genは、変分オートエンコーダを用いており、特にデコーダ部分に配列の挿入・欠失・置換といった特徴を捉えやすいプロファイルを組み込むという独創的な工夫がなされている。これにより、アプタマーらしい配列を効率的に生成できるだけでなく、目的の長さに合わせた設計も可能になった。さらに、RAPTシリーズは進化を続けており、言語モデルを用いて結合親和性を予測する「RAPT-Score」や、配列設計を組み合わせ最適化問題と捉え、量子アニーリング(量子計算)を用いて最適な配列を探索する「RAPT-QA」といった、さらに先進的な手法も紹介された。第二に、RNAそのものを創薬のターゲットとするアプローチが紹介された。特に、タンパク質をコードしない「長いノンコーディングRNA(lncRNA)」に注目が集まっている。lncRNAはゲノム上に多数存在し、疾患との関連が示唆されているものが増えている一方で、その多くは機能が未解明である。浜田先生は、これらが新たな創薬ターゲットになる可能性を指摘し、研究を推進するための基盤として、lncRNAに関する多様な情報を統合したデータベースを構築していると報告した。このデータベースには、RNAの相互作用、化学修飾、構造情報、低分子化合物との結合データなどが集約されており、将来的にRNAを標的とした創薬研究を加速させることが期待される。本講演を拝聴し、バイオインフォマティクス、特にAIや量子計算といった最先端の計算科学技術が、創薬のプロセスを根本から変えうる強力な駆動力となることを改めて実感した。従来、実験的な試行錯誤に大きく依存していたアプタマーの探索が、RAPTシリーズのような計算科学的アプローチによって、より合理的かつ効率的な設計へとシフトしていく未来を強く感じた。特にRAPT-Genにおいて、単に深層学習モデルを適用するだけでなく、プロファイルを組み込むことでアプタマー配列の生物学的特性をモデルに反映させるというアイデアは、単なる技術応用にとどまらない、ドメイン知識に基づいた非常に洗練されたアプローチだと感じ、大変参考になった。また、配列設計というバイオインフォマティクスの難問に対し、量子計算という全く新しいパラダイムを持ち込んだRAPT-QAの研究は、分野の未来を切り拓く挑戦であり、非常に刺激的であった。
最後に自分のポスター発表について述べたい。ありがたいことに、企業・アカデミアを問わず、様々なバックグラウンドを持つ方々に足を運んでいただけた。当初、バイオインフォマティクス学会という特性から、聴衆は数理情報系に精通しているという前提で説明を準備していましたが、実際には多様な専門性を持つ方々がおり、必ずしも数理情報系に明るくない方に対して十分に意図を伝えきれない場面があった。この経験から、今後は複数の説明パターンを用意し、聴衆の背景に合わせて柔軟に発表内容を調整できるように準備する重要性を痛感した。今回、全国規模の学会で初めて「後藤修賞(最優秀ポスター発表賞)」という栄誉にあずかることができ、自身の研究が評価されたことを大変光栄に思うと同時に、大きな励みとなった。この受賞は、日頃からご指導いただいている清水先生をはじめ、発表準備に際して丁寧に助言をくださった研究室メンバーの皆様のご支援の賜物であり、この場を借りて深く感謝申し上げます。
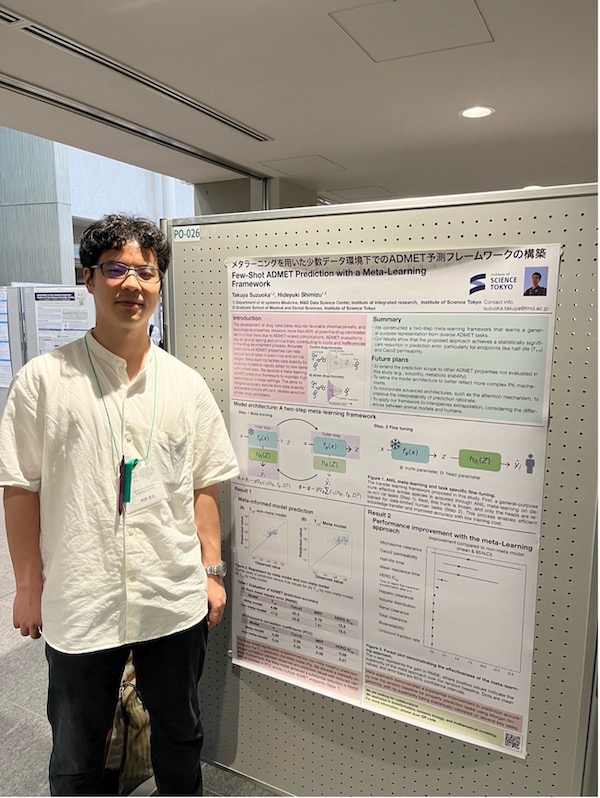
2025年の9月3日から5日にかけて、名古屋大学豊田講堂にて開催された2025年日本バイオインフォマティクス学会年会(IIBMP2025)に参加させていただいたので、その報告をする 。
2023年度の年会(IIBMP2023)に続き2度目の参加となる本学会は私にとって、とても思い出深い学会である。1度目の参加は入学してから半年というタイミングであったため、聴講のみであったが、あらゆる分野のオーラルセッションやポスター発表を聞きながら、「本当に私もこの様な場で発表できる様な成果が出せるのだろうか」と少し不安に思ったことを鮮明に覚えている。あれから2年、清水研の一員として貴重な経験を多々積ませていただき、今回は発表者として参加する機会をいただいた。自分で言うのもだが、2年前と比べると少しは成長できたのではないかと感じた。
初日は、JSBi名誉会員就任記念講演を聴講した。冨田勝先生(慶應義塾大学)の「AI時代における人間研究者の役割〜脱優等生のススメ」と題したご講演は、今回聴講した発表の中でも最も印象深い発表の一つであった 。冨田先生は、人工知能を専門とする研究室が日本にまだ存在しなかった時代に、カーネギーメロン大学に修士課程から留学し、機械学習の分野でPh.D.を取得された自然言語処理を専門とする情報科学者であったが、ヒトゲノム計画の発足をきっかけに生命科学に転じられた。
発表のなかでは特に、解糖系、遺伝子の転写・翻訳、リン脂質合成系を組み込んだ、127遺伝子からなるバーチャル細胞のシミュレーションソフトウェア、E-CELLを発表した際のエピソードが印象的であった。バーチャル細胞シミュレーションの様な、ドライ解析のみの研究成果を当時の分子生物学会で発表すると、実験生物学を専門とする研究者から袋叩きにあったという話であった。「実験的に検証していないドライの成果には価値がない」、「他人が計測した公共データをいじっているだけ」などといった批判を浴び続けたが、これからはコンピューター解析の時代が来ると信じていたため、何を言われようと揺らぐことがなかったという話は大変刺激的であった。いち早く最先端の技術を新たな分野に取り入れ、周りの批判があろうとも時代が自分に追いつくまで黙々と成果を出し続けるような「脱優等生」的な姿勢を真似することは決して容易ではないが、そういった方々がいるからこそ大きく研究が進歩するのだと感銘を受けた。また、発表の終盤では近年著しい進歩を見せている生成AI技術についても触れられた。各国の司法試験や医師国家試験を瞬時に合格できる様な生成AIにスマートフォンでアクセスできる時代が到来した。そんな中であなたの人間的な魅力は何か?生成AIに代替されないあなたの価値は?と聴衆に問いかける形で冨田先生は発表を終えられた。私自身、これらの問いに対して自信を持って言える答えを見つけられていない。代替されないような人材であるために、自分にしかない価値を見つけ、磨き続けたい。
2日目の午前中は、研究室の同期である伊東さんの口頭発表が行われるセッションに参加した。当研究室では学会などで口頭発表を行う場合、事前に研究室メンバーの前で予行演習を行い、全員で発表スライドを一枚ずつ振り返りながら修正を行っている。当日の伊東さんの発表は、スライド・発表内容ともに予行演習の時とは見違えるほど洗練されており、結果的に最優秀賞である後藤修賞を受賞された。清水研の一員となって以来、優秀な同期である伊東さんと大谷さんの背中をずっと追いかけてきた。常に自分の一歩先を行く彼らの存在があったからこそ、自分も大きく成長できたと感じている。残り少ない研究室での時間をフルに活用し少しでも追いつきたい。
伊東さんが発表を行ったセッションはハイライトトラックと呼ばれる、プレプリントサーバー、もしくは査読付き学術雑誌に掲載された研究成果のみが対象となっていたため、どの発表も非常にレベルが高かった。中でも印象に残ったのは廣田さん(東京科学大学 大学院生)による酵素スクリーニングのための深層学習モデル:DeepRESについての発表であった。代謝反応データベースに含まれる多くの反応は触媒する酵素に関する情報が欠如していることに着目し、タンパク質のアミノ酸配列情報をもとにまずそのタンパク質が酵素か否かを分類した上で、触媒する反応を予測する多段階フレームワークであるDeepRESの詳細について発表された。モデルの構造や、既存モデルとの比較結果もimpressiveであったが、何より課題設定が非常に良いと感じた発表であった。酵素と深層学習を組み合わせた研究は、酵素パラメーター予測や酵素番号の予測などのタスクに特化したものが多い中で、アミノ酸配列から直接触媒する酵素を予測し、機能未知酵素のアノテーションツールとして活用するというアプローチは今後行うであろう実験検証とも相性が良く、非常に勉強になった。
2日目の午後は「Bio x Info EXPO 若手クロストーク」と題した公募ワークショップに参加した。本ワークショップはJST ACT-X「生命と情報」領域との共催であり、本領域に参画する若手研究者が研究内容を紹介するという内容のものであった。生命科学と情報科学の融合領域の最先端を走る若手研究者による発表は、MDシミュレーション、GWAS、発生に関するバイオインフォマティクスなど多岐にわたり、どれも大変勉強になった。中でも、Huangさん(京都大学 大学院生)が発表された、数理生物学を駆使して、代謝産物から細胞の表現型を効率的に分類するために測定するべき重要な物質のみを選択する手法の開発について報告する。近年、トランスクリプトーム情報ではなく、細胞の機能をより直接的に反映する代謝物質を測定して細胞の表現型を分類するメタボローム解析が注目されている。しかし、細胞内の全ての代謝産物を測定するのは現実的ではないため、細胞の表現型を決定する少数の指標分子を選ぶ必要がある。Huangさんは、代謝反応ネットワークの構造に注目しトポロジカル次数理論や不動点定理などの数学理論を応用することで、複雑な反応ネットワークを小さなサブネットワークに分解し、指標分子を特定する手法を開発した。サブネットワークや指標分子の厳密な数学的な定義から始まり、結果に至るまでに難解な証明がいくつもあった発表を全て理解できたとはもちろん言えないが、普段機械学習を主に扱う自分にとってはとても新鮮であった。また、発表後にHuangさんが、数理生物学の分野では様々な数理的手法が多々開発されているものの、それらをどういった生命科学の課題に適用するかを見極めるのが難しいと感じる研究者が多いと仰っていたことが印象に残った。近年の生命科学データの蓄積と技術の進展に伴い、AIと生命科学の融合が非常に盛り上がっているが、純粋数学の強みを活かすような研究も展開できればより幅が広がるのではないかと感じた。機会があれば一度数理生物学会にも参加してみたい。
ポスター発表では抗がん剤効果予測のプロジェクトの成果を発表した。本学会のポスターセッションは二日間にわたって実施されたため、分子生物学会などの大規模な学会と比較すると、より余裕を持った発表ができた。ありがたいことに、両日とも多くの方々にポスターに足を運んでいただいた。ポスター発表の際には複雑な多段階のモデル構造の詳細を可能な限り簡潔にかつわかりやすく説明することを意識した。いただいた主な質問としては、モデルの入力の詳細や、既存モデルと比較しての新規性、そして臨床現場だけでなく創薬への応用可能性に関する質問をいただいた。コンピューター解析を主軸にした生命科学、薬学、医学など幅広い分野の方々と濃密な議論を交わすことができ、とても有意義な時間となった。
今年のバイオインフォマティクス学会年会のテーマは「生命・医薬科学とその先へ越境するバイオインフォマティクス Ver2.0」であった 。大規模生命科学データの蓄積と、基盤モデルをはじめとするAI技術の進歩に伴い生命科学と情報科学を融合領域における研究が非常に活発になっているが、本当に価値のある研究成果を出すことはとても難しいと日々感じている。生命科学における特定のタスクに対して、単に精度の高い予測モデルを構築するだけでなく、その先にある「なぜこの研究が必要なのか」という問いを意識しながら、今回の学会参加にて得られた知見やアイデアを活かし、研究に取り組みたい。