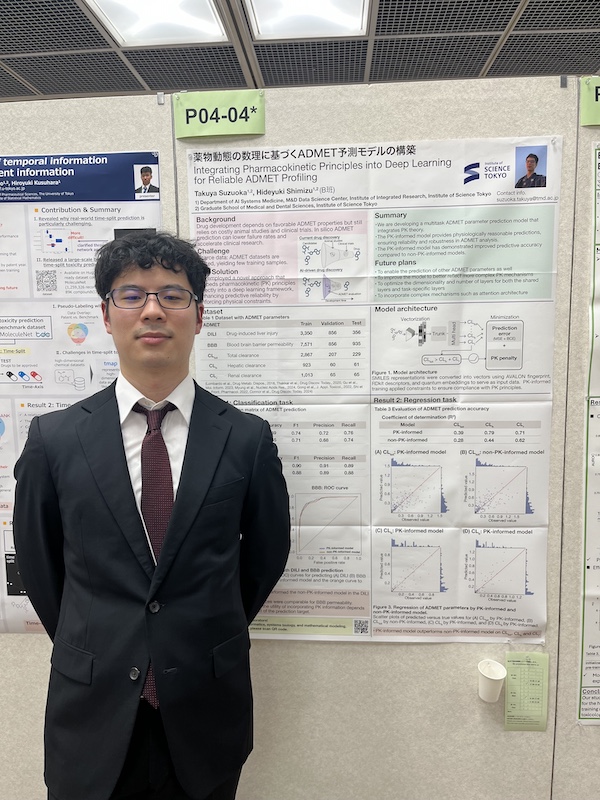CBI学会2025 参加報告
10月27日から30日にかけて開催された、CBI学会の年会に参加した。本学会は、バイオインフォマティクス、計算化学、構造生命科学、医療情報、AI技術など、創薬研究に関わる多様な分野の最新知見が一堂に会する重要な機会であり、今秋から創薬エージェントのプロジェクトを始めたこともあり、参考になる知見があればと思い参加するに至った。特に本年は、ハイゼンベルクによる「行列力学」発表から100年目ということで、予てより気にはなっていた量子コンピューティングについても多くのセッションがあり、想定以上の収穫を得ることができた。
学会初日は、CBI研究機構内に設置された各研究所の活動報告と、最新の研究成果についてのセッションを聴講した。量子構造生命科学研究所、次世代モダリティ研究所、先端領域ELSI研究所、生体分子デザイン研究所と四つの研究所のお話があったが、中でも生体分子デザイン研究所の浜田省吾先生のお話は大変興味深く拝聴した。
DNA、タンパク質、脂質膜などを合理的にデザインし、分子ロボットや人工細胞を開発する研究は世界的に盛り上がっているが、基礎研究から社会実装(産業応用)への「ハブ機能」が日本に不在であるという課題認識のもと、当研究所は研究推進、人材教育、産学連携の3本柱で、そのハブとして機能することを目指しているとのことであった。
研究所の活動の核は、教育プロジェクトとしてのBIOMOD(国際分子ロボコン)運営である。これは、学部生がチームで一夏をかけ、独自の分子ロボットを設計・製作・評価し、国際大会で競うものとのことだ。BIOMODは2011年にハーバード大学Wyss研究所の打診で発足し、コロナ禍で国際大会が中止になった際も、日本では独自に国内大会を開催しコミュニティを維持した。2023年に初の米国外開催として日本(Tokyo Tech)で国際大会を成功させたことが大きな転機となり、これがCBIでの研究所設立の直接的な契機となった。直近では10月に中国・吉林大学で2025年大会が開催され、G-quadruplex(G4)で制御するDNA膜構造を開発したチームが優勝したとの報告があった。来年(2026年)はメキシコ大会が予定されている。研究所はBIOMOD運営のほか、産学連携ハブとしてバーチャル研究所(東北大、名大など)を整備する「共有実験拠点ネットワーク部門」も推進中である。このように教育を行いながら、分野のイノベーションを牽引していくという活動はかなり独自性が高く、大変興味深く拝聴できたご講演であった。
二日目は、創薬研究の基盤となる計算科学技術(HPC、量子)に焦点を当てたセッションを中心に聴講した。
東京科学大学の秋山泰先生からは、GPUへの移行を中心としたHPCの最新動向と創薬への応用が紹介された。2025年は「本邦の科学技術がGPUに振り切った年」として記憶されるだろうとのことで、本学のTSUBAME4.0や産総研のABCI 3.0 / ABCI-Qなどの主要インフラが最新GPU(H100/H200)基盤となり、RISTなどの国の支援も既存のCPUベースアプリケーションのGPU移植を強く後押ししている現状が説明された。ただ、それでも重要なのは、単に巨大な計算機を導入するだけでなく、その性能を最大限に引き出す「正しい方法論」と「効率的な利用技術」であると強調されていたことは印象的であった。
また、その後のプレナリー講演「量子コンピューティングが開く未来」では、産総研G-QuATの益一哉先生(東工大前学長)より、量子技術を巡る社会と研究開発の動向が語られた。科学技術とビジネスの関係性が急速に変化し、ビジネス(B)、サイエンス(S)、テクノロジー(T)が分離せず、渾然一体となって高速で進む「Agile Dynamic Society」への移行を意識する必要があり、予測困難な時代において「柔軟性」と「越境」が鍵となるという旨が、度々強く指摘されていたことが印象的であった。
前述の生体分子デザイン研究所同様に、アカデミアの基礎研究と社会実装を「Agile Dynamic Society」のスピード感で繋ぐ「橋渡し」として、産総研にG-QuAT(量子AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター)が新設された(2024年10月〜)。日本政府は、停滞の30年を突破すべく量子・AI分野へ大型支援を行い、「2030年までに量子技術使用者1000万人」という目標を設定している。量子コンピュータについてはこれから先必ず必要な技術となることがわかっている一方で、まだ自分自身の学習が不十分である自覚はあったため、この機会に基本を一通り学ぶことができた点も有意義なものであった。
三日目は、医療情報の利活用が創薬研究、特に標的探索にどのような変革をもたらすかについてのセッションを聴講した。中でも大変興味深かったのが、大阪大学微生物病研究所の石谷太先生の「健康長寿の合成生物学」であった。
細胞レベルの老化メカニズムの理解は進む一方、「個体レベル」の老化制御の解明は、ヒト(時系列情報不足)やマウス(実験に時間がかかりすぎる)では困難であった。このボトルネックを解消する最適なモデルとして、先生はターコイズキリフィッシュ (N. furzeri) での研究をおこなっておられる。この生物は、飼育可能な脊椎動物で最も短命(寿命約半年)でありながら、ヒトと類似の老化形質(白内障、運動能力低下など)を示し、特にマウスにはない「メス > オス」というヒトと共通の寿命性差を持つため、老化の性差研究に最適であるとのことであった。
詳細は割愛するが、この性差や加齢に伴う各種生理現象がなぜ起こるのかを解明していくご発表は非常に知的好奇心を刺激するものであり、一研究者としてのプレゼンテーション法としても非常に多くのことを勉強させていただくことができた。
学会最終日は、現在最も注目を集める技術である「生成AI」に焦点を当てた招待講演を聴講した。若くして優秀な研究者として活躍されている東北大学の東北大学の赤間先生、Preferred NetworksやSakana AIといった超一流のAI研究企業でご活躍されている水野先生、高橋先生、中郷先生という素晴らしい演者の方々のお話はどれも引き込まれるようなプレゼンテーションであり、一時間半という時間があっという間に感じられた。
中でも、やはり自分自身が創薬エージェントの開発をテーマにしていることもあり、Sakana AIの中郷先生のご講演は非常に参考になるものであった。Sakana AIの研究として、「集合知による新たなモデル構築」、「AI Agent Workflowの自動化」、「AIが目指すベンチマーク自体の発明」の三つの分野で具体的な研究プロジェクトについて幅広く聴講することができた。
なかでも、やはりAI agentについては、自分の生命科学とは少し分野が異なるとは言え、毎年ものすごいスピードで新たな論文を発表しておられ、言わずもがな自分自身の研究プロジェクトにも大きな刺激を受けるものであった。
また、最後のベンチマークの発明については、AIの進化速度が速すぎて、もはや既存のベンチマークでは次々とAIに解き尽くされ、AIの真の能力を測れなくなってきているという背景があり、それを踏まえていまやAIの性能を「どのように上げていくか」だけでなく、「どのようなベンチマークで測るか」をセットで発明・提案することが、AI研究の加速に不可欠であるというものであった。このような情報科学の領域での研究の動向を、AI研究の最先端を走る企業のメンバーの方からうかがうことができたことも、大きな収穫と言えるだろう。
以上、今回の学会の参加報告となる。
本学会は、創薬研究のパラダイムシフトを強力に牽引する多様な技術の最新動向を、分野横断的に把握する絶好の機会となった。
総じて、構造情報、医療情報、計算パワー(GPU、量子)、そしてAIという全ての要素が劇的に進化・融合しつつある現在地を確認できたことは大きな収穫であった。これらの技術動向を継続的に注視し、今後の研究開発に積極的に取り入れていく必要があると実感した。

この度、2025年10月27日から30日に東京都江戸川区のタワーホール船堀で開催された「CBI学会2025年大会」に参加しました。今回はポスターなどの発表もなく、自己研鑽として参加させていただきました。日程の都合上、28日(2日目)・29日(3日目)の全日と30日(4日目)午後のみの参加となりましたが、本学会への参加を通して得られた学びについて、印象に残った2講演とポスターセッションについてを中心に共有させていただきます。
印象に残っている講演の1つは、東京工業大学の前学長の益先生による「量子フロンティア ― アジャイル・ダイナミックな共創による未来形」です。この講演では最初に、現代のイノベーションを基礎研究・応用研究・社会実装・ビジネス創出が同時進行するアジャイルダイナミック社会として提示し、この予測困難な時代を勝ち抜く鍵は「柔軟性」であると強調されました。
量子コンピュータ開発は、実用化が2050年代から2030年代へと前倒しされるほど開発が加速しており、現在は多様な方式が乱立していてどの方式が主流となるか予断を許さない状況です。量子回路を用いて汎用的な計算を目指すゲート方式(汎用型)だけでなく、東工大の西森先生が開発された量子アニーリングの基礎理論を利用し、エネルギーが最小となる安定状態を探索する組合せ最適化問題に特化したアニーリング方式が日本の強みとなっています。日本政府も2021年にグリーンイノベーション基金(2兆円)を設立するなど量子・AI分野へ大型支援を行っており、「2030年までに国内の量子技術使用者を1000万人にする」国家目標も設定されました。この中で、アカデミアの基礎研究とアジャイルダイナミック社会が求めるスピード感での社会実装との間にある「橋渡し」の役割を担うための産総研の取り組みが紹介されました。まさに、日本が一丸となって量子技術の発展を支えるため、多様なヒト・モノ・知を集積しグローバルに産業を発展させる拠点としての役割が期待されていると感じました。
しかし、後の講演でも紹介されていましたが、量子コンピューティングに関しては現場(例えば製薬企業)の期待と現在の技術の実力との間に依然として大きな「ギャップ」が存在するという現実があり、今すぐの実用化は難しそうでした。技術的な「転換点」が来たときに即座に対応できるよう、ハードウェア・ソフトウェアの動向を継続的に注視し、「転換点」に乗り遅れないための準備をすることが重要であると強く感じました。来年度のCBI学会のテーマも「量子生命科学が拓くヘルスケアへの未来」ということで、量子AIの分野を今後キャッチアップしていくことはますます重要であると感じました。
これまで量子技術についてはなんとなく聞いたことがあったものの詳細についてお伺いする機会が全くなかった自分にとって、益先生の講演は非常にテンポ良く軽妙な語り口で理解を深めることができました。益先生は講演の中で東工大改革の例を挙げながら、「予測困難で変化が早い現在において、自分では頑張っているつもりでも周りはもっともっと早く対応している」と指摘されており、前学長の立場からアカデミア(特に次世代を担う若い学生)に対して厳しくも愛のあるエールを送られていました。また、質疑応答の中で、「どの決断をするべきかを悩んで何もしないことが一番良くない」と述べられており、何をしていくかを悩んでなかなか次のアクションが踏み出せないことが多い自分にとってはすごく心に刺さりました。
また、大阪大学微生物病研究所の石谷先生による「『健康長寿の合成生物学』〜オミクスデータから見つけた因子を利用して超短命動物に健康長寿を合成する〜」も印象に残っています。この講演では、細胞レベルの老化メカニズム(細胞老化やオートファジー低下など)の理解が進む一方で、未だ不明な点が多い「個体レベル」の老化制御機構(個体差や性差を生む分子基盤)の解明に向けた研究が紹介されました。
個体レベルでの研究を行うにあたってのボトルネックとしては、ヒトデータの時系列情報の不足やマウス実験の長時間化などが挙げられます。石谷先生はこれを解消するモデル動物として、「ターコイズキリフィッシュ」に着目されました。ターコイズキリフィッシュは寿命が約半年と、飼育可能な脊椎動物で最も短命であるだけでなく、白内障や運動能力低下などヒトと類似の老化形質を示し、マウスでは見られない「メスがオスよりも長寿である」というヒトと共通の寿命性差を示すということから、「ヒトの老化における性差の分子基盤研究にターコイズキリフィッシュは最適である」と述べられていたことが印象に残っています。
これらのターコイズキリフィッシュを用いた研究により個体の老化を制御する因子について、複数の例が示されました。ここでは未発表データも含まれているので一部のみの感想を共有したいと思いますが、「出産数が少ない動物種ほど長生きである」という生殖と寿命のトレードオフ仮説に基づき、生殖細胞が寿命性差に与える影響が検証されました。生殖細胞(精子)のみを除去したオスの寿命は延長し、生殖細胞(卵)を除去したメスの寿命は大幅に短縮しました。延長したオスの寿命と短縮したメスの寿命が同程度となり、フェノタイプからは生殖細胞が寿命の性差に与える影響が示唆されました。比較トランスクリプトーム解析により、オスの肝臓で活性型ビタミンD合成酵素の発現上昇が特定され、実際に活性型ビタミンD(アルファカルシドール)を水槽に添加するとオスの野生型の寿命が延長しました。一方で、メスでは女性ホルモンの減少がIGFシグナルの過剰な上昇を引き起こすことも明らかとなり、生殖細胞の存在がヒトと共通する「メスがオスよりも長寿である」という寿命の性差を生み出す主要因である可能性が示されました。
講演を通して、ヒトの老化研究における最大のネックである「時間(寿命の長さ)」と「性差(マウスでは不明瞭)」という2つの問題を同時に解決できるターコイズキリフィッシュという実験モデルに着目した点に非常に重要な点が隠されていると感じました。また、フェノタイプの観察からオミクス解析でビタミンDやIGFシグナルといった具体的な分子メカニズムにまで落とし込んでいる点が鮮やかで、データ解析から得られた仮説を実際に実験検証できている点が自分にとっても目指すべき方向性であると感じた研究でした。また、ビタミンDは個人的に学部の研究で少し扱っていたターゲットであったので、新たにアンチエイジングホルモンとして機能する可能性が示されたことは非常に面白い話であると感じました。
最後に、タワーホール船堀の大ホールで行われた144件のポスターセッションについて述べたいと思います。これまでに参加したバイオインフォマティクス学会と比べても製薬企業からの参加者がはるかに多く、ポスター発表でも3分の1程度を占めていました。また、Science Tokyoからの発表者も全体の3分の1程度を占めており、この分野での東京科学大学のプレゼンスの高さを垣間見ることができました。CBI(化学生物情報)学会ということもあり、ポスター発表全体で見ると半数程度がMDシミュレーションなどをはじめとした物理化学や有機化学と情報科学領域の融合分野、残りの半数程度がバイオインフォマティクスや創薬応用を見据えた分野の発表で、自分の分野と少し離れていると感じた発表も多くありました。今回のセッションでは自分のプロジェクトにも今後関連してくることを鑑みて、特にADME関係のポスターを重点的に見ましたが、来年度以降参加する際にはさらに今回あまりカバーできなかったケモインフォマティクスや分子ロボティクスのような分野にもついていけるように勉強を重ねたいと感じました。ADMET予測の発表を行われていた複数のプレゼンターとのディスカッションを通して、薬物動態パラメータ予測の現状やデータの少なさ、それに伴う精度の低さなどの課題について学ぶことができました。さらに、これまでに参加したバイオインフォマティクス学会や潜在空間リトリートで知り合った先生方や学生さん、企業の方ともお話することができ、自分は発表していませんでしたが研究の進捗を含めた近況報告ができました。当然ながら発表した方が得るものはさらに多くあると感じましたので、(CBI学会に限らず)来年度には是非発表したいと感じました。
この度は、このような貴重な機会とご支援をいただきまして、改めて感謝申し上げます。

この度、2025年10月27日から30日にかけて開催された2025年度CBI学会に参加する機会を頂いた。CBI学会は、Chem-Bio Informaticsの略称の通り、化学(Chemistry)、生物学(Biology)、情報科学(Information)という3つの学問分野の融合を掲げ、創薬をはじめとするライフサイエンス研究の先端的な基盤構築をテーマにしている学会である。私自身、AIによる抗体分子の設計や、化合物のADMET予測・PBPKシミュレーションに関する研究に携わっているため、本学会は私の研究分野と密接に関連する最新の知見を得る非常に貴重な機会であった。学会は4日間にもわたる中、HPC (High Performance Computing) や量子コンピュータといった次世代計算基盤の創薬応用、生成AI・AIエージェントによる科学的発見の自動化、そしてそれに伴う倫理的・社会的課題に至るまで、極めて広範かつ先進的な議論が交わされていた。特に、ポスターや口頭発表の多くがAIや言語モデルを活用した研究であったのが印象的であり、近年の深層学習やLLMの爆発的な発展が、従来のバイオインフォマティクスやケモインフォマティクスの枠組みを大きく超え、創薬プロセスのあらゆる側面に変革をもたらしている現状を強く実感した。
本報告書では、学会全体を通して特に印象に残り、今後の自分の研究において重要な示唆を与えてくれたいくつかの研究をピックアップして、私なりの感想や考察を述べる。
今回のCBI学会で私が非常に印象深いと感じた研究領域は3つである。
一つ目は、「生成AIによる生命科学研究や科学的発見の加速」である。4日目の招待講演「生成AI:未来を紡ぐ知のエンジン」で集中的に議論されたように、大規模言語モデル(LLM)を始めとする生成AIは、単に文献情報を要約したり、既知のデータから活性を予測したりする段階をとうに超えている。Sakana AIの「AI Scientist」の試みのように、AIが自ら仮説を立て、実験計画(あるいは計算計画)を立案し、結果を解釈し、論文執筆まで行うという、科学的発見のプロセス自体を自律的に実行するエージェントAIの構築が現実のものとなり、さらにこのようにして自律的に行われた研究がICLRのような世界トップクラスの国際会議のワークショップに採択されるレベルとなっている。これは、研究者の役割そのものを変え得るイノベーションが起きつつあり、その渦中にいるのだなと感じた。
二つ目は、「次世代計算基盤(HPC・量子コンピュータ)によるシミュレーションの実用化と未来」である。2日目の秋山先生(HPC)や益先生(量子)、中外製薬(量子)の講演を通して、次世代の計算基盤として期待されている技術が創薬の領域を確実に変革してきている実感を得た。たとえば、GPUなどの多くの計算リソースに支えられているHPCは、膨大かつ複雑なデータを高速に処理する高性能な計算システムであり、かつては膨大な計算時間を要したFEP(自由エネルギー摂動法)による結合自由エネルギー計算などを、創薬現場で使える実用的な技術へと押し上げた。さらにその先を見据え、古典コンピュータでは原理的に困難とされる最適化問題や量子化学計算を解く鍵として、量子コンピュータへの期待と投資が(もちろん、本当に実用的なものなのかという懐疑的な見方も含め)真剣に議論されていた。従来の技術では莫大な計算量が必要なため、手の届かなかった非常に精密な分子動態シミュレーションが、次世代の計算基盤技術の向上によって現実のものとなり、創薬におけるシミュレーションの精度を飛躍的に向上させている現状を知れ、非常に貴重な最先端のお話を聞くことができた。
三つ目は、「動物実験代替へ向けたin silicoのADMET予測やPBPKシミュレーションの高度化」である。学会3日目の午後に行われた「計算ADMET研究会」フォーカストセッションにおいて、この分野の著しい進展を学ぶことができた。PBPK(生理学的薬物動態)モデルと機械学習の融合、既存の毒性情報を活用するリードアクロス手法の体系化、そしてAlphaFold DatabaseのようなAIによる構造予測データベースを活用した網羅的分子ドッキング(Binding Proteomics)による毒性標的探索など、計算科学が創薬のボトルネックの一つである毒性や安全性評価の領域でいかに強力な武器となりつつあるかが示唆されており、今後データがどんどん蓄積していくことによって大きな発展が期待される分野となると感じた。一方で、現状の予測精度は極めてブレが大きく、ADMET予測とひとくくりに言っても、得意な予測と不得意な予測がはっきり分かれている印象である。データ数も少ないため、この領域はまだまだ発展途上だと言わざるを得ないが、もし今後成長していけば、社会的意義の非常に大きい研究分野になってくるであろうと感じた。
以下では、これらの潮流の中で特に印象深かった講演内容について、より詳細に掘り下げていきたい。
2日目のプレナリー講演「量子コンピューティングが開く未来」では、産総研G-QuATの益 一哉 先生、中外製薬の荒川 晶彦氏による講演が行われ、非常に印象的であった。まず、産総研G-QuATの益先生による「量子フロンティアーアジャイル・ダイナミックな共創による未来形」と題した講演は、量子コンピュータの発展について、より長期的かつマクロな視点を提供するものであった。益先生は、現代を「Agile Dynamic社会」と定義し、かつてのリニアモデル(科学→技術→ビジネス)ではなく、基礎科学から実用化までが同時並行で進むサッカーのパス回しのような時代であるとおっしゃっていた。私はまさにその通りだなと非常に感銘を受けた。 そのようなAgile Dynamic社会の象徴が量子コンピュータであり、益先生はゲート方式とアニーリング方式の現状を冷静に比較しつつ、現在は誤り訂正技術がロードマップの中心にあり、非常にホットな研究対象になっていると解説していた。産総研が推進する「G-QuAT」構想(ABCI-Qなど)は、まさにこの次世代計算基盤のユースケース開拓と人材育成(未来への投資)を目指すものであり、日本の産業競争力強化への強い意志を感じ、今後の量子コンピュータ含めた周辺領域の発展に目を光らせていきたいと思った。
次に中外製薬の荒川氏による講演が行われ、製薬企業の立場から量子コンピュータ(QC)にどう取り組んでいるかについての現実的な報告を聞くことができた。中外製薬は環状ペプチドを第三のモダリティとして推進しており、そのドッキング計算のハードル(コンフォメーションの複雑性や計算の膨大さ)をQCで解決できないかと期待し、デロイトと共同研究を行ったようである。結果としては、現状のQC技術では古典計算に対する「量子コンピュータの優位性」は確認できなかったとのことだが、これは非常に重要な報告であると感じた。荒川氏のお話では、現状のQC技術が創薬にインパクトを与えるにはまだ多くのハードルがあることを認めつつも、その可能性にいち早くベットし、ユースケースの探索を続ける企業の姿勢が示されており、まさに「Agile Dynamic社会」の実践例であると一連の講義を受けて感じた。
次に、4日目に行われた招待講演のうち、Sakana AIの中郷 祐幸氏による「生成AIの最前線:Sakana AIが推進する研究の方向性」は、本学会で最も刺激的だった講演の一つであった。Kaggle Grandmasterとしての実績も持つ中郷氏が提示したSakana AIの研究方針は、現在のLLM開発の主流である「巨大データや計算資源によるさらなるスケーリング(大規模化)」とは少し異なった、非常にユニークで興味深い研究が目白押しであった。
Sakana AIはリサーチに特化し、特に「モデルの組み合わせによる集合知」「エージェントワークフローの構築」「社会貢献可能なベンチマーク作成」の三点に注力しているというお話であった。圧巻だったのは、「集合知」の実現に向けた具体的な取り組みである。現在、Hugging Faceなどには200万以上もの事前学習済みモデルが公開されている。Sakana AIのアプローチは、これらの既存モデルをゼロから再学習するのではなく、それらを「融合」させることで、個々のモデルを超える高性能なモデルを低コストで創出しようとするものであった。その具体的手法として紹介された「Evolutionary model merge」(Nature Machine Intelligence採択済み)は、進化的アルゴリズム(突然変異や自然淘汰)の着想を用い、データセット不要、かつ低コストで複数のモデルの重みを融合させる手法である。さらに「M2N2」(NeurIPSに採択)では、複数の異なるモデル(フロンティアモデルのような重みが非公開のモデルも含む)を活用し、モンテカルロ木探索のように各モデルに推論させながらアンサンブルすることで、単体モデルを超える性能を引き出す研究も行われていた。これは、巨大な単一モデルを構築する「スケールアップ」に対し、多様な既存知能を組み合わせる「スケールアウト」的なアプローチであり、計算資源が限られるアカデミアや多くの企業にとって、極めて現実的かつ強力な戦略となり得ると感じ、このようなSakana AIの研究スタイルには非常に感銘を受けた。さらに衝撃的だったのが、「AIエージェントワークフロー」の研究である。特に「AI Scientist」と名付けられたプロジェクトは、論文のアイデア生成から実験(計算)、論文執筆、評価までの一連の研究プロセスをAIが全自動で行うという、まさにSFのような試みであると感じた。驚くべきことに、このAIが生成した論文(v2)は、ICLR(機械学習のトップカンファレンス)の査読を通るレベルに達しているという。これを実現するために、単なるLLMの探索に留まらず、具体的なドメイン知識を組み込んだTree based searchによる探索や、VLM(Vision-Language Model)による論文中の画像(Figure)の妥当性チェックまで組み込まれているとのことであり、Sakana AIの研究に散りばめられている研究アイデアのエレガントさに思わず唸ってしまった。また、「ADAS」という、あるタスクに対して最適なAIエージェントのワークフロー自体をAIに自動設計させる技術や、「DGM (The Darwin Godel Machine)」という、AIが自らプログラムを書き換えて試行錯誤し自己改善していく枠組みなど、非常に大量の革命的な研究が次々と紹介され、Sakana AIの研究レベルの高さや研究遂行力に非常に感銘を受け、我々も負けてられないとモチベーションになった。
今回のCBI学会2025年度大会への参加は、化学・生物・情報学が融合し、創薬技術の発展という壮大な目標に向かってダイナミックに進歩している現在進行形の様子を体感することのできる、非常に貴重な経験となった。本学会で得た数多くの知見と、最前線で活躍される研究者たちの熱意を糧とし、私自身も現在取り組んでいるAIによる抗体設計などの研究分野で、少しでもこの研究分野に貢献できるような研究成果を生み出すべく、より一層精進していきたいと強く決意した。
最後になりますが、このような貴重な学会参加の機会を与えて頂きましたことに、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

2025年10月27日から30日にかけて、東京 (船堀) にて開催された「CBI学会2025年大会」に参加いたしました。
本学会は、昨年度に引き続き参加しましたが、アカデミアの研究者のみならず製薬企業からの参加者が非常に多く、基礎研究から応用・実用化までを見据えた「創薬」色が極めて濃い学会となっています。
私自身、現在「AI創薬」(化合物とタンパク質の相互作用予測)に関する研究に取り組んでおり、今回の参加にあたっては、以下の3点を主な目的といたしました。第一にAI創薬分野における最新知見を収集すること。第二にポスター発表を通じた、研究への建設的なフィードバックを獲得すること。第三に、製薬企業とアカデミア、両分野のAI創薬研究者との交流を通じた、最新動向の把握とネットワークの構築すること。
本報告書では、4日間の学会参加を通じて得られた学びや所感について、特に印象に残った講演や自身の発表を中心に、報告いたします。
学会初日、まずは「KNIMEを使ったケモインフォマティクス入門」のチュートリアルに参加しました。本セッションは、ワークフロー構築型ツールKNIMEを用い、医薬品データを題材に、データ読み込み、前処理、活性分類モデル(ロジスティック回帰、ランダムフォレスト)の構築と評価までをノーコードで体験する内容でした。
私自身は普段Pythonを直接記述して研究を行っていますが、KNIMEは情報学のバックグラウンドを問わず直感的に操作できます。製薬企業のバリューチェーン全体において、専門家以外も含めた全社員向けの機械学習研修や、現場レベルでの迅速なデータ解析導入において非常に有効なツールであると実感しました。
初日に聴講した中で特に強烈な印象を受けたのが、京都大学 川又生吹先生による若手奨励賞受賞記念講演「生体分子デバイスを統合した分子ロボットの展開」でした。
川又先生は、情報科学をバックグラウンドに持ちながら、工学、物理、生物学の垣根を越え、文字通り「分子でロボットを作る」分子ロボティクスの研究を推進されています。本講演では、分子ロボットの主要な構成要素である「構造」「知能」「運動」をいかにして「統合」し、自律的なシステムを構築するかが主題でした。
まず「構造」デバイスの例として、化学シグナルに応答して動的に変形する「DNAオリガミ・ナノスプリング」の研究が紹介されました。これは、DNAオリガミの連結部分に特定のDNA配列を組み込んだもので、カリウムイオン(K+)の存在下ではDNAがG-quadruplexと呼ばれる特殊な立体構造をとり、ナノスプリング全体がコイル状に縮みます。さらに、anti-GQ鎖と呼ばれる相補的なDNA鎖(シグナル)を加えることで、その構造がほどけて逆方向に曲がります。このように、外部からの化学シグナルによってナノスケールの「バネ」の伸縮や向きを精密に制御できる点が非常に画期的でした。
続いて、この「構造」を動かす「運動」と「知能」のデバイスを統合した成果として、DNAベースの分子コントローラによって制御される「自律滑走分子ロボット」の研究が紹介されました。
この研究では、「運動」デバイスとしてキネシン駆動型の微小管(MTs)を、「知能」デバイスとして酵素とDNA鎖からなる化学反応回路(DNAコンピューティング)を用います。驚くべきことに、これら全てのコンポーネントを単一の溶液内に混合するだけで、このDNAコントローラはプログラムされた時間差で2種類の異なるDNAシグナルを自律的に生成します。第一のシグナルは滑走する微小管同士を結合させ「群れ」を形成させ(集合)、一定時間経過後に生成される第二のシグナルがその結合を解除し、群れを「解散」させます。
これは、外部からのマニュアル操作を一切必要とせず、分子プログラムが分子モーターの集団的な振る舞いを自律的に制御可能であることを実証した画期的な成果でした。
今回紹介されたDNAコンピューティングは、「集合」と「解散」といった時間差での逐次的なシグナル生成であり、現状ではシリコンベースのコンピュータが行うような複雑な演算処理は難しいです。しかし、この分子プログラムがより高度化・集積化されていけば、例えば「特定のバイオマーカーを感知した時だけ作動するDDS」など、より知的な分子ロボットの実現に繋がる重要な基盤技術であると強く感じました。
また、情報科学の観点からは、この「DNAコンピューティング」というアプローチ自体が、現代のコンピュータが直面する根本的な課題への一つの解となり得る点に感銘を受けました。近年、生成AIの急速な発展に伴い、その膨大な計算リソースを支える消費電力の増大が世界的な課題となっています。これに対し、生体分子の化学エネルギーを利用するDNAコンピューティングは、原理的に極めてエネルギー効率が高いです。川又先生が取り組まれているようなボトムアップ型の分子コンピュータは、将来的に、現在のトップダウン型シリコンコンピュータが直面するエネルギー問題や集積化の限界を、全く異なるパラダイムで解決する可能性を秘めています。情報科学と生命科学が融合する本分野の今後の動向を、引き続き注視していきたいと思いました。
学会二日目は、創薬研究の未来を支える3つの重要な技術トレンド、「量子コンピューティング」「クラウドインフラ」「基盤モデル」に関するセッションを中心に聴講しました。
プレナリー講演では、産総研の益一哉先生より「量子フロンティアーアジャイル・ダイナミックな共創による未来形」と題した講演がありました。特に印象的だったのは、現代のイノベーションの在り方を「アジャイル・ダイナミック社会」と表現されていた点です。かつての基礎研究から製品化までが一直線だったリレー方式とは異なり、現在は基礎科学、応用研究、ビジネス創出が同時に進行する「サッカーのパス回し」のような形になっているというお話は、分野の垣根を越えた連携の重要性を再認識させられるものでした。
続いて、中外製薬の製薬R&Dにおける量子コンピュータ活用の講演を聴講しました。量子コンピュータは「古典コンピュータでは解決不可能な計算課題に対処できる可能性」を秘めており、臨床画像解析や試験プロトコルの最適化 、そしてまさに自身の研究分野にも関連する「ターゲットと薬剤の相互作用解析」や「結合親和性予測」への応用が期待されています。一方で、中外製薬が取り組まれていた環状ペプチドのドッキングシミュレーションではまだ量子の優位性が確認できていないことや、タンパク質のような生体高分子のシミュレーション自体が依然として大きな課題であることなど、ハード・アルゴリズム両面での実用化に向けた課題も明確に示されました。
ランチョンセミナーでは、第一三共のAWSを活用した次世代創薬基盤の取り組みが紹介されました。「2030 DXビジョン」として「データとデジタル技術を駆使してヘルスケア革新に貢献する」ことを掲げ、Design, Make, Test, Analyze (DMTA) サイクルを高速に回すための基盤構築を進めているとのことです。
特に興味深かったのは、データを「中央管理型」にするのではなく、「自律分散型のデータメッシュ」というアーキテクチャを採用している点です。これは、各研究ドメインがデータオーナーシップを持つことで、中央集権的なシステムが陥りがちなボトルネックを解消し、変化への適応力とスケーラビリティを高めるという、非常に合理的な設計思想だと感じました。
また、小さな単位で検証を繰り返す「MVP(Minimum Viable Product)指向」での開発や、「Techを実現するためのnon-Techの重要性」といった視点も、変革を成功させる上で極めて重要だと認識しました。MVPによって現場の研究者のニーズを開発に素早く反映させ、同時に「既存ルールとの摩擦」といったnon-Tech(組織や人)の課題にも向き合うことで、初めてデジタル技術が現場に根付くのだということを学びました。このように、デジタル技術の導入が、いかに組織やプロセスの変革と一体になるかが重要であるということを認識し、将来製薬業界でのデジタル変革に携わる者として非常に示唆に富む内容でした。
学会2日目最後のセッションとして、「基盤モデルの最前線」に参加しました。東京科学大学の先生による「シングルセル基盤モデル」の講演では、従来の平面的な細胞研究とモデル動物とのギャップ(ヘテロ性)を埋めるオルガノイド研究に、scRNA-seq解析などを通じて複雑な細胞間コミュニケーションを解き明かそうとする試みが紹介されました。
このセッションで特に注目したのは、Preferred Networks社の講演「創薬におけるニューラルネットワークポテンシャルの応用」です。NNP(Neural Network Potential)は、原子番号と3次元座標を入力とし、計算コストの重い量子化学計算の高速・高精度なサロゲートモデルとして機能するものです。私自身、研究で量子化学的特徴量(記述子)を扱っているため、物理科学の基盤モデルとも言えるNNPが、今後どのように分子シミュレーションや物性予測の精度と速度を向上させていくのか、強い関心を持ちました。
学会三日目は、AI創薬の具体的な応用と今後の可能性に焦点を当てた「AI創薬・メゾスコピック化学討論研究会」に参加しました。
この研究会の中で特に印象深かったのが、塩野義製薬の「深層学習と計算科学の統合: Boltz-2と物理科学計算による創薬の展望」の講演です。この講演では、近年発表された新手法であり、高精度なFEP計算に匹敵する精度を1000倍以上の速度で達成する「Boltz-2」を使って、社内のインハウスデータを用いて複合体構造予測と結合親和性予測を行ったことが紹介されていました。アカデミア発の最新AI技術であるBoltz-2が、発表後即座に製薬会社のR&D現場で検証されているサイクルを目の当たりにし、AI創薬分野の技術導入の速さと競争の激しさを実感しました。
学会最終日である四日目は、「生成AI: 未来を紡ぐ知のエンジン」のセッションに参加しました。ここでは、東北大学言語AI研究センターの先生による、生成AIの進化予測に関する講演がありました。この講演では、現在の生成AIが汎用人工知知能(AGI)へと足を踏み入れつつあると述べられていました。また、性能向上の鍵として「たくさん学び、なおかつ出力する前によく考える(リーズニング)」ことが重要であり、この「リーズニング」能力によって、AIは単なる知識のオウム返しではない、より複雑な論理パズルや多段階の推論が可能になってきているとお話されていました。
この講演で最も深く考えさせられたのは、「ローカルな知識」の問題です。現在の生成AIは、世界中のWebから得られる「一般的な知識」の学習は得意ですが、特定の研究室や企業内でのみ通用する「例外的・局所的に正解な情報」の扱いは依然として難しいという指摘をしていました。AI創薬において、社内データ(ローカル知識)の活用はまさに中核的な課題であり、一般的な知識を持つ基盤モデルに、いかにして特殊性の高いローカルな知識を効果的に組み込んでいくか、そのアーキテクチャこそが今後のAI開発の鍵になると強く感じました。
最後に、本学会における私自身の活動として、ポスター発表についてご報告します。
学会期間中、自身の研究成果について発表を行いました。この発表の場では、熊本大学の杉本学先生をはじめ、製薬企業やアカデミアの多くの先生方から貴重なご質問やアドバイスをいただきました。
中でも、「タンパク質側の電荷の情報も特徴量として加えることで、予測性能がさらに向上するのではないか」というご指摘は、今後の研究の方向性を考える上で非常に有益なものでした。
また、懇親会などの場でも、多くの方々と発表内容について深く議論することができ、業界の動向やキャリアについて有益な情報交換を行うなど、活発なネットワークの構築をすることができました。
今回の学会参加を通じ、AI創薬の最前線について、特に以下の3点を強く実感しました。
第一に、最新のAI技術が即座に現場で検証される「AI創薬の技術革新の速さ」。第二に、情報科学が物理や生物学と融合していく「異分野融合の重要性」。第三に、AIの性能を最大限に引き出すために不可欠な「AI創薬をR&Dで利用するためのインフラ構築の重要性」です。
本学会で得たこれらの視点と、ポスター発表でいただいた具体的なアドバイスを糧に、修士論文の完成度を高め、今後のキャリアに活かしていきたいです。
最後に、このような貴重な機会と支援をいただきまして、改めて感謝申し上げます。

10月28日から30日にかけて開催されたCBI学会年会2025大会に参加した。本学会では、創薬化学からバイオインフォマティクス、AI創薬まで、幅広い領域の最先端の研究が一堂に会し、活発な議論が交わされていた。特に、大規模言語モデル(LLM)の応用や、量子コンピューティング技術の創薬への適用といったテーマは大きな注目を集めており、計算科学が創薬のパラダイムをいかに変革しつつあるかを肌で感じることができた。数多くの発表が行われる中、以下では本学会を通して特に印象に残った講演と自身のポスター発表について報告する。
数多くの発表の中で特に印象深かったものは、Sakana AIの中郷孝祐氏による「Sakana AIが推進する生成AI研究の方向性」と、アヘッド・バイオコンピューティング株式会社が主催するランチョンセミナーでの東京科学大学の柳澤渓甫先生による「量子時代のChem-Bio Informatics」と題した講演である。前者は生成AI研究の未来像を俯瞰するスケールの大きなビジョンを示し、後者は量子計算という次世代技術を創薬の現場課題に落とし込む具体的なアプローチを提示しており、両講演は現代のAI創薬研究が持つマクロとミクロの両側面を象徴しているように感じられた。
まず、中郷氏の講演は、Sakana AIの研究開発における基本思想の紹介から始まった。氏は前職のPreferred Networksでの経験を経て現職に至り、現在は応用研究チームの立ち上げを担っている。講演の核心はLLM時代の研究の焦点をどこに置くべきかという問いにあった。基盤モデルの性能を向上させる「学習」のスケール競争はすでに巨大テック企業が莫大なリソースを投じており、後発の研究機関が同じ土俵で戦うのは困難である。そこでSakana AIが着目するのが、コンピュータが人間より得意とするもう一つの領域、すなわち「探索」である。様々な課題をLLMを用いた探索問題として再定義し、「自然界からの着想」、特に「進化(Evolution)」と「集合知(Collective Intelligence)」をヒントに解決を目指すという研究方針は非常に独創的であった。具体的な取り組みとして、まず「集合知の形成」が紹介された。これは、Hugging Faceなどに存在する膨大な数の既存モデルをゼロから作り直すのではなく、賢く組み合わせることで新たな能力を引き出すアプローチである。その代表例が「Evolutionary Model Merge (EMM)」であり、進化的アルゴリズムを用いて複数のLLMの重みを自動で探索的にマージする。ファインチューニングや追加データが不要で低コストながら、例えば英語の視覚言語モデルと日本語LLMを融合させることで、日本の「青信号」を文化的な文脈で理解できるVLMを構築するなど、目覚ましい成果を上げていた。このアプローチは、多目的最適化に対応した「CycleQD」や、GPT-4のような非公開モデル群を協調させて思考させる「AB-MCTS」へと発展しており、単にモデルを組み合わせるだけでなく、そのプロセス自体を最適化しようとする姿勢に感銘を受けた。次に、研究の方向性を定める羅針盤としての「ベンチマークの確立」の重要性が語られた。生成AIの進化は速く、既存のベンチマークはすぐに陳腐化してしまう。そこでSakana AIは、PyTorchコードを高速なCUDAカーネルに自動変換する「ACE-Bench」や、人間の「ひらめき」に近い推論力を測る「Sudoku-Bench」、さらには金融不正検知や物流最適化といった現実社会の課題を直接扱う「EDINET-Bench」「ALE-Bench」など、社会実装価値の高いベンチマークを自ら創出している。研究の主役が手法から課題設定そのものへ移りつつあるという指摘は、研究者としての姿勢を考えさせられるものだった。最後に、研究プロセス全体の自動化を目指す「AI Scientist」や、そのワークフロー構築自体をAIに委ねる「Meta Agent」といった壮大なプロジェクトが紹介された。特にAI Scientist v2がICLRワークショップの査読を通過するレベルの論文を自動生成したという事実は衝撃的であり、AIが科学的発見のパートナーとなる未来を強く予感させた。
次に、柳澤先生の講演では、量子アニーリング技術を用いた大規模バーチャルスクリーニング手法「FraSCO-VS (Fragment-based Screening powered by Combinatorial Optimization-Virtual Screening)」が紹介された。この研究は、NEDOの支援のもと、アカデミアと複数の企業が連携して進められている。背景にあるのは、Enamine REAL Databaseのような数十億化合物規模のライブラリに対し、従来のドッキング計算を全化合物に適用するのは計算コスト的に不可能であるという、創薬化学における喫緊の課題である。この課題に対し、本研究では大規模ライブラリの化合物が比較的小さな「フラグメント」の組み合わせで構成されている点に着目した。全化合物ではなく、数万種類程度のフラグメントに対して事前にドッキング計算を行い、その膨大な配置の中から最もらしい組み合わせを「組合せ最適化問題」として解くことで、計算量を劇的に削減するというアイデアである。このアプローチの独創性は、組合せ最適化の求解に、東芝が開発したイジングマシン「SQBM+」という疑似量子アニーリング技術を応用している点にある。各フラグメントの配置を採用するか否かをバイナリ変数で表現し、ドッキングスコアや化学的な妥当性(結合、衝突など)を考慮した目的関数(QUBO形式)を最小化する。疑似量子アニーリングの利点は、最適解だけでなく、それに近い多数の準最適解を一度に得られることであり、これにより多様な結合様式の候補を網羅的に探索できるという説明は非常に説得力があった。性能評価では、10万化合物のライブラリに対して従来の約50倍の高速化を達成しつつ、精度は標準的な手法と同等以上を維持するという結果が示された。さらに、実証実験では実際に新規の阻害剤を発見することに成功しており、本手法の実用的なポテンシャルを強く印象付けた。量子計算という、まだ基礎研究段階のイメージが強い技術を、バーチャルスクリーニングという創薬現場の具体的なボトルネック解消に結びつけ、実用レベルの成果を示している点は非常に刺激的であった。計算手法の工夫と次世代のハードウェアを組み合わせることで、これまで不可能とされてきた壁を乗り越えようとする本研究は、今後の計算創薬のあり方を示唆する重要な一例だと感じた。
最後に、自身のポスター発表について述べたい。昨年度、本学会は聴講のみであり、来年は発表したいと考えていたので、今回ポスター発表をすることができてよかった。今年開催された学術変革領域A潜在空間の公開シンポジウムや前回のバイオインフォマティクス学会の際に訪れてくれた方が多く、前回からの研究のアップデートに関する質問などをいただくことができた。また、幸運にも学生発表奨励賞をいただくことができ、バイオインフォマティクス学会に続き2つ目の受賞となった。自身の研究が評価されたことを大変光栄に思うと同時に、大きな励みとなった。この受賞は、日頃からご指導いただいている清水先生をはじめ、発表準備に際して丁寧に助言をくださった研究室メンバーの皆様のご支援の賜物です。この場を借りて深く感謝申し上げます。