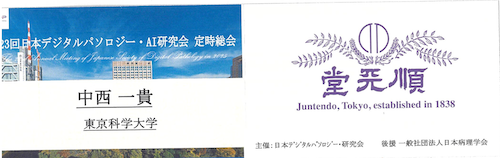第23回デジタルパソロジー・AI研究会 参加報告
この度、2025年9月13日から15日にかけて順天堂大学・本郷御茶ノ水キャンパスで開催された「第23回デジタルパソロジー・AI 研究会年次総会」に参加しました。今回の学会は発表会場が1つでポスター演題が12に対して企業ブースが20以上と、かなり産学交流にも重きが置かれていたことが印象的でした。今回の学会参加を通して得られた学びを、印象に残った講演を中心に共有させていただきます。
1日目では他のデジタルパソロジー学会との国際セッションが多く、デジタルパソロジーにおける国際的な取り組みに対する日本の立場との比較や今後の病理学の方向性など、幅広い視点から議論が交わされました。その中で、「AIは病理学者の代替になるか」や「病理学者はAIとどう向き合っていくべきか」という議論が多くの講演の質疑で投げかけられていましたが、「AIは病理学者の直接的な代替とはならないが、普通の病理学者はAIを活用する病理学者にとってかわられる」というコメントがすごく印象に残っており、このコメントは病理学者に限らず当てはまると感じます。十分な知識やリテラシーを持ってAIをうまく使いこなせば、AIの結果に振り回されることなくこれまで以上に多くの仕事や新たなアイデアを生み出せるようになるという意味で、AIを活用しないと生き残っていけない時代になっていると強く感じました。また、議論の本質とは関係ありませんが、会場ではリアルタイムの同時通訳が提供されており、日本語や英語がわからない場合でも、ほぼタイムラグなくスムーズな質疑応答が実現していた点には驚きました。言語能力やAIを使う技術が依然として重要なことに変わりはありませんが、それだけに留まらず、ドメイン知識や議論の内容もこれまで以上に重要になっていると強く感じることができました。
1日目で印象に残っている講演は、ESDIP(ヨーロッパ・デジタルパソロジー学会)とのセッションの中の「Multimodal AI for Precision Oncology: Insights from CHIMERA benchmark 23JSDP」と題した講演です。この講演では、現在の計算病理学におけるAIの限界と、それを克服するためのマルチモーダルAI(CHIMERA)の重要性が明確に示されており、非常に興味深かったです。MRIと病理スライド、RNA-seqとスライド画像など、マルチモーダルデータによる具体的ながんの再発予測事例が示されていましたが、「臨床データのみのデータが最もc-indexが良かった」点が印象に残っています。講演の中では、臨床データのクリーニングがこの結果に寄与しているという考察がされていましたが、マルチモーダルAIの真の価値を引き出すためには、単なるデータ統合量だけでなく、質の高いデータの前処理と洗練された融合アルゴリズムが極めて重要であることに改めて気付かされました。また、病理学の分野でも100万枚の画像を学習した基盤モデルが登場するなど技術の進歩が目覚ましい現在ですが、欠損データに対しての補完能力はまだ低いということで、欠損データをどう融合するかは今後の研究の方向性を考える上で不可欠な視点になると改めて痛感しました。自身の研究においても、マルチモダリティにわたるデータを統合する試みを行っていますが、この講演でデータ品質、欠損データの処理、最適な融合方法といった現実的な課題を冷静に分析していた点は勉強になりました。講演の中で紹介されたCHIMERAもまだこの辺りの課題に全て対応することはできておらず、だからこそマルチモーダルAIは難しいと述べられていましたが、本講演は自分の研究に対するモチベーションを高めるきっかけとなりました。
また、清水研もお世話になっている中谷生体空間オミクス医療解析拠点が協賛の基調講演「Non-destructive 3D pathology and analysis for optimizing treatments」では、非破壊的かつスライド不要な3D病理学という最先端の技術に触れることができ、大変感銘を受けました。従来の2Dスライド病理学に比べてより広範囲にサンプリングでき、予後や予測に役立つ細胞の分布や組織構造を立体的に画像化でき、分子アッセイに必要な検体を非破壊的に保存できるという3D病理学の利点がエレガントに示されて圧倒されました。特に興味深かったのはこの新しい技術をどのようにして臨床に落とし込むかという具体的な議論で、データの立体化と組織の透明化やセグメンテーション、組織を傷つけずに高速で観察できるライトシート顕微鏡の開発によって、非常にイレギュラーな組織表面の情報を正確に抽出することができ、よりよい患者層別化に繋がっていることを学ぶことができました。さらに、ラジオミクスやゲノミクスといった他の分野との相乗効果で多様な患者集団の治療方針決定を改善するというビジョンはコンバージェンスサイエンスを体現しており、今後に大きな期待が持てると感じました。また、質疑応答の中でされていた「3D病理学が将来的には2D病理学を書き換えていくが、2D病理学自身もさらに良くすることにもつながる」や「膨大な3Dデータセットに対してAIがトリアージを行い、2Dの知見も持った病理学者が最終判断を下すという役割分担が最も良い」といったコメントは、AIが病理学者を代替するのではなく、その能力を拡張するという理想的な関係を示していると感じました。
2日目及び3日目のセッションでは口頭発表や企業と共催のワークショップ、臨床現場の視点の共有など、1日目に比べるとミクロな視点での講演や議論が多かったように感じました。その中で特に面白いと感じたのは口頭発表の「Whole-Brain Single-Neuron Atlas-driven 3D Pathology Reveals Microglial Security Hole Accelerating Neuronal Vulnerability」という講演でした。この講演は、神経変性疾患の早期診断と介入を目指した新しい3D全脳アトラスを開発し、神経細胞のシングルセルレベルでの解析で不均一な神経変性病変を精密に検出できたという内容で、短い時間での口頭発表の中でアルツハイマー病モデルマウスAppNL-G-Fを用いた解析について大量のデータが示されました。自分は口頭発表だけでは理解しきれなかったので、口頭発表後に鈴岡さんとポスターを見に行ったところ、ポスターセッションの時間ではありませんでしたが、偶然演者の三谷先生に声をかけていただきデータについて詳しく説明いただけました。特に神経細胞周辺のミクログリア分布が乱れて「ミクログリアのセキュリティホール」ができることにより、神経細胞が失われてしまうという一連の流れ(神経変性病変のリスク因子にミクログリア減少が関わっていること)を示したデータが印象的でした。単純にミクログリアの増減を見るだけでなく、ミクログリアが「どこにどのような状態で」存在しているかという「空間的な」組織化が神経細胞生存に非常に重要であることを示されていた点で、今回の3D解析技術の意義が強く伝わるような設計となっていて非常に参考になりました。また、ポスターについて説明されている中で三谷先生が「臓器レベルでの空間的マルチオミクス統合を実現して、セルオミクスやセローム解析への道を開いていきたい」というビジョンも語られていて、総じて非常に面白い研究であったと感じました。
また、AIセッションの「医療AI/創薬AI研究開発に向けた日本発WSIデータベース」という講演も印象的でした。この講演では、医療および創薬分野におけるAIが臨床情報や分子情報と連動した放射線画像・病理画像データセットを基盤に世界的に急速に進展している一方で、全スライド画像(WSI)に関してこうしたリソースを構築する際には、データの効率的な取得と標準化、厳格な匿名化処理、一貫したキュレーション、高品質なアノテーションが課題となっているといったことを挙げられていました。本講演では、日本が国際的に遅れをとっている分野として、データに対する信頼・AIや医療のドメイン知識・コストの3点を挙げており、その解決に焦点を当てた日本発のWSIデータベース構築が提案されていました。大規模でキュレーションの少ないデータセットは、基礎研究目的のAIモデルを妥当な精度で訓練可能であることから国家的データベースに最適な一方で、高精度で堅牢なAIモデルには高品質で特異的なデータセットが必要であり、民間データプラットフォームを通じて最も効果的に推進されるなど、国家的データベースと民間データプラットフォームは相互補完的であり、欧州や米国では共に活発に運用されているとのことでした。自由にアクセス可能な主要疾患向け多機関連携WSIデータベースを日本で独自に構築することにより、プライバシーを保護しつつ即時利用可能なデータセットから日本や世界における医療・創薬AIの研究開発が加速でき、日本のデジタルパソロジーを推進することにつながるという提言は、1日目の議論の中であったデータ融合の課題に対する解決策を提示していたようにも感じました。
今回はポスターなどの発表もなく、自己研鑽のために参加させていただきました。会場が清水研から近かったこともあったかとは思いますが、これまでにこういった形でご支援いただくことがなかったため非常にありがたく感じています。病理学の分野としては薬学部時代にしっかり学んだこともなく、実際に学会の発表を聞いていてわからないことも多くあったことは事実ですが、エッセンスコースなどで消化器や循環器をはじめとした染色画像を少し見ていたこともあって、少なくとも学部時代の自分と比較すれば病理学に対するハードルは低かったように思います。現在の菱沼先生のように共同研究でお世話になる可能性もあるので、少なくともAIに関する部分については今後対応していけるように研鑽を積んでいきたいと感じました。
この度は、このような貴重な機会とご支援をいただきまして、改めて感謝申し上げます。
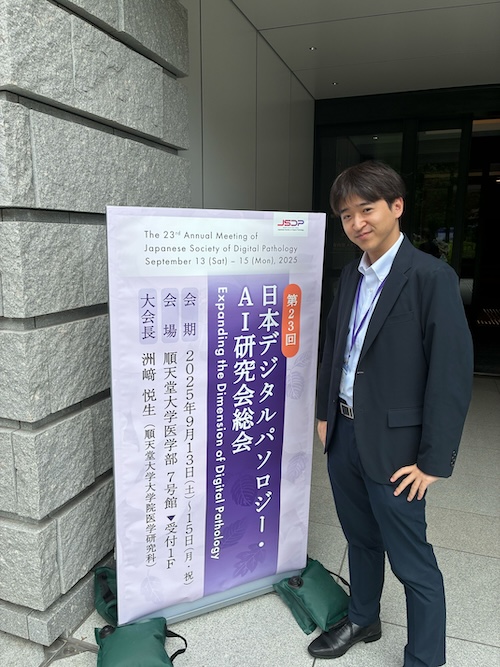
2025年9月13日〜15日に順天堂大学で開催されたデジタルパソロジー学会に参加した。本学会では普段ではなかなか接点のない分野に触れることができ、非常に刺激的だった。以下では本学会を通して特に印象に残った2つの発表の発表について報告する。
一つ目はスタンフォード大学のJonathan T.C. Liu教授による「治療最適化のための非破壊3D病理診断と解析(Non-destructive 3D pathology and analysis for optimizing treatments)」に関する講演を、もう一つは新潟大学の三⾕智樹先生による「全脳ニューロンアトラスによる3D病理解析は神経脱落に先⾏する新規病理”ミクログリアセキュリティホール”を解明する」に関するポスター発表について報告する。
Liu教授は、従来の2Dスライドベースの病理診断が持つサンプリングの限界や破壊的なワークフローといった課題を克服するため、非破壊的な3D病理診断技術の開発に取り組んでいる。本講演では、組織を物理的に切断することなく、生検組織や手術断端全体を3Dで撮像し、AIを用いて解析することで、診断精度を向上させ、さらには手術中の迅速な意思決定を支援する革新的なアプローチが紹介された。特に注目するべきは、サンプル調製から独自開発の顕微鏡、AI解析までを一貫して行う「フルスタック」なアプローチである。まず、組織を透明化し、従来のH&E染色を模倣した蛍光色素で染色する。次に、Liu教授の研究室で開発された「オープントップ光シート顕微鏡(OTLS)」を用いて、組織全体を高速に3D撮像する。このOTLSは、サンプルをガラスプレート上に置くだけで撮像できる「フラットベッドスキャナー」のような簡便さが特徴であり、臨床現場でのハイスループットな運用を可能にする点で非常に画期的であると感じた。生成された膨大な3Dデータは、AIを用いて解析される。Liu教授は2つの解析手法を提示した。一つは、腺管の体積や曲率といった、病理学的に意味のある3D特徴量を抽出し、機械学習で分類する手法である。このアプローチは解釈可能性が高く、前立腺がんの研究では2D解析よりも高い精度で生化学的再発を予測できることが示された。もう一つは、深層学習を用いて、人間には認識できない潜在的な特徴量を学習させる手法である。この手法も、3Dデータを用いることで2Dデータよりも優れた予測性能を発揮することが報告された。
これらの技術の応用として最も衝撃的だったのは、「AIトリアージ」と手術中の迅速断端診断への展開である。AIトリアージは、3Dデータから診断に重要な領域を自動抽出し、病理医に提示することで、診断精度を向上させつつ、病理医の負担を大幅に軽減するものであり、実用化に向けた非常に現実的な戦略であると感じた。さらに、ARPA-Hの大型プロジェクトとして、手術中に摘出された検体の断端を15分以内に評価するシステムの開発が進められている点も紹介された。これは、迅速染色、OTLSによる撮像、AI解析を統合し、手術室で外科医にリアルタイムに近いフィードバックを提供するものである。この技術が実現すれば、がんの取り残しを減らし、再手術率を劇的に低下させることが期待される。本講演を通じて、3D病理診断が単なる研究ツールではなく、臨床診断のワークフローそのものを変革しうる強力な技術であることを改めて認識した。特に、組織を破壊せずに全体像を把握できるという利点は、サンプリングエラーのリスクを低減するだけでなく、撮像後の検体をゲノム解析などの分子アッセイに利用できるという点で、個別化医療の推進に大きく貢献すると感じた。
三谷先生は神経変性疾患、特にアルツハイマー病(AD)の早期診断と治療介入を妨げる「微細な神経細胞脱落」の検出という課題に取り組んでいる。この課題を解決するため、脳全体の構造をシングルニューロンレベルの解像度で3次元的に解析する革新的なプラットフォーム「全脳神経病理アトラス」の開発と、それを用いたAD病態の新たな発見について発表した。特に参考になったのは、アルツハイマー病の主要な仮説である「アミロイドカスケード仮説」(アミロイドβの蓄積が神経細胞死の引き金になる)に対し、新たな視点を提供する発見をデータに基づいて示した点である。先生の研究チームは、ADモデルマウス(AppNL-G-F)の脳を組織透明化し、独自に開発した高速光シート顕微鏡「Movie」で全脳を3D撮像した。これにより得られた1500万個以上の神経細胞の位置情報を、健常マウスから作成した標準脳アトラス「CUBIC-Atlas」と比較することで、神経細胞の密度変化を全脳レベルで精密に定量化した。その結果、従来考えられていたよりも早く、アミロイドβの沈着が始まるのとほぼ同時期に、特定の脳領域で神経細胞の脱落が開始していることを突き止めた。これは、病態のタイムラインがより切迫したものである可能性を示唆する重要な知見である。この発表で特に興味をひいたのは、「CUBIC-Atlas」という全脳神経細胞アトラスを基準(リファレンス)として用いている点にある。ゲノム研究がリファレンスゲノムとの比較によって個々の遺伝子変異を同定するように、病理脳をリファレンスアトラスと比較することで、どの領域で、どの程度の細胞が失われているかを客観的かつ網羅的に評価できる。これは、2Dスライスでの部分的な観察では困難であった、脳全体の不均一な変性部位を正確に検出することを可能にしたというアプローチは素晴らしいと感じた。さらに、本研究の最も衝撃的な発見は「マイクログリアセキュリティホール仮説」の提唱である。脳内の免疫細胞であるマイクログリアは、これまで神経炎症の場では増殖すると考えられてきた。しかし、先生の3Dリスク解析によると、神経細胞脱落の初期リスク指標となるのはマイクログリアの増殖ではなく、むしろ局所的な枯渇であることが示された。加齢に伴いマイクログリアは灰白質から白質へと再分布するが、ADモデルマウスではこのプロセスが加速する。その結果、アミロイド病理によってマイクログリアの分布が乱れ、機能的に疲弊し、神経保護機能が損なわれた「セキュリティの穴」ともいえる空間が脳内に生じる。空間的トランスクリプトーム解析との統合により、恒常性維持に関連する遺伝子発現が低下したマイクログリアの近傍で、神経細胞が特に脆弱になることも明らかにされた。3D全脳解析という強力なツールが、従来の2D病理学では見過ごされてきた新たな病態仮説を導き出すことを示した。シングルセルレベルの空間的なリスク解析というアプローチは、複雑な神経変性疾患のメカニズムを解明するための強力な手法であり、今後の治療戦略開発に大きな影響を与えると感じた。また、このプラットフォームが臓器レベルでの空間マルチオミクス統合解析の基盤となるという展望も示され、病理学研究の未来を予感させる非常に刺激的な発表であった。
本学会は、自身の専門分野から離れた研究テーマが中心であり、また多くの講演が英語であったため、内容の理解に不安があった。しかし、研究室で日頃から行われている分野横断的な勉強会に参加していた経験が活き、講演の要点を把握することができた。入学当初は専門外の勉強会の意義を十分に理解していなかったが、本学会への参加を通じて、幅広い知識を持つことの重要性を実感した。

2025年9月13日から9月15日にかけて第23回日本デジタルパソロジー・AI研究会 定時総会が開催された。ここでは私が聴講した9月15日のプログラムとポスター発表について得た知見と感想を報告する。
本学会では『病理技師によるデジタルパソロジーの実践と実際』と題したセッションを聴講した。このセッションでは全体を通して、Whole Slide Imaging (WSI) を病院へ導入することのメリットと現場での課題および社会普及させる上での現実的な課題の対比がなされた。実際にデジタルパソロジーの運用を行っている病理技師を中心とした四名の登壇者から、徹底した現場視点での現状の報告を聴く機会となった。概してWSI導入のメリットについては各登壇者ともに一貫しており、遠隔診断の促進や他院へのコンサルテーションの円滑化、医学教育への活用、画像解析やAIによる補助支援への接続などが挙げられた。一方で、WSI導入の課題については多岐にわたる指摘がなされた。印象的だったのは長崎大学の病理技師を対象としたアンケートにおいて約7割がデジタルパソロジー導入後に業務負担が増えたと回答している点である。その背景として、組織構築や教育の問題ではなく、そもそもデジタルパソロジーの導入はガラススライドの作成を不要にする訳ではないため工程数が増えていることが指摘された。したがって、短期的には確実に増加する業務負担を上回る導入メリットを生むためには、デジタルパソロジーを活用するための院内および病院間の連携態勢が確立されることが重要となる。これを阻む課題として、保険診療におけるデジタル加算などが乏しいことなども本セッションを通して繰り返し言及された。WSIの導入に限らず、医療AI等の先端技術の恩恵を研究から現場へ繋げるためには様々な障壁が存在するため、その全体像について解像度高く理解しておくことが研究において価値のある問いを立てるためにも必要であると痛感した。
ポスターセッションでは、非破壊三次元病理組織の解析に焦点を当てた発表がいくつか見受けられた。まず、順天堂大学の金光昌史先生らの発表では、腫瘍微小環境 (TME) における抗癌剤の局所分布の不均一性について定量化がなされた。今後の発展として、効果的な薬物送達を実現するための空間トランスクリプトーム解析との統合解析を提案しており大変印象的だった。TMEにおける酸素や栄養供給の不均一性についても考慮することで主要組織の生存戦略を明らかにできる可能性がある。次に、京都大学の山田博之先生らの発表では、腎生検した組織を非破壊三次元で解析した場合の有効性について示された。抗糸球体基底膜抗体型腎炎の腎組織を対象として、三次元データを用いる場合に一般的な二次元の病理スライドを用いる場合よりも半月体の検出率が有意に高いと報告されており、臨床現場においても病理診断の三次元化が効果的である可能性がある。
本学会の最後に特別企画として、病理医に焦点を当てた人気漫画「フラジャイル」の原作者 草水 敏氏の講演が設けられた。質疑応答の中で、総会長の洲崎悦生先生より「知識を多く吸収する時期を経て、注目すべき課題を絞りモノづくりへ繋げる」という漫画原作者の営みと研究活動の類似性の指摘がなされ、その後のパネルディスカッションでも「AIを何のために使うかが重要であり、AIの使用の自己目的化は確実に今後の病理診断の発展を阻む」という点が強調された。講演内容の面白さに加え、AIの医学・生命科学への応用に従事する立場として非常に刺激を受ける機会となった。
本学会の参加を通じて、ハードウェアとしての医工学とソフトウェアとしての情報学がどのように連関することでデジタルパソロジーという病理学の変革を推進してきたかなど、手本となる学際的研究の事例を多く学ぶことができた。近視眼的な研究へ固執せず新しい価値を創造できるよう、この経験を今後の糧として研鑽に励みたい。
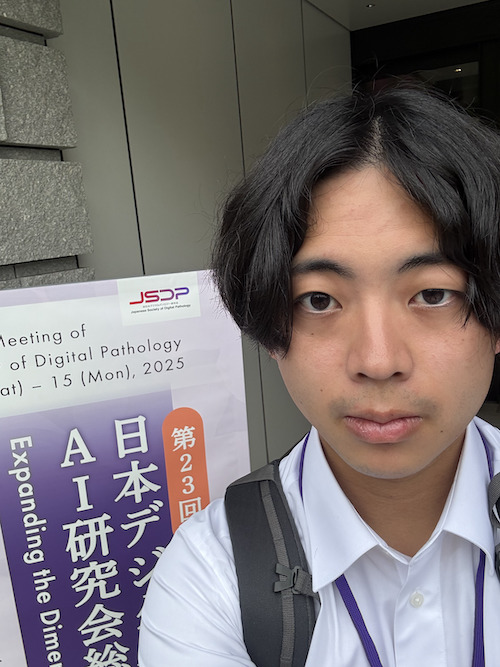
9月13日から15日にかけて順天堂大学にて開催された、第23回日本デジタルパソロジー研究会年次総会に参加した。本年のメインテーマ「Expanding the Dimension of Digital Pathology」が示す通り、本学会はデジタルパソロジーが単なる標本のデジタル化から、AIやマルチモーダルな情報を融合させることで病理診断の質と役割そのものを変革し、精密医療へ貢献する「応用・深化」の時代へと移行したことを実感させる、示唆に富むセッションで満ちていた。
初日に参加した国際セッションでは、デジタルパソロジーが目指す最先端の方向性が二つの大きな潮流として明確に示された。一つはAIによる精密医療の深化、もう一つは患者参加を促す医療の民主化である。
Session 1-1の「Empowering the pixels for better diagnostics and therapeutics: The road to precision pathology」と題された講演では、Whole Slide Image(WSI)の膨大なピクセル情報が、単なる形態診断のデジタル記録に留まらず、治療効果予測や予後予測、さらにはゲノム変異の推定にまで貢献しうる「情報の宝庫」であることが力説され、AIを用いた計算病理学(Computational Pathology)によって、人間の目では捉えきれない微細な形態的特徴を抽出し、客観的・定量的なデータへと変換することで、これまで病理医の経験に依存しがちであった腫瘍の悪性度評価(grading)や予後予測が、より高い精度と再現性をもって行えるようになるという未来が示された。講演後の質疑では、病理医の役割についてのディスカッションがあり、これからの病理医は「形態診断の確定者」から、多様な情報を統合し治療戦略を提案する「臨床コンサルタント」のようなものへと進化していくであろうといったお話があったことが印象的であった。
また、Session 2-2の 「CPath twisting predictive pathology: TROP2 and other stories」は、Computational Pathologyの具体的な応用例を示すものであった。特に、肺がんにおけるTROP2免疫組織化学染色(IHC)の評価を例に挙げた解説は、AIの臨床的価値を明確にした。IHCの陽性度評価は、目視による判断では評価者によるばらつきが生じやすいという課題を長年抱えてきたが、ここにComputational Pathologyを用いることで、陽性細胞の割合や染色強度をピクセル単位で正確に定量化でき、治療薬選択の根拠となるコンパニオン診断の信頼性を飛躍的に向上させることができる。
そして、この潮流の究極的な姿を示したのが、Session 2-3「Multimodal AI for Precision Oncology: Insights from CHIMERA benchmark 23JSDP」の講演であった。現在の病理AIの多くがWSIのみを扱うunimodalであるのに対し、本講演で示されたのは、病理画像に加えて放射線画像やゲノム情報といった全く異なる種類の情報を統合的に解析するmultimodal AIの可能性である。例えば、ある遺伝子変異を持つ腫瘍がWSIやCT画像上でどのような特徴を示すかを学習させることで、画像から遺伝子変異を予測したり、治療への反応性をより正確に層別化したりすることが可能になる。いまだ各モーダルの情報をうまく統合することのできるAIの開発には苦戦している現状とのことであったが、このような統合的アプローチが可能となれば、複雑化するがん医療において真の個別化医療を実現が近づくと感じられた。
一方で、これら技術中心の議論とは一線を画し、デジタルパソロジーが持つもう一つの重要な側面を提示したのが、Session 1-2の「The digital difference: partnering with patients & the public for better pathology」 であった。DPA(Digital Pathology Association)の患者エンゲージメント委員会の視点から語られた本講演は、デジタル化によって、これまで専門家の中に閉じていた「病理情報」が患者自身の手の届くものになることの意義が強調された。患者が自身のWSIや病理レポートに直接アクセスし、病態を視覚的に理解することは、インフォームド・コンセントの質を高め、患者が治療方針の決定に主体的に参加することを促す。これは、医療情報の非対称性を解消し、従来の医師主導の医療から、患者と医療者がパートナーシップを築く協働的な医療へと転換させる「医療の民主化」の大きな一歩である。私自身、過去に東京都医師会の懸賞論文においてブロックチェーンを用いた患者主体の医療情報管理の構想を発表した経験があるが、それと同様の理念、すなわち技術の恩恵をいかに患者へ届け、透明性の高い医療を共に創るかという視点が、デジタルパソロジーの学会で一つの演題として議論されていたことは、非常に感慨深く、また印象的であった。
国内の実装に焦点を当てた三日目のセッション9では、遠隔病理診断の具体的な取り組みが報告された。Session 9-1では順天堂医院の施設間連携による医療の均てん化が、Session 9-2ではベトナムやミャンマーとの国際連携による医療格差是正への貢献が紹介された。こうした施設間、あるいは国家間の連携を円滑に進めるためには、システムやデータの「標準化」が不可欠であり、Session 9-3での「遠隔病理に必要な標準規格とガイドライン」 では、その根幹をなすDICOM規格について紹介された。異なるメーカーのスキャナやビューア間での相互運用性が保証されなければ、遠隔診断の普及は限定的なものになってしまう。現在進行形で規格の整備が進んでいるとのことであり、今後の動向を注視していく必要があると感じた。
Session 10は、AIやシステムの議論を根底で支える「現場の力」に焦点を当てたセッションであり、Session 10-3では、病理検査技師の方から、従来の高品質な標本作製に加え、スキャナ操作や品質管理、データ管理といった新たな領域へと検査技師の役割が拡大・深化している現状が示された。その品質管理をいかに客観的かつ継続的に行うか、という課題に対する一つの答えとして、Session 10-4では、神戸大学における管理図を用いた品質管理手法について紹介された。染色やスキャニングのプロセスを客観的な指標でモニタリングし、安定した品質を維持する取り組みは、施設間のばらつきという病理AIの性能保証において非常に重要な基盤技術である。
本学会を通じて、デジタルパソロジーが、AIによる診断支援という単一の技術革新に留まらず、極めて広範な領域に影響を与えるプラットフォームへと進化していることを確認できた。最先端の国際的な研究開発動向から、日々の臨床現場を支える地道な努力まで、多角的な視点からデジタルパソロジーの現在と未来を学ぶことができ、大変有意義な機会であった。