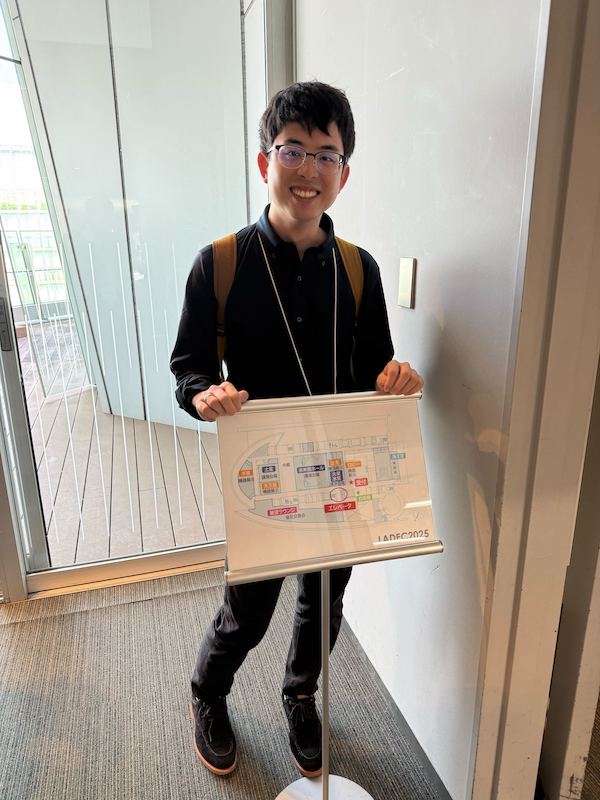LADEC2025参加報告
2025年9月25日、26日に開催されたLaboratory Automation Developers Conference 2025 (LADEC 2025)に参加した。本カンファレンスは、ラボラトリーオートメーション(LA)の最新技術動向、業界の課題、そして未来の展望について、第一線で活躍する研究者や技術者が集い、知識を共有する貴重な機会となった。
「ラボラトリーオートメーションの基礎知識と最新情報」と題された最初のセッションでは、LAの基本的な概念から最新の技術動向、国内外の研究者や企業の取り組みまで、業界の全体像が概説された。特に、AIとの連携によるLAの「自律化」、そして実験計画から実行、学習までを人間の介入なくループさせる「クローズドループ」の概念は、LAにおける重要な概念として紹介され、後のセッションでも度々触れられた。
そのほか講演では、ハードウェア、ソフトウェア、運用管理、応用分野の4つの構成要素が適切に融合することの重要性が説かれ、単純な自動化から、AIエージェントなどを活用した自律的な科学的発見を目指す「Self-Driving Labs」へと潮流がシフトしていることが示された。国内外の主要プレイヤーや国家レベルの具体的なプロジェクトがいくつも紹介され、LAが自分の想像していたよりもずっと遥かに研究開発の成功に不可欠な技術として浸透しつつある現状を学ぶことができた。分野の全体像を掴む上で、非常に有益な導入セッションであった。
セッション2C DBTLサイクルのセッションでは、研究開発を加速する循環型プロセス「DBTLサイクル」の最新実践事例が共有された。DBTLとは、①設計(Design)で仮説を立て、②構築(Build)で試料を作製し、③評価(Test)で性能を測定し、④学習(Learn)で得られたデータを次の設計に活かす、といったサイクルのことであり、いわゆる「PDCA」のLAにおける用語の様なイメージである。
セッション内では生命科学および材料化学の分野における具体的な事例が紹介され、ロボティクス、自動化プラットフォーム、AI解析といった技術が、このサイクルをいかに高速化・高精度化するかが議論された。九州大学の馬場健史教授からは、「次世代バイオものづくりを駆動する高度オミクス計測・解析基盤の開発」について、NIMSの田村亮博士からは材料研究における自律実験オーケストレーションシステム「NIMO」について紹介された。そもそもあまり知識がなかった「ものづくり」について学ぶという点でも新鮮であったが、その中で分野横断的に活用できる手法や共通の課題について理解を深めることができ、DBTLサイクル実装の具体的なイメージを得ることができた。
セッション3C「創薬スクリーニングと自動化 ― 過去・現在・未来」のセッションでは、創薬研究におけるスクリーニング技術と自動化の歴史的変遷から、AIを活用した未来の展望までが網羅的に語られた。個人的にはある程度なじみのある創薬の分野を起点としたセッションであり、最も印象に残るセッションとなった。
実は1980年代に端を発している実験自動化の歴史において、近頃パラダイムはデータの「量から質」へとシフトし、より生体に近い複雑な評価系と、そこから得られる多次元的なデータを解析する「ハイコンテントスクリーニング(HCS)」の重要性が増してきている。さらに、AIの技術を取り込むことで、実験の状況に応じてリアルタイムで最適化を行う「ダイナミックスケジューラー」や「オーケストレーションソフトウェア」の開発が進行し、遂にラボの自律化が可能となる。このような歴史の流れにおけるLAの現在地を知ることができた。講演の後行われたパネルディスカッションでは、技術の発展によって失われる可能性のある「セレンディピティ」をいかに担保するか、研究者の役割はどう変わるかといった、本質的な問いについて議論があり、示唆に富む内容であった。
今回のLADECでは、海外からの招待講演者に加え、国内の大学、研究機関のほか、アステラス製薬などの大手製薬企業から、AWSのようなITプラットフォーマー、Science Aidといったスタートアップまで、多様なプレイヤーが登壇しており、産業界や学術コミュニティ全体でLAを推進しようとする流れが感じられた。
今回聴講したセッションを通して、ラボラトリーオートメーションが単なる効率化ツールではなく、科学的発見そのものを加速・変革する「研究の主体」へと進化していることが明確になった。創薬スクリーニングの歴史が示すように、技術は常に研究ニーズの変化とともに進化する。「量」を追い求めた時代から、より複雑な生命現象を捉える「質」の時代へと移り変わる中で、自動化・自律化技術もより高度で柔軟なものが求められている。
これらのトレンドを踏まえ、我々の研究においても、まずは反復性が高く、精度が求められる作業から段階的に自動化を進めていく必要があると感じた。
本カンファレンスで得られた知見は、そのための具体的なロードマップを描く上で極めて有益であった。本カンファレンスで得られた知見を活かし、また適宜アップデートしながら、自分自身でもLAに向けた取り組みを進めて行きたいと思う。
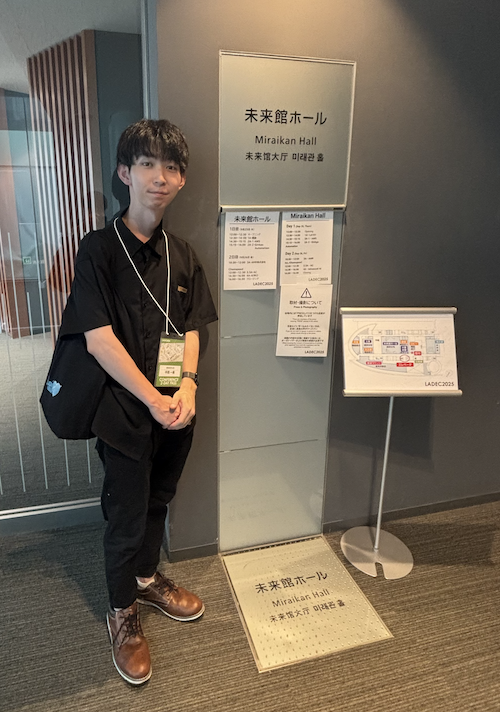
9/25~26に日本科学未来館で開催されたLaboratory Automation Development Conference 2025 (LADEC) にこの度参加し、最新の自動実験装置やロボット・AIなどによる実験の自動化についての知見を勉強させていただいた。私の専門分野外の内容ではあったが、現在の実験自動化のトレンドや課題点、これから実現されていきそうなことについて色々知ることができたため、非常に有意義な経験であった。
以下、自分なりに学んだことを以下に述べる。
はじめにLADECのセッション1A「概論:ラボラトリーオートメーションの基礎知識と最新情報」に参加した。このセッションでは、東京科学大学の神田元紀先生がラボラトリーオートメーション (以下LA) の基礎知識や最新情報を講義してくださった。講義によるとLAの明確な定義は存在しないみたいだが、「機械化」「自動化」「自律化」の三段階で整理される。単に手作業を機械に置き換える「機械化」、複数の作業からなる一連のフローを効率化する「自動化」、そして、AIなどが状況を判断し自律的に作業フローを遂行する「自律化」である。現在、我々が目にしている技術の多くは「自動化」の段階にあるが、その先にある「自律化」が実現される時代がそう遠くないうちに来そうだと感じた。
また色々な報告があるが、そのうちの一つでは、現在のLAの市場規模は2024年に73.3億ドル、2029年には114.1億ドルに成長するといわれており、LA分野は急速な成長期にあると言える。このような潮流はアカデミアのみならず、民間企業にも波及しているらしく、さまざまな大手製薬企業では実験の自動化、AI・ロボットの導入は「当たり前」の時代に突入している。LAは創薬にとって必要不可欠な基盤技術として定着しつつあり、自動化技術に対する深い理解がこれからの時代に不可欠になっていきそうである。神田先生は、「アカデミアでできることはほぼ終わりつつあり、今は企業が主体となってLA技術の研究を進めるフェーズに入った」とおっしゃっており、民間企業が多額の資本を投入してLA技術を発展させている状況となっている。LA技術を実現するためのロボットやクラウド技術などはなかなか参入するのが難しいが、例えばロボットを動的に操作するためのアプリケーション開発などのソフト面で我々が何かできることがあるかもしれないなと感じた。
そして、講義で私が感銘を受けたLAの将来的なビジョンとして、「大規模なロボットセンターを構築し、世界中の実験をクラウドに集約し、誰もが同じ条件で、「匠の技」に依存することなく、実験を実行できる未来」であった。これが実現すると、実験の属人性を排し、プロトコルや結果をデジタルデータとして完全に共有・再現可能にすることが可能になる。生命科学の再現性の問題は劇的に改善され、世界中の研究者が時間や場所に縛られずに巨大な実験プラットフォームへアクセスして実験検証を行うことができるようになるだろう。このビジョンに触れ、私はLAが目指すゴールが、研究の生産性向上だけでなく、科学のあり方そのものをよりオープンで堅牢なものへと変革することにあるのだと学び、深く感銘を受けた。
また、非常に面白かった講義はセッション3Bの「バイオ一点もの」である。ここでは、アカデミアならではの非常に独創的かつ「尖っている」LA研究が4つ紹介されていた。以下に紹介されていた研究について述べる。
最初の発表は、国士舘大学の神野誠先生によるマイクロチューブの蓋を開け閉めする「マイクロチューブ capper/decapper」の開発についてであった。マイクロチューブの蓋の開け閉めの自動化は、一見地味な作業だが、コンタミネーションリスクの低減や実験者の負担軽減の観点からは極めて重要である。神野先生が開発した自動装置と実験者の手作業での蓋の開け閉めの速度比較では引き分けであったが、コンタミネーションにつながるような飛沫飛散についての検証実験では自動装置が圧勝したという結果になっており、これからの更なる装置の改良に非常に期待が持てた。研究者の「あったらいいな」を形にし、社会実装まで見据える神野先生のその姿勢に、技術者としての強い情熱を感じ、自分もこうありたいと思った。
次の発表は、理化学研究所の落合幸治先生による汎用ヒト型ロボット「まほろ」の運用ソフトウェア「maholocon」の開発についてであった。細胞のコンフルエンシーをアプリケーションで予測して、継代タイミングを動的に調整するダイナミックスケジューリングや、消耗品の状態を管理し自律的に維持管理を行う「Self-maintainability (SeM)」という概念は、まさにLAが「自動化」から「自律化」へと進化していく過程そのものであると感じ、とてもワクワクした。
3人目の発表は、同じく理研の藤田美紀先生による植物表現型解析システム「RIPPS/CRIPPS」の発表であった。藤田先生は食料安定供給という社会課題の解決をモチベーションとされており、人間には不可能な、長期間にわたる精密な水・肥料管理と多角的な植物観察を自動化することで、植物の乾燥ストレス応答といった複雑な生命現象の解明に迫っておられた。特に、当初は土詰めに使う予定であったロボット「コボッタ」を、化学物質処理用のロボットへと転用したエピソードは、固定観念にとらわれない発想の転換が新たな価値を生むというイノベーションの本質を示しているなと感じ、大変感銘を受けた。
最後は、筑波大学の史先生による「アリの睡眠研究」であった。史先生の研究では、LAが生命科学の根源的な問いの追求にどう貢献できるかが示されていた。個人的に非常に面白いと思ったのは、「Kroghの法則」に基づき、睡眠研究のモデル生物としてマウスではなくアリを選び、その微小な個体を多数、長期間にわたり行動観察するための専用自動化システムを構築していたことである。このLADECでは色々な発表や実際の展示機器に触れる機会があったが、どれもin vitroの実験の自動化・効率化のものばかりであり、in vivoはまだまだ自動化するのは難しい現状なのかな?と思っていた。しかし、史先生はかなり難しいであろうin vivoの実験自動化を実現しておられ、非常に感動した。さらに現在マウスを使った神経科学研究の自動化技術の開発も進めておられるらしく、in vivo実験の自動化もどんどん進められてきている現状を知ることができた。
今回のLADECへの参加を通して、私のLAに対する認識は一新された。LAは、単に実験を高速化・省力化する技術ではなく、世界中の科学者の実験再現性と信頼性を飛躍的に向上させ、研究者の「パートナー」として、これまで不可能だった規模や精度の実験を可能にすることのできる、次世代の研究だと感じた。正直なところ、この勉強会に参加するまで実験自動化のイメージが全くついていなかったが、LADECを通してLAの現状や展望、有用性について知見を深めることができ、自分にとってとても大きな財産になった。最後になるが、このような貴重な勉強の機会を頂きましたこと、感謝申し上げます。ありがとうございました。
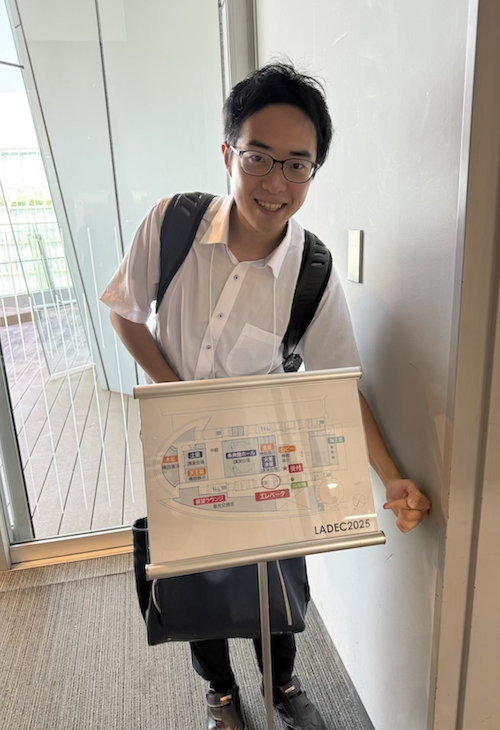
2025年9月25日から26日、日本科学未来館で開催されたラボオートメーションLaboratory Automation Developers Conference 2025に参加した。東京科学大学では近いうちに複数の実験ロボットを導入した大規模施設を計画している。本会議への参加は、その実現に向けた知識習得とアイデア探しのための勉強会であった。私自身、この分野については全くの素人であり、2日間の参加で「何ができて、何ができないのか」という基本的な感覚を掴むことができた。
まず、現状のラボオートメーション自体がまだ発展途上であり、間口が広い領域であると分かった。初日の講演で、東京科学大学難治疾患研究所の神田先生が「ラボオートメーションの基礎知識と最新情報」について語った。国内外の産業界・学術界では、ロボット・AI技術による研究全体 (WetもDryも) の自動化が加速しており、特に製薬会社はラボオートメーションによる自動化方針を打ち出している。しかし、この「ラボオートメーション」という言葉に明確な定義は現状存在していない。神田先生によると、ラボオートメーションを「研究室+ハードウェア+ソフトウェア」という認識で良い、とのことだ。この言葉が示すように、明確な線引きはない。遠隔地のロボットが作業を行う完全自動化された大規模システムも、細胞播種などの特定の作業を代替する単体ロボットも、全てラボオートメーションに含まれる。現状、参入障壁はそれほど高くない、柔軟な領域であるように感じた。
ラボオートメーションから想像されるロボット (ハードウェア) について、展示と講演を通じて得た知見を簡単にまとめる。会場には多様な企業の展示があり、大小様々なロボットが動作していた。見学と講演から、個々のロボットは特定の操作しかできないという事実に気がついた。高度な作業を行うロボットほど、この傾向は顕著である。多くの作業をこなしているように見えるシステムは、特定の機能を持つロボットを「モジュール」として組み合わせることで、一連の実験パイプラインを構築していた。「まずは何でもできる高性能ロボットを導入する」という私の当初の認識は誤りであった。必要な機能を持つ個々のロボットをモジュールとして追加し、システムを徐々にアップグレードしていくという考え方ができる。この点においてもラボオートメーションの参入障壁はそこまで高くないと感じさせられた。
もう一つトピックを報告したいと思う。それはロボットとAIである。これはロボット自体にAIを搭載するというよりも、ロボット技術とAI技術により高速にDBTL (Design-Build-Test-Learn) サイクルを回すことである。人の手では決して対応できない量 (人海戦術であれば対処できるかもしれないが現実的ではないだろう) の実験を均一に繰り返すことができるロボットによって行う。この考え方は生命科学だけではなくて、むしろ材料工学等で進んでいる印象を受けた。これらの講演を聞いて、ロボットを組み込んだ研究では「何をどこまでやるか」を明確にすることが大切だと感じた。というのも、今回の研究ではどこまでやるか、何を達成することを目標にするのかを明確にしないと、終わりがない研究になってしまうだろう。ロボットやAI自体はどこまでも最適解を追求し続けようとするため、そこに待ったをかけられるのは人間である。この人間がぶれてしまうと研究の方向性やそもそも何をやっているのかということが段々わからなくなってしまいそうな印象を受けた。ロボット x AIは私自身非常に興味のあるところなので、この感覚は大事にしたいと思う。今回の勉強会で得た最大の学びと思っている。
最後にラボオートメーションの目指す究極の姿と、それを実現するために超えるべき課題をまとめる。神田先生をはじめ、ラボオートメーションの目指す究極の目標は完全クラウド型の巨大実験ロボット施設の完成とおっしゃっていた。実験プロトコルをプログラミングのように記述し、送信すれば、遠隔のロボットセンターで作業が始まる。このシステム最大の価値は、単なる時間短縮や24時間稼働だけでなく、実験者の技術に依存しない、100%再現可能な実験が実現することだ。プロトコルをGitHubなどで共有すれば、世界中の誰もが同じ条件で再現実験ができる世界をラボオートメーションはもたらす。そのためには、いくつも越えなければならない障壁があるが、個人的に注目していきたい課題をまとめたい。
一つ目は規格化である。例えば、現在多くの企業様が様々な実験用のプレートを販売している。実はどれも同じに見える96 wellプレートでもwellの相対位置や透明度に若干の差が生じている。この僅かな規格のズレはチップの先端を壁面に当てながら液体を入れる。という人が作業する分には全く問題にならないことでも、実験間の差を生んでしまう原因になる。これを解決するには徹底的な規格化が必要である。実験器具のみに限った話ではなく、ロボットおよびソフトウェアについても一定の規格化が必要になってくるだろう。仮にこの課題が解決されたら、非常に効率と再現性の高いシステムが構築できるが、すぐに解決できる問題ではないだろう。
二点目は実験手技である。以前、同じ実験でも作業者が変わると同じ結果にならないという話を聞いた。その時の結論としては、シャーレに液体を入れるときのシャーレの絶妙な角度やシャーレの揺らし方など、プロトコル上の記載には現れない作業者の習慣に原因があるとなった。いくつかの講演ではこの習慣を「匠の技」と呼んでいた。例として挙げられていたのが、細胞を培養するインキュベーターの閉め方である。扉を閉めるにも、ゆっくり優しく閉めることで庫内の環境が一定に保たれ、結果として安定した実験が可能になるという。このような匠の技は文字としてプロトコルに現れにくく、継承や習得には時間がかかる。ロボットによる再現性100%の実験を目指すには、この「匠の技」をいかに数値化し、プログラミング可能な手順として落とし込むかが極めて重要な課題となる。決して刃向かったりしてこないが、探索によるtry and errorを行えない従順なロボット達にこれら匠の技を継承するのは果たしてどれくらい大変なのだろうか。
今回の会議参加により、ラボオートメーションは「何でもできるロボットを一つ導入する」のではなく、「特定の機能を持つモジュールを組み合わせて進化させるシステム」であるという現実的な視点を得た。東京科学大学が開発しているロボットセンターの先にある究極のラボオーメーションの実現には、「規格化」によるハードウェア・ソフトウェアの基盤整備と、「匠の技のデータ化」による再現性の確保という、技術的な壁に加え、文化や習慣の変革が不可欠となる。私自身、東京科学大学にいるということで手を挙げればロボットへのアクセスの可能性があるので、頭の片隅で何かできないか考え続けていきたい。