学生時代にオンラインで研究して論文発表してみませんか?
数理情報科学を生命科学研究に取り込みたい (あるいはその逆) という需要は年々増すばかりであり、その1つの指南書として「Pythonで実践 生命科学データの機械学習」を上梓して基礎的な考え方を余すところなく公開しました。この本に限らず、今の学生さんたちにはさまざまな自習の機会が提供されていますが、「その先」の学びの機会があまりないというのは20年前とほぼ変わっていません。自分でいろいろ学び、さらに高みを目指すハイレベルな学生さんに向けて実践の機会をオンラインで提供するのがオンライン研究制度です。
今から2年後に論文を世界に発表したいという修士課程までの学生さん (+条件を満たす研修医の方) を募集しています (博士課程の方はよりadvancedなダブルメンター制度があります)。オンラインなので、全国どこにお住まいでも問題ありません。
ポータブルスキルが身につく上、業績を出すのは就職にも学振DCにも圧倒的に有利
私が得意とする医学あるいは生命科学と、情報科学 (データサイエンス) の融合領域はまさにオンライン研究にうってつけの分野です。今や新しく取得したデータは必ず公開されており、無料で使える計算リソース・パッケージもかなり登場していますし、情報科学、特に機械学習領域は日夜新しい手法が考案されています。生命科学や医療のデータも爆発的に増えていることを鑑みれば、研究のネタには事欠かない領域と言えます。
そこで、オンラインによる生命科学・医学と情報科学の融合領域、特にドライ解析研究を清水とともにオンラインで取り組みたいという意欲的な学生を全国から募集しています。(オンラインではないですが) 清水自身も学部生のときに論文を筆頭著者として発表しており、博士号を取得後は学部生の研究指導をして筆頭演者として全国学会に発表する機会を用意したり、他大学の学部生をオンラインで指導して学部生が筆頭著者として英語学術論文を発表したこともあります。
研究をして筆頭著者として英語の学術論文にまとめる中で、ライフサイエンスの知識や情報解析技術はもちろん、論理的思考や魅力的なプレゼンテーション、そして英語力といった多岐にわたるポータブルスキルを学生のうちに身につけることができ、それは将来のキャリアパスでも大きく役立つでしょう。また、論文を出版するという経験は「普通の学生生活」ではできませんが、だからこそ大きな差別化になり、例えば就職活動の際には企業の大きな注目を集め、博士課程に進学する際には筆頭論文が1つあるだけで学振DC (選抜された学生に月20万円を数年間支給する制度。返済不要) へ採択される可能性が非常に高まるので経済的に安定した大学院生活をおくることができます。
実験系の生命科学や医療系を目指しているが情報科学を今のうちに習得したい、あるいは逆に現在は情報科学や数理科学を専攻しているがライフサイエンス領域に参入したいという方も大歓迎です。
参考までに、みなさんの先輩方はすでにオンラインで素晴らしい実績を挙げはじめています。例えばオンライン指導はじめてわずか1年で筆頭著者として論文発表 (Hozumi et al., PNAS Nexus 2023) した学部生さんもいますし、学会発表は複数の方が経験しています。論文を発表した学生さんからのメッセージはこちら。
オンライン研究をしている先輩の声
こんにちは、清水研のオンライン研究制度でお世話になっております、川原田明徳です。
まず、私が清水研でオンライン研究を始めたきっかけを少しお話しようと思います。最初のきっかけは、大学3年の頃のコロナ禍でした。コロナ禍により部活動が休止し、空いた時間を利用して自分を成長させたいと思い、データサイエンスを独学で学び始めました。新しく勉強する分野を探している中で、データサイエンティストという職業が注目され始めているというニュースを目にし、なんとなく、これだと思ったのを覚えています。データサイエンスといっても必要な力は幅広く、統計学や機械学習、プログラミングなどを書籍中心で独学しました。データサイエンスのコンペティションに参加したり、統計検定を受験したりする中で、得られた知識や技術を医学や生命科学に生かしたいという思いが強くなりました。そして、そのような研究ができる場を探していたところ、清水研のオンライン研究制度を知り、すぐにメールを送らせていただきました。
次に、この制度において、これまで研究をさせて頂いた感想を話そうと思います。このオンライン研究制度では、マイプロジェクトを持って研究することができます。私の場合、自分のスキルを生かせる研究分野が分からなかったため、清水先生にプロジェクトの方向性を提示していただきました。その後は、zoomでのミーティングで軌道修正していただきながら、進めていくことになります。ミーティングでは、清水先生の知識の幅広さと深さ、最新研究へのアンテナの張り方などに、毎回、感銘を受けさせていただいております。
オンライン研究制度では、このような最高の指導を受けながら、あくまで自分が主体となって研究をできます。学生の主体性を重視しながら、様々な情報や知識、経験を伝えてくださります。これほどまでに、教授が学生のことを考えて、指導をしてくださる研究室があるのかと驚きました。しかも、それが地方に住んでいても可能なのです。このような機会は、かなり貴重だと思います。将来、アカデミアに進む方はもちろん、他のあらゆる進路に進む方にとって、これ以上ない経験を積むことができる制度だと思います。迷っている方がいたら、まずは連絡してみてください!お待ちしております!
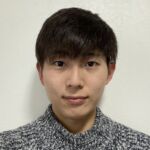
九州大学医学部医学科 卒
オンラインで研究するには? (受け入れ条件)
オンライン研究は定期的にzoom等でdiscussionしながら研究の方向性を修正していきますが、清水の時間も有限ですので次の条件を満たす方を優先させていただきます。
大前提として 「Pythonで実践 生命科学データの機械学習」を自力で読了できるくらいの基礎的な機械学習の知識と経験を持ち、かつ例えば解析のエラーが出た際にも自分であれこれ調べ対応できるくらいにはプログラミング等の素養が不可欠です。
- 「データサイエンスで未来の医療を創る」ことに興味関心があり、また筆頭著者として論文発表をして医療界ないし (生命科学・情報科学などの) 学術界に貢献する不退の覚悟がある方。
- 1に関連しますが、私たちと相談しつつ自分である程度テーマの方向性を設定できる程度には論文理解力と理論的思考力、そして主体性のある方。
- 自ら貪欲に学び続け、また学んだことを仲間同士でシェアしさらに高め合っていけるような向上心と協調性のある方
- 日本国内の大学または大学院修士課程に通う現役の学生の方。博士課程の方はこちらではなくダブルメンター制度をご検討ください。
- 大学院生 (修士課程) の場合には、指導教員の許可がある方 (指導者の中にはドライの考え方を身につけることも大事だとお考えの先生もいらっしゃいますが、逆に新たなテーマを始める時間があるなら今やっている修士のプロジェクトに専念してほしいとお考えの先生も当然いらっしゃるでしょう。修士の学生さんは指導者の先生のご意向が最優先です)。
- 金曜日の夕方 (17:30~19:00頃) に都合がつけられる方。オンライン研究生合同のmeetingやBiomedical Data Science Clubの勉強会が入ります。
- ドライ系の研究を主体的に遂行する上で最低限必要となる、基礎的な数学(目安として数学検定1級以上)、統計学 (目安として統計検定準1級相当以上) またはバイオインフォマティクス (目安としてバイオインフォマティクス認定技術者試験合格以上) のいずれかの理解がある方。検定の例を出していますがその資格を持っていなければいけないという意味ではありません。
- 一定程度の英語読解力がある方 (目安としてTOEIC 600程度以上)
- 研究をして成果として発表するための一定程度のまとまった時間が確保できる方 (目安として1000時間程度以上。これは1日1~2時間換算で2年前後になります。卒業まで2年ない方は、時間の工面をどうするつもりなのか教えてください)
- 当分野のHP上でお名前等を掲載しても問題ない方
希望される方はメールでご連絡ください (h_shimizu.dsc@tmd.ac.jp)。
メールをいただいたら一度Biomedical Data Science Club (BDSC) へゲスト参加者としてご招待します。BDSCでオンライン研究と並行して同世代の学生たちとともに学んでいただくことになりますので、BDSCにゲスト参加して引き続き私たちと一緒に取り組みたいとみなさんが思うのかが第一段階です。もしさらに勉強したいということでしたらBDSCの正規メンバーとして登録します。3回ほど正規メンバーとしてBDSCへご参加していただいたタイミングでこちらからオンライン研究の意思をお伺いします。BDSCもかなりハイレベルですので、BDSCだけでも十分勉強になるかと思います。その上でオンライン研究もしたければ、そこで初めてzoomで1度個別にお話ができればと思います。
我々に提供できること、できないこと
オンライン研究はいろいろな制約もありますから何でもできるというわけではもちろんございません。ゼロから手取り足取り全部教えてほしいという方は物理的にも距離が近いご自身の大学の先生にご相談ください。このオンライン研究は、あくまで他大学の先生との共同研究の機会だとお考えいただくとよいかと思います。あるいは、「ドライ完結のやりたいことがあって基本的には自分で行うが、研究計画を立てたり大規模計算機を契約したり論文を書いたり投稿したり、そういう学生個人では難しいところについてアシストしてほしい」という方のサポートだとお考えいただいてもいいかもしれません。なお、研究にかかる全ての費用 (例としてスパコン使用料、論文掲載費) は当方が工面します。
提供できること
- プロジェクト構想段階における科学的なアドバイス
- スーパーコンピューター使用権の提供
- いくつかの教育リソースの提供
- 研究開始後の進め方に関する助言
- 研究で出たデータに関する建設的なdiscussion
- 論文の方向性の助言、論文校正、論文投稿
- 論文査読者コメント対応のアシスト
提供できないこと
- DNAワーク、細胞培養などドライ解析の検証目的の生命科学実験
- 東京科学大学病院の診療情報のご提供 (セキュリティの都合です)
- 学会発表をご自身が希望した場合の旅費等の支給 (他大学の学部生さん個人には本学の規定上支払いができません)

