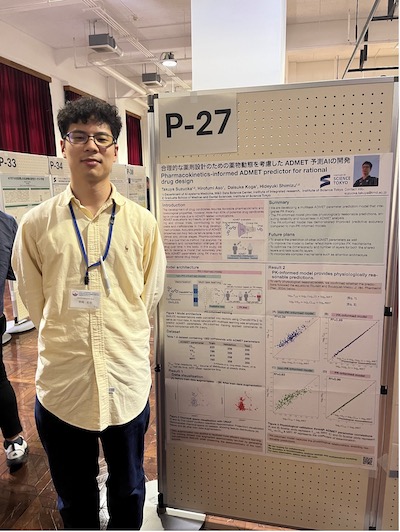学変A・潜在空間分子設計リトリート2024 参加報告
2024年11月17日から19日にかけて開催された学術変革領域研究(A)「天然物が織り成す化合物潜在空間が拓く生物活性分子デザイン」の第一回リトリートに参加させていただきました。
本リトリートでは有機合成化学、生物学、情報科学など様々な分野の研究者が一堂に集まり、分野を超えた活発な議論がされました。各研究者による口頭発表では、天然物の構造多様化やタンパク質-化合物間相互作用の解析、機械学習を用いた化合物設計、画期的な化合物合成の手法など、多岐にわたる研究内容が紹介され、本領域における研究の高度さを実感しました。また、リトリートを介して共同研究のアイデアが続々と出ているのを目にし、異分野の融合研究の実現を実感しました。
私がこのリトリートで特に印象的だったのは、機械学習やシミュレーションなどの計算科学的手法が、もはや特別な技術ではなく研究の基盤となる一般的なツールとして確立されているということでした。例えば、深層生成モデルを用いた化合物生成、タンパク質-リガンドドッキングシミュレーション、分子動力学計算など、これらの技術は多くの研究で当たり前のように活用されていました。重要なのは、これらの技術をただ使用するだけでなく、実験科学との連携によって新たな知見を生み出すことだと感じました。このような状況を踏まえ、今後は実験科学も行いながら、計算科学分野における専門性も高めていくという二つの方向性を意識して研究を進めていきたいと考えています。そのためには、実験科学の理解を深めつつ、計算科学の理論的背景や最新技術の動向にも常にアンテナを張りながら、研究者として成長していく必要があると感じました。
ポスターセッションでは私自身も発表させていただき、同じ分野の先生のみならず、異なる分野の先生方との対話を通じて新たな視点や知見を得ることができました。頂いたご意見などを参考に研究に磨きをかけていきたいと思います。さらに、本リトリートを通じて同年代の研究者の方とも接することができ、私にとって貴重な機会となりました。
最後に、このような充実した会を企画・運営してくださった関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
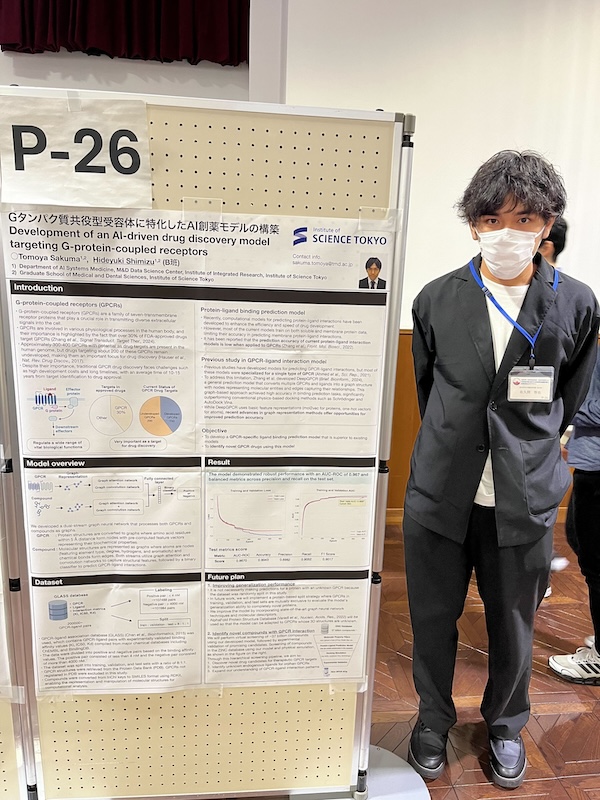
2024年11月16日から19日にかけて、福岡県の九州大学病院キャンパスと北九州市旧大連航路上屋で開催された学術変革領域研究 (A) 潜在空間分子設計第1回リトリート及び若手の会に参加した。本リトリートでは、化合物潜在空間を活用した新たな分子設計の学理構築を目指す3つの研究班(A班:ケミカルバイオロジー、B班:情報科学、C班:有機合成)がそれぞれの最新研究成果を共有し、分野横断的な議論を行った。本報告書ではリトリート全体の概要、オーラル発表およびポスター発表の内容、そして自身のポスター発表について述べる。
16日に開催された若手の会では東京科学大学の林周斗先生の『AIとロボットによるタンパク質設計の効率化』と北里大学の岩月正人先生の『化合物潜在空間の深化に資する微生物由来天然物の拡充』の2題のオーラル発表の後、計24名の学生及び若手の研究者が自己紹介を兼ねたショートプレゼンテーションとポスター発表が行われた。
林先生は高機能なタンパク質を設計する研究に取り組んでいる。高機能なタンパク質を生成AIで設計してアームロボットを用いた機能検証する。機能の検証結果を生成AIにフィードバックするというサイクルを通じて、より高機能なタンパク質を設計できるフィードバックループシステムの構築に取り組みについての報告があった。また、分子動力学シミュレーション (MDS) の簡単な解説の後、MDSの欠点である計算コストが高いという課題に対して、MDSの計算結果を予測するようなモデルの開発にも取り組んでいるということである。10月に参加したCBI学会のセッションでもあったが、ヒトではなくロボットで肺スループットな実験をする流れがきているのだと感じた。
岩月先生の微生物由来の独自の大村天然化合物ライブラリー他、大村智記念研究所の4つのグループ (微生物、化合物探索、有機合成、創薬検証) の取り組みについての紹介もされていた。特に抗マラリア原虫活性スクリーニングを実施し、in vitro 及び in vivoの独自の評価系で放線菌由来の化合物を検出した。また、ひと昔前の熱帯病治療薬は経口投与薬だけだったが、最近は注射剤でもよくなってきているなど、薬剤のモダリティーについても言及があった。
若手の会の翌日の17日から19日にかけて開催されたリトリートでは15題のオーラル発表と47題のポスター発表があった。その中でも特に印象に残ったB班の名古屋大学の海東和麻先生とC班の京都大学の後藤佑樹先生のオーラル発表、B班の東京科学大学の鈴木敬将先生のポスター発表について触れたい。
海東先生による発表では、シトクロムP450 (CYP) による代謝物の予測モデルと、ビルディングブロック型および深層生成モデル型を統合した化合物生成モデルが取り上げられた。CYPは主に薬を含めた異種生体物質を代謝し、無毒性の構造を生成する重要な酵素ファミリーだが、その代謝産物の一部は肝毒性を引き起こす可能性がある。そのため、CYP3A4の代謝物生成を予測することは、非肝毒性薬剤の設計において重要な課題である。本発表ではCYP基質の代謝部位を予測するモデルが紹介された。さらに、CYP生成物の構造を予測するための構造コンバーターも開発され、実験的に観測されたCYP3A4産物の構造式を正確に生成することが確認された。また、ビルディングブロック型と深層生成モデル型を統合した化合物生成モデルであるEMPIREも紹介された。ビルディングブロック型は生成された化合物が科学的に妥当である傾向があり、事前な膨大なデータセットが不要という特徴がある。一方で、深層生成モデル型は未知の化合物が生成可能だが、大規模な学習データが必要という特徴がある。そこで、この両方のアプローチを採用することでそれぞれの利点をいいとこ取りをするようなモデルである化合物生成モデルであるEMPIREを開発した。EMPIREは従来の化合物生成手法と比較して、籠型構造を含む複雑な構造式を重点的に生成することが可能である。
後藤先生は天然物ペプチドを基盤とした新しい化学空間の開拓について発表した。微生物が産生するペプチド性の二次代謝産物(天然物ペプチド)は、膜透過能や血中安定性などの薬剤的性質を持つ特徴的な骨格を有しており、その設計は新たな薬物開発に貢献する可能性がある。特に、チオペプチドの主鎖複素環やシアノバクチン類のプレニル化ピロロインドリン骨格などの特異な構造に着目し、人工的にデザインされたペプチド誘導体を合成する技術が紹介された。これにより、既存の天然物ペプチドではアクセスできなかった化学空間を探索することが可能となった。後藤先生は天然物特有骨格と人工配列を組み合わせた擬天然ペプチドの創成に注力している。具体的には、翻訳合成系、改変遺伝暗号、および翻訳後骨格変換を活用することで、17回の多段階骨格変換をワンポットで実現し、擬天然ペプチドの生産を達成した。このアプローチにより、人工的に設計されたチオペプチド誘導体を自在に合成する技術を確立した。さらに、酵素の人工基質許容能力を予測する学習モデルを構築し、任意の人工基質の酵素修飾結果を高精度で予測することにも成功した。擬天然チオペプチドライブラリーの構築と探索を通じ、既存のペプチドにはない薬効や薬物動態性能を持つ新規ペプチド薬剤の創製を目指している。もしこのライブラリーが利用可能であれば、中分子のデータとして自身の研究に取り入れ、さらに広範囲の化合物を扱えるようにしたい。
鈴木先生のポスター発表では、新規な多目的分子生成モデル『Mothra』を活用したde novo分子生成手法について発表した。このモデルは薬剤候補分子の探索において、複数の評価指標(例えばターゲットタンパク質結合親和性、薬剤らしさ、毒性)を同時に最適化するために設計された。従来の評価指標の線形結合による問題を解決するために、Mothraはパレート最適化を用いて、多目的モンテカルロ木探索とリカレントニューラルネットワークを組み合わせた手法を採用した。Mothraの重要な特徴は生成される分子が単一の目的に最適化されるだけでなく、複数の評価指標間のトレードオフを考慮して設計される点にある。例えば、DDR1キナーゼをターゲットとした分子生成実験では、Dockingスコア、QED(薬剤らしさ評価)、毒性確率の3つを評価指標として使用し、これら全てを満たす分子を効率的に生成した。シミュレーションステップで得られた分子は、タンパク質ポケットに適切に結合し、評価スコアが著しく向上したことが示された。また、生成された分子は既存のデータセットに含まれない新規化学物の生成に成功した。鈴木先生から直接多目的最適化の手法などを直接伺うことができ、生成された分子が複数の目的を同時に満たす仕組みや、パレート最適化の具体的な応用例についての説明が非常に参考になった。
次に私の初めてのポスター発表について報告する。当初は自分の研究に興味がある参加者が少ないのではないかと不安だったが、予想を超える多くの方に興味を持っていただいた。特にB班の先生方からはアルゴリズムの改善に関する具体的なコメントをいただき、大変参考になった。また、A班およびC班の参加者からも生物活性評価や合成技術の観点から貴重なアドバイスを受けることができた。一部、その場で十分に回答できなかった質問については今後の課題として調査を進め、分子生物学会のポスター発表に活かしたいと考えている。
最後に2024年6月に参加した第2回公開シンポジウムとの差異として、各班の先生方が他班とのコラボレーションを積極的に進めていることが挙げられる。また、情報科学の専門ではないA班やC班の先生方も自身の研究に機械学習を取り入れ、MDSなどの技術を活用している例が多く見られた。このような取り組みは、情報科学が特化されていない分野においてもその重要性が認識されていることを示すだけでなく、MDSレベルの技術はB班以外の班でも扱えて当然な技術であると認識した。一方で、大上先生のグループのように情報科学の分野で卓越した研究を行う班や、実験班のようにオリジナルなデータ取得を行う班とは異なる立ち位置にいる自分自身の研究姿勢について深く考える機会にもなった。また、前回の公開シンポジウムで知り合った学生や初めて出会った研究者たちと交流を深めることができた。