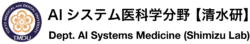このページでは、東京医科歯科大学の大学院入試に見事合格をした先輩方からいただいた清水研を志望している方へ向けた合格体験記をシェアしています。ここに書いてあるのはあくまで公開できる範囲であり、実際には見学にいらっしゃる際にもっといろいろなアドバイス等がもらえます。
博士課程 大学院入試合格 (北海道大学薬学部6年)
私は医療やライフサイエンス領域におけるデータサイエンスに興味を持ち、研究室を探していたところ、清水研のHPに出会いました。豊富な情報量と一からでも勉強ができる教育体制や研究体制が整っていると思い、お世話になりたいと感じました。4月に研究室訪問をさせていただき、出願希望の旨を連絡し、試験を受け、無事合格することができました。
過去の入試データが大学から公表されていますが、結構な数の受験者が落ちているようでしたので、しっかり勉強をする必要があると感じました。小論文とTOEFL-ITPと面接が入試科目ですが、ネットなどの情報からTOEFL-ITPが大事だと思い、重点的に勉強しました。特に博士課程を目指されている方は今行っている研究が業績となって後の色々な申請に有利に働くと思いますので本業をおろそかにすることなく、すきま時間などを有効活用して勉強する必要があると思います。
TOEFL-ITPはListening ComprehensionとStructure and Written ExpressionとReading Comprehensionの3つのセクションがあります。このうち、Structure and Written Expressionは大学入試の際、NEXT STAGEやスクランブル英文法などの文法問題集を頑張った方にはご褒美セッションであり、高得点が望めるため、ここでしっかりとスコアを取っておく必要があると思います。私は、全問正解するTOEFL ITP TEST文法問題580問(語研)で学習した結果、落として2, 3問のレベルまで到達することができました。Listening ComprehensionとReading Comprehensionについては、TOEFL特有の会話表現や学術単語などが文中に含まれますので単語帳などを使ってしっかりと覚える必要があると思います。また、受験1ヶ月前ほどからは公式問題集を何回も解くことで試験全体になれることも必要だと思います。また、私は6月に現在所属する大学でTOEFL-ITPを受験しました。受験の機会がTOEICと比べて少ないかもしれませんが、チャンスがあれば受けてみるといいかもしれません。院試本番では6月に受けたときよりスコアを50点ほどあげることができました。
小論文に関しては、大学に対してメールを送ることで過去3年分の入試問題を請求することができます。それを確認したところ、毎年時事に関することが出題されている傾向がありましたので予想される内容に関しては事前に内容を考えていました。その結果、本番では見事的中しました。そういった対策は有用かもしれません。
面接に関しては聞かれそうなこと(志望動機など)を考えておき、あとは今の自分を面接官に伝えることができれば、問題はないのではないかと思います。
清水研への研究室見学の際には研究室のメンバーの方と話をする機会があり、不安なことやさらに詳しいことを聞くことができると思います。不安に感じることがあれば是非相談してみてください。是非、頑張ってください!
修士課程 大学院入試合格 (早稲田大学理工学部4年)
そのような中,
私が合格できたのは,
院試の勉強においては,
個人的には,院試の勉強と学部の生活(研究や勉強)
清水研は配布して下さる事前勉強用の教材が非常に充実しているの
修士課程 大学院入試合格 (東京理科大学薬学部4年)
なぜ清水研究室に見学へ行ったか、そしてなぜ出願を決めたのか
現代ではAIやChat GPTなどが注目を集めており、私は情報学をベースに人の生命に関連する研究を行いたいと考えていました。そういった思いから、バイオインフォマティクスという学問に出会い、その研究を行っている研究室を探していました。その過程で、清水研究室に出会い、学部3年の9月ごろに見学に伺いました。清水先生からは研究設備や研究内容、そして教育方針について熱心に説明いただき、その情熱に触れたことで、自身の成長にとって清水研究室が最適であると感じ、出願を決意しました。
大学院入試への勉強法
大学院入試への具体的な勉強方法は、英語の勉強方法と専門科目の勉強方法に分けて書きたいと思います。
まず英語(TOEFL ITP)の具体的な勉強方法です。私は、単語学習・リーディング学習、リスニング学習・文法学習に分けて勉強しました。
- 単語学習
旺文社の「TOEFLテスト英単語3800 4訂版」を用いて、CDを使って発音を聞きながら、単語だけでなく例文でも覚えるように学習しました。またRANK2までは完璧にマスターし、時間のある限りRANK3まで学習しました。また、この本の付録についている分野別英単語リストは、長文に出ると思われるテーマごとで英単語リストが分けられており、背景知識をあまりもっていなくて苦手であると思うテーマを重点的に読みました。
- リーディング学習
旺文社の「TOEFL ITPテストリーディング問題攻略」という教材を使いました。この教材のCHAPTER1では設問の出題パターンごとの解き方とポイントが書かれているため、このCHAPTERを通じて出題パターンに慣れることを意識して学習しました。また各例題を解いた後、長文の構文分析をし、構文を把握してから複数回音読を行いました。さらにCHAPTER2では3回分の模試が収録されているため、実際に時間を計って緊張感をもって解く練習をしました。
- リスニング学習
語研の「TOEFL ITP TESTリスニング完全攻略」という教材を使いました。この教材は練習問題が310問と豊富に収録されており、これらの問題を解き、解説を読んで音読やシャドーイングをし、この教材を2周程度すると十分リスニングの力をつけることができると思います。また、TOEFL ITPのリスニングは特にPART Cが難しいため、入試まで時間があまりない人は比較的簡単なPART Aの問題をたくさん解いて徹対策し、残りの時間をPART Bの対策に充てると効率的に点数アップを望めると思います。
- 文法学習
語研の「全問正解するTOEFL ITP TEST文法問題580問」という教材を使いました。TOEFL ITPの文法問題はStructureと呼ばれる4択から選ぶ通常の文法問題とWritten Expressionと呼ばれる誤文訂正問題から構成されています。通常の文法問題は標準的な難易度ですが誤文訂正問題は難しいため、誤文訂正の問題の対策に多くの時間を使った方がよいと思います。また、通常の文法問題をいかに早く解き、全問正解し、誤文訂正問題に時間を回せるかが文法の高得点を取るための鍵だと思うので、普段の練習から時間を計ってタイムマネジメントを意識したほうが良いと思います。
最後に、リスニング・リーディング・文法の中で最も効率的に得点アップしやすいのは文法であると思うので、英語の勉強はまずは文法から始めることをおすすめします。
次に、専門科目の具体的な勉強方法です。私は生物を選択したため、生物の勉強方法を書きたいと思います。
私はまず南江堂の「Essential細胞生物学」という教科書を用いて勉強を行いました。1週目は生物学の大枠をつかむためにざっと読みこみました。2周目では重要なポイントをノートにまとめることや、図をよく見て内容を理解することを意識して学習を行いました。3週目は過去問や問題集を解きながら読み、知識の穴を埋めることを意識し学習を行いました。
また、私はニュートンプレスの「Molecular Biology of THE CELL 細胞の分子生物学」も用いて学習を行いました。この教科書はEssential細胞生物学と姉妹本であり、Essential細胞生物学に漠然と書かれていた内容を掘り下げ、もっと詳しく知りたい内容に限定し学習を行いました(この本は非常に分厚く内容も濃いため時間のない方は読破することはおすすめしません)。
専門科目はインプットに時間をかけることも大事ですが、知識がついてきたらアウトプットに時間を割くことも大事です。私は医科歯科の過去問や他大学の大学院試の過去問を用いてアウトプットを行いました。アウトプットを行うことで分野ごとの知識を有機的につなげることができ、体系的な理解につながると思います。
専門科目は過去問を見ることである程度の出題傾向が分かると思いますが、あまりあてにせず特定の単元に固執せず、どの単元が出てもいいように幅広く学習を進めることをおすすめします。
後輩へのメッセージ
大学院入試は大学受験と異なり受験に関する情報が少なく、また模試がないため受験生内での自分の立ち位置や合格確率がわからないため自分が合格できるのかどうか不安でいっぱいだと思います。でもあきらめずに自分を信じて頑張り続けることが大事だと思います。特に出題傾向がつかめない医科歯科の試験ではどんな問題が出ても大丈夫なぐらいの対応力が身につく位に勉強をして、試験に臨んでほしいと思います。頑張ってください。応援しています。
修士課程 大学院入試合格 (茨城大学農学部4年)
私がAIシステム医科学分野へ見学に訪れた理由は、バイオインフォマティクスを用いた研究に興味があったのですが、在籍している大学にバイオインフォマティクスを扱った研究室がなかったためです。研究室を探している際に清水先生のwebサイトを見つけ、ドライとウェットの両方の側面から研究ができると知り、ぜひ見学してみたいと思いました。そして、大学3年の終了間近頃に面談の機会を設けていただきました。
出願を決めたのは5月初旬でした。大学院進学を検討している方を対象にしたミニセミナーに参加させていただいたことで、研究室に在籍する先輩方やスタッフの先生方のお話を聞き、研究室の雰囲気を感じることができました。その結果、自分のやりたい研究を実現するには清水先生のもとでなら可能であると確信しました。また、かねてから興味を抱いていた創薬研究ができることが、出願を決断する大きな要因となりました。
次に、入試に向けた対策です。筆記試験は、『英語1、英語2、生物、化学、工学、臨床検査学』の中から1科目選択する形式だったので、本番では『英語1、英語2、生物』の中から選択しようと考えました。まずは、過去問を中心に学習を進めました。英語では興味のある分野(特に、現在の所属研究室関連や生命科学分野)に関する論文を読み、生物では大学の講義で使用した教科書をもとに学習しました。
個人的に英語に不安を感じていたため、TOEFL ITP対策に力を入れました。過去に一度TOEFL ITPを受験したことがあり、その時の経験からリスニングと文法と単語に焦点を当てた学習を行いました。文法問題は得点源になりやすい傾向があるので要点を押さえた参考書を用いて対策を行いました。また、入試の約3週間前から本番さながらの模試形式の問題集を使用し、時間を意識して取り組みました。具体的には、以下の4冊を中心に学習を進めていました。
- 『全問正解するTOEFL ITP TEST文法問題対策(語研)』
- 『TOEFL ITP TESTリスニング完全対策(語研)』
- 『TOEFLテスト英単語3800(旺文社)』
- 『完全攻略!TOEFL ITPテスト模試4回分(アルク)』
大学院進学に向けて心配事や不安があるかと思います。私は、研究室訪問の際に先生に相談させていただくことで、前向きに頑張ることができました。皆さんも、不安なことなどは相談してみてください。先輩方や先生方は親身にお話を聞いてくださると思います。自分の興味を大切に目標に向かって頑張ってください。応援しています!