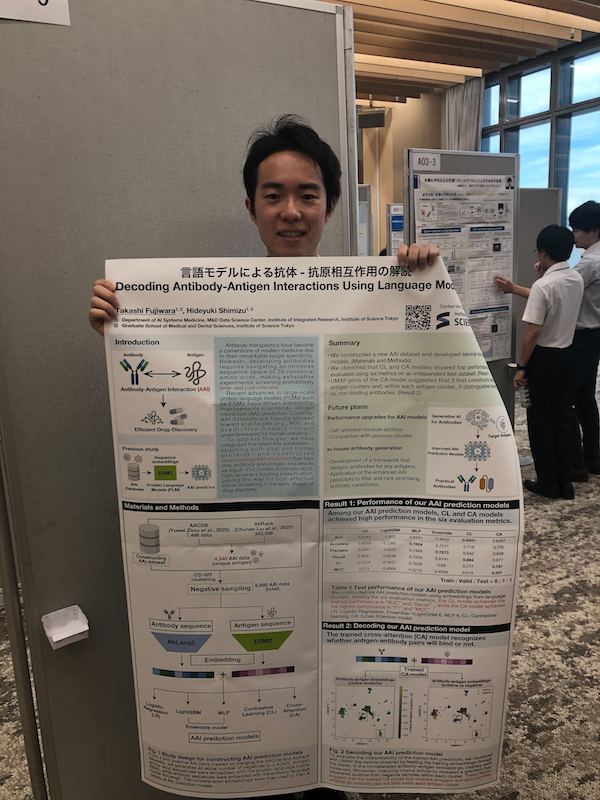予知生合成科学 第6回公開シンポジウム 参加報告
7月18日に福井県で開催された、学術変革領域研究 (A) 「予知生合成科学」第6回公開シンポジウムの初日に参加したので、その内容について報告する。
冒頭の領域説明では、「予知生合成科学」が目指す全体像が改めて示された。本領域は「集積・予知・拡張」の3分野を柱とし、多分野の研究者が有機的に連携することで、合成生物学や有機合成化学といった実験科学と、情報科学や計算科学との融合による発展を目指すものであることが強調された。実際に、医学、理学、化学、薬学、農学、工学、情報科学など、実に多様な専門性を持つ先生方が一堂に会しており、共通の目標達成に向けた分野横断的な協力の重要性を再認識することができた。
その後のセッションは、ショートトークとポスター発表で構成されていた。ショートトークでは、ポリケタイド合成酵素(PKS)やリボソーム翻訳後修飾ペプチド(RiPPs)をはじめ、多様な天然物の生合成に関する研究が紹介された。様々な発表を聴講し、天然物などの有用物質を生み出す「生合成遺伝子クラスター(BGC)」を対象に、①ゲノム情報から機能を「予知」し、②酵素改変や経路設計により新たな化合物を「創出」する、③そのためにウェットな実験知見を「集積」し、AI等でモデルを高度化する、という一連の流れのイメージを身につけることができた。
ポスターセッションでは、私自身も研究成果を発表する機会をいただいた。私にとっては、本学入学後初めての研究発表の場となった。私の研究は、自己免疫疾患の創薬を目指し、AIモデルを用いて免疫機構の解明に迫るものであるが、今回の発表では、その第一歩として入学からこれまでに間で開発したAIモデルの詳細について報告した。聴講してくださった方とはモデルの新規性やタンパク質言語モデルの導入についてといった技術的な議論ができたほか、予測モデルを創薬へ応用する上での注意点について貴重なご助言をいただくことができた。
今回のシンポジウムへの参加は、最先端の「予知生合成科学」に触れるまたとない機会となった。多くの発表でAIや計算科学が活用されており、当研究室が掲げる「Convergence Science」の重要性を改めて認識する機会ともなった。私が取り組む免疫学研究もこの大きな潮流の中にあり、異分野の知見を継続的に取り入れ、他分野の先端技術を自身の研究に応用していく必要性を痛感した。
今後は、本シンポジウムで得た知見を参考に、自己免疫疾患の病態解明と創薬への応用をさらに進めていきたいと考える。
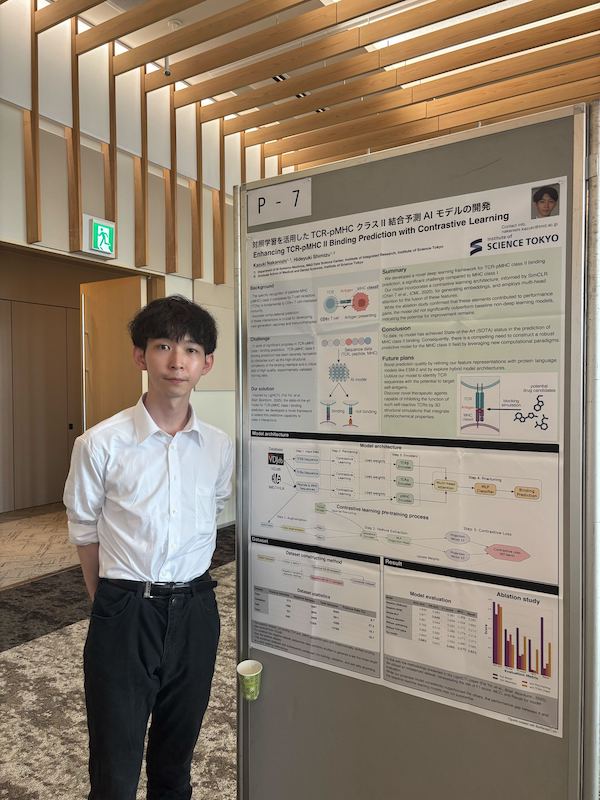
2025年7月18日、19日の両日にわたり、福井県繊協ビルにて開催された学術変革領域研究(A)「予知生合成科学」第6回公開シンポジウムに参加した。本領域は、これまで実験科学が中心であった天然物研究に計算科学を組み込み、「生体機能分子群の生合成システムを明らかにし、自在に作り出す」ことを目指すものである。領域代表の葛山智久教授(東京大学)による領域説明では、これまで中心であった天然物研究の「探す」フェーズから、生合成遺伝子クラスター (biosynthesis genome cluster: BGC) や計算科学に基づく「造り出す」フェーズへと転換させるという本領域の目標が語られた。NCBIに登録されている膨大な数の機能未知タンパク質(全体の99%以上)を前に、これまでのように実験のみで機能annotationを解明することは現実的ではない。そこで計算科学による「予知」の重要性が強調された。本レポートでは、特に印象に残った発表を中心に、シンポジウムで得られた知見をまとめる。
本領域は、新規生合成経路や酵素機能の「A01: 集積」、計算科学による機能や構造の「A02: 予知」、そして新たな化合物をデザインし、作り出す「A03: 創出」の三つの柱で構成されている。
「A01: 集積」班では、多様な生物種から未知の生合成経路や新規酵素反応を発見し、その知見を集積することを目的としている。
特に興味深かったのは、西村陽介先生(海洋研究開発機構)による「メタゲノムビッグデータで環境微生物が生み出した生合成ポテンシャルを理解する」という発表である。原核生物はその環境において必要な遺伝子は保存 (場合によっては外界から取り込む) などによって保持するが、不要な遺伝子はどんどん手放していく。このようにメタゲノムはその環境の影響を大きく受ける。海洋というひとくくりにされがちな環境にも、深海や熱水孔、沿岸など多様なニッチが存在し、それぞれの環境に適応した微生物が独自の生合成遺伝子を持っている。先生の研究室では、世界最大規模のメタゲノム情報基盤を構築し、これまで見過ごされてきた環境由来のBGCを網羅的に探索している。私自身が取り組んでいる研究にも是非取り入れたいと感じた。
これらの研究は、我々の知らない生合成の世界の広大さを示すと同時に、「予知」や「創出」の基盤となる膨大かつ詳細な質の高いデータが次々に生み出されているのを目の当たりにした。
A02班は、本領域の核となる計算科学・AI技術を駆使して、酵素機能や化合物の構造を予測する研究を推進している。我々清水グループが所属するのがこのA02班である。
藤田卓先生(東京大学)の「機械学習を用いた酵素ペアの機能同一性予測」の発表は、本領域の進展を象徴するものであった。アミノ酸配列情報に加え、AlphaFoldによる予測立体構造情報を特徴量として取り入れた機械学習モデル「FUJISAN」は、従来の配列相同性検索(BLAST)や他の深層学習モデル(ESM-2, DeepFRI)を上回る高い精度で酵素機能の同一性を予測できることが示された。さらに、最新の言語モデルESM-Cを用いた新手法「UNKAI」では、AUROC値0.9887という予測性能を達成しており、機能未知タンパク質の網羅的な機能アノテーションが可能である。このようなタンパク質の機能アノテーションの手法開発は、冒頭で報告した課題を克服するものであり、この後益々重要になってくるテーマだと感じた。
また、レオ チーシャン先生(山梨大学)は、計算コストが膨大なDFT計算を深層学習で代替し、テルペン化合物の複雑な環化反応経路を高速・高精度に予測するモデルの開発に取り組まれていた。従来の計算精度を保ちつつ100倍の計算速度の向上を達成したとのことだ。創薬に量子的な情報を取り入れた研究を展開したいと考えていたところなので今後とも勉強させていただきたい。また、レオ先生は私のポスター発表に熱心に聞いてくれた先生の1人でもあった。貴重なフィードバックをいただいたので、今後の研究に組み入れていきたい。
集積・予知された知見を基に、新たな機能を持つ酵素や化合物を実際に創り出すのがA03班である。
南篤志先生(東京科学大学)は、分子進化の概念を取り入れ、複数の酵素のドメインを戦略的に入れ替える「ドメインスワップ」により、デザイナー酵素を創出する研究を発表した。南先生とは懇親会でお話しする機会をいただき、タンパク質工学の現場の生の声を伺うことができた。後藤佑樹先生(京都大学)は、翻訳後修飾ペプチド(RiPPs)において、6兆種を超える人工基質ライブラリーを一つのチューブの中に構築・評価し、有能な配列をスクリーニングする系を確立しているとのお話を伺った。兆のオーダーを生命科学ではあまり聞いたことがない。このような技術を持った先生方がたくさんいらっしゃるので、ぜひこの2年間の間にたくさんの繋がりを作りたい。
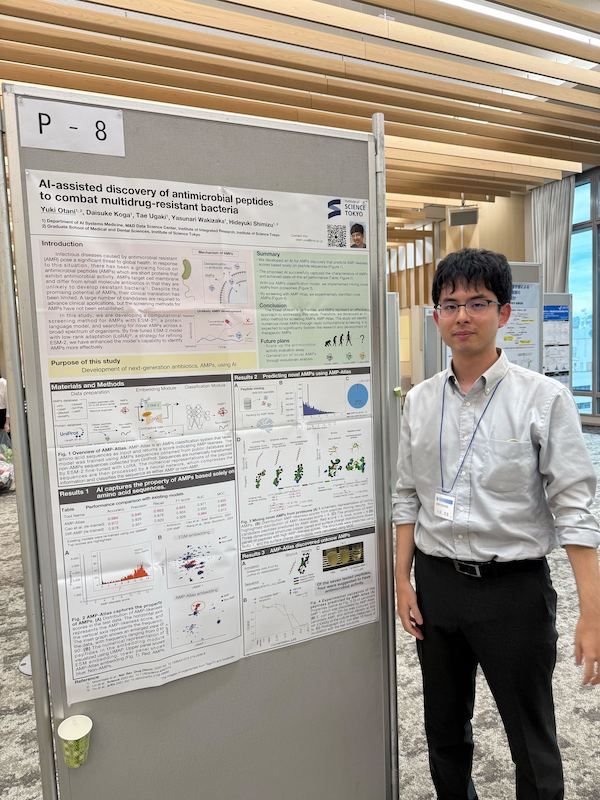
この度、2025年7月18〜19日に開催された「予知生合成科学」第6回公開シンポジウムに参加する機会を頂いたため、福井県にて、公募班のショートトークを聞き、ポスター発表もさせて頂いた。本シンポジウムは、生体反応の集積・予知・創出を基盤としたシステム生物合成科学という学術変革領域研究の一環として開催され、その名の通り、生命が持つ複雑な生合成経路を理解し、予知し、さらには人工的に創出するといったビジョンを掲げている。
以下、私が聴講した発表で興味深かったものとポスター発表の感想を述べる。
まず、公募班のショートトークにて、神戸大学 農学研究科の水谷正治先生のゼニゴケの独自代謝酵素遺伝子の活用についての発表が個人的に印象に残っている。ゼニゴケは積極的に研究されてはいないため、情報が少なく、その代謝酵素遺伝子についてもほとんど解析されていない。しかし、苔類は多様かつ固有の二次代謝産物を産生しているため、その生合成において今まで知られていないような新規の酵素遺伝子がゲノム解析によって見つけられる可能性は多分にある。水谷先生は、コケ植物において独特な大環状ビスベンジル類の生合成に関与する酵素遺伝子を網羅的に解析し、ゼニゴケのユニークな生合成関連代謝遺伝子を見つけ出し、活用していこうという取り組みを行なっており、緻密に設計された研究やその成果に門外漢ながら非常に勉強になり、とてもワクワクしたショートトークだった。また、水谷先生はゼニゴケの食用化にも取り組んでおられるらしく、日本料理「雲鶴」でコケを使ったとても美味しそうな懐石料理もショートトークで紹介しており、コケの食用化への可能性だけでなく、水谷先生のコケへの熱意もひしひしと感じた、面白い発表だった。
ポスター発表について、私は「言語モデルによる抗体-抗原相互作用の解読」というテーマで発表を行った。発表する前は、清水研に入ってまだ3ヶ月程度であり、私の研究ポスターを聞きにきてくれる人なんているのかなと少し不安だった。しかし、発表本番では、実質40分程度の時間の間に3人もの人が私のポスターを聞きにきてくれ、鋭い質問や、貴重なディスカッションの機会を頂けた。また、ディスカッションの際はこれまで清水研で培った生物学や数学の基礎知識だけでなく、5~6月に勉強会で扱った大量の最新バイオインフォマティクス論文で得た知識を使って活発な議論を行うことができた。これは半年前の私からは考えられない成長であり、それを今回のシンポジウムで実感することができ、僅かではあるが、自信に繋がった。
今回のシンポジウムへの参加を通じて、単に既存の知識を集約するだけでなく、AI、計算科学、合成科学といった最先端技術を駆使して、生命の根源的な反応を「予知」し「創出」するという、挑戦的かつ魅力的な研究領域の可能性を多分に感じることができ、最前線で活躍されている日本の科学者の熱意やレベルの高さをまじまじと感じられる、とても貴重な体験ができた。また、今回の予知生合成会議は、異分野の研究者同士での共同研究を非常に重視しており、基礎、応用問わず、多様な分野の研究者が交流し、熱いディスカッションを交わしている様子を見て、日本の科学技術の更なる発展を感じることができ、個人的に刺激を受け、非常に研究のモチベーションが高まった。
最後になりましたが、このような貴重な経験を頂けたことをこの場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございました。