このページでは当研究室の大学院生新入生に「最初の3ヶ月で成長できたこと」についてまとめてもらっています。大学院を検討している方は、先輩の声をじっくりお読みください。
2025年度 (3期生)
医学科3年の頃から3年以上お世話になっている研究室ですが、課外活動としての参加と、博士課程の大学院生として本業で研究に取り組むのとでは、やはり気持ちの面で大きく異なります。MD-PhDコースで博士課程に進学して3ヶ月になりますが、この間に非常に多くのことを経験し、成長させていただいたと感じています。
まず、いくつかの奨学金への応募を通じて、研究計画や自己アピールの方法について改めて深く学ぶ機会がありました。学部4年生の研究室配属期間の時から学振のフォーマットで研究計画書を書く、他の人の文章を添削する経験があったため、ある程度の形は作ることができました。しかし、いざ本番の申請書として取り組むとなると、自らの研究テーマの面白さや重要性、そして自分がそれを達成できるという確信をわかりやすく伝えるために何が重要かを、これまで以上に熟考する必要がありました。この経験は、論理的思考力、プレゼンテーション能力の向上に留まらず、研究テーマや興味に対する考え方を深化させるという点で、大きな成長につながったと感じています。
また、2つ目の研究テーマに新たに取り組み、成果を挙げられたことも大きな経験です。これまでとは異なる分野のテーマにゼロから挑戦し、preprintとして発表するまで漕ぎ着けることができました。研究のサイクルを一通り完遂できたことは、大きな自信となっています。現在は、このテーマに関連したwet実験にも着手しており、決まったプロトコル通りに手技をこなすだけでなく、物品の発注からプロトコルの作成まで、主体的に関わることができています。まだ慣れないことばかりですが、これこそが大学院時代を通じて養いたいと願っていた能力であり、今後も楽しみながら取り組んでいきたいです。
本稿を書くにあたり大学院生活最初の3ヶ月をこうして振り返ると、いかに多くの、そして密度の濃い経験をさせていただいたかを再認識します。今後もこれまで以上の密度で、研究活動に邁進していきたいと考えています。
2025.7.2掲載

清水研に入学した日から早くも3ヶ月が経過した。ほんの少し臨床医学をかいつまんだだけで、基礎医学も数理科学も情報科学もそもそも研究の「いろは」もよくわかっていない自分が、この研究室でやっていけるのか。同じくほぼ初学者から当研究室に進学した1期生の大田さんが後輩へのメッセージとして残した「やっていけるかは自分の努力次第」という言葉だけを頼りに、非常に大きな不安を抱えて研究室にやってきた初日のことは、今でも昨日のことのように思い出される。
清水研での経験値は、大きく分けて勉強会と自身の研究プロジェクトの二つがある。勉強会については、本研究室ではML (Machine Learning)とCS (Convergence Science)の二つを主軸としたカリキュラムが組まれている。最初の3ヶ月は、その他にバイオテクノロジーの基礎、生命科学実験の基礎(座学・実習)、スーパーコンピュータの使い方、Illustrator 速習講座など、当分野で必要となる基礎的な知識やスキルを習得した。これらの勉強会の中でも、特に5月から6月にかけて行われたCSの勉強会では、最新のBriefings in Bioinformaticsに掲載された論文について自分でプレゼンテーションをすることで、様々なバイオインフォマティクス研究の手法について理解を深めることができた。また、清水研ではJournal clubでの論文のFigure の解説を新入生が担当することとなっており、こうした論文説明の経験を通して、バイオインフォマティクスについて右も左もわからなかった状態から、ある程度初見の論文でも一連の流れをイメージしながら論文を読み進められるような応用力を身につけることができた。
研究プロジェクトについても、この3ヶ月で大きく成長できたと感じている。入学時点では大まかに自己免疫疾患の新規治療開発研究にとり組みたいと考えていた程度であったが、そこから自らの興味関心と清水研のテーマをすりあわせて自分独自の研究テーマを作り上げ、そのテーマについて自分自身で研究計画書を執筆し、6月には独自の研究を進め始める段階に至った。7月には既に一つのポスター発表が予定されており、このようなハイペースで研究を進めることができたのは、清水先生の熱意あるご指導はもちろんのこと、研究室の先輩方が適宜、研究計画の相談に乗ってくださったおかげにほかならない。
以上のように、勉強会・研究プロジェクト両方の側面で、入学前からは想像できなかったようなスピードで成長できているという実感がある。持続可能性と成長の最大化の折衷点として、週に75時間の学術活動という目標を立て、その時間は集中してとり組んできたつもりだが、それでも足りないくらい清水研では山のように学びを得られる機会がある。学習資料も周囲の環境もこれ以上なく充実しており、まさに自分が入学前に大田さんの記事を通して心得たとおり、清水研でどれほど成長できるかは自分次第と強く感じる。もし、当分野に興味はあり、「せっかくやるなら本気で取り組みたい」と考えてはいるものの、同時に「本当に自分がここでやっていけるのか」という不安を感じている方がいれば、「すべてはこれからの自分次第であり、現在地はさほど重要ではなく、入学を決意してからどれだけ本気で取り組むか、それが最も大事である。」とお伝えしたい。まずはぜひ一度見学に来て、当研究室の雰囲気を感じ取っていただきたい。
2025.7.2掲載

清水研にお世話になり早くも3ヶ月が経過しました。イレギュラーな形でお世話になることになり、まだまだ先生方や先輩方にご迷惑をかけてばかりですが、ここまで支えてくださった全ての方々に感謝し、ここまでに学んだことや成長したことについて共有させていただきたいと思います。
そもそも私はリアルワールドデータ解析から創薬標的を見出す研究を行っており、疾患発生率を統計学的に解析する疫学的な視点をさらに情報科学的に発展させたいと考えていました。研究室に新しい教授が着任され、同じ方向性の研究を行っているメンバーが全員卒業されたことを機に、BDSCでお世話になっていた清水研で修行させてもらえないかと思い切ってお願いし、派遣研究指導委託生として受け入れて頂いております。
情報系の研究はどうしてもソロプレイになりがちで、オンラインで完結する研究室も多くあると思いますが、清水研の大きな特徴は多くの勉強会を「対面で」行っていることにあると感じています。私は講義等の関係で6月から対面でお世話になっていますが、対面での理解はリモートでお世話になっていた時期と比べても格段に深いものであると感じています。自分にとってはミーティングや勉強会後に皆で集まって話し合ったディスカッションや、全体で聞く程でもないが少し引っかかっていた疑問点を同期と話し合うことに理解のための本質があると強く感じる期間となりました。
もともと頭の回転が早くなく、理解できるまでの時間が他の人より多くかかってしまう自分ですが、数理情報科学から生命科学に至るまで3ヶ月間とみっちりと基礎を叩き込んでいただけたおかげでその時間が少しずつ短くなっていると感じています。また、テーマは違えど「データサイエンスで未来の医療を創る」というミッションに向かって同じ方向を向いているラボメンバーの存在は研究の面でも精神的な面でもすごく大きな存在です。
ここまでの3ヶ月間で、数理科学から機械学習の実装、生命科学実験から臨床医学に至るまでの様々な勉強会と並行して知識を深めながら、研究の計画を立てて実行に移し出せているのは清水研にお世話になっていなければ間違いなくたどり着けなかったでしょう。大変なことも多くありましたが、自分がやってみたい道を貫いてチャレンジをしてよかったと強く感じています。勉強会をはじめとして、清水研は独力で研究を進められるようにするためのサポート環境が他の研究室と比べても群を抜いて充実しています。自分に自信がなくても周りと比べて落ち込むことなく、目の前のことに着実に取り組んでいけば成果は出ると信じて、今後の研究を進めていきます。
2025.7.3掲載

この記事を書いている今、「あれ?もう3ヶ月経ったのか」と時の早さを実感するとともに、清水研での密度の濃さを改めて実感しています。このような密度の濃さを感じつつも、確実に自分の実力を伸ばすことができているという達成感もあります。このような体験ができたのは、清水先生はじめ、研究室の同期や先輩、先生方のおかげであり、とても感謝しています。
以下、清水研で学んで3ヶ月で自分の成長を実感した体験を述べたい。
清水研に入ってまず始まったのは、「数理科学入門」という数学の基礎を固める勉強会でした。私は数学がそこまで得意ではなかったので、ついていくのでやっとでしたが、優秀な同期やTutorの方々のわかりやすい解説によって、自分なりの数学への理解を深めることができました。
また、5月から始まった「AIシステム医科学実践編」では、バイオインフォマティクスのトップジャーナルである「Briefing in Bioinformatics」から、自分の研究領域以外の直近で出た論文を取り上げ、読み込んでみんなに発表することで、バイオインフォマティクスの幅広い知識や、論文の読み方、最新手法を学ぶことができ、非常に有益な勉強会となりました。具体的な例を挙げるのであれば、情報学では多く利用されている「RAG(Retrieval Augmented Generation)」という技術を応用して、特定のタンパク質に結合する化合物を生成するという「RAG2Mol」という論文がとても印象に残っています。この論文から、情報学のプロの人たちが開発した優れた手法を自分の分野に応用する発想と最新技術に対する迅速なキャッチアップの重要性を認識しました。
さらに私の場合、この3ヶ月で特筆すべきは、自分で勉強会を立ち上げたことです。「情報学と生命科学から日本の創薬技術の発展に貢献したい」と考えている自分にとって、生命科学の知識は修士である程度身につけたから、情報学の知識を身につければいいと思っていました。しかし、ラボで勉強会やジャーナルクラブを行なっていると、自分が思っているよりも重要な遺伝子に対する基礎知識が足りていないことに気づきました。そこで自分から清水先生に「論文に出る遺伝子 デルジーン300」を使った遺伝子勉強会を提案し、研究を本格的に開始する7月までに3期生の同期や先輩方と重要な遺伝子の基礎知識を身につける勉強会を行いました。この勉強会では私がTutorを務め、薬の知識や医療の知識など足りない知識は他の同期や先輩に補ってもらいながら、勉強会を完遂することができました。この経験から、単に遺伝子の知識を身につけることができただけでなく、研究に対する自分の理解力やモチベーションの向上にも繋がりました。
以上のように数理・情報だけではなく、生命科学についても改めて自分の知識を深めることができたとても密度の濃い3ヶ月でした。この体験は清水研でなければできていなかったと思います。改めて感謝申し上げます。
また、7月は研究のポスター発表の機会にも恵まれ、大変ですが、さらに充実した経験ができそうで、とてもワクワクしています。博士課程は長いので、これからも倦まず弛まず、楽しんで研究に励んでいきたいと思います。
2025.7.5掲載

2024年度 (2期生)
清水研に入ってから最初の3ヶ月間で成長できたことを記す。
私は学部時代は自分の特定のテーマに関して焦点を当てて研究を行っていた。一方で、清水研の研究対象は生命医科学と情報科学の融合領域であり、また、ドライのみならずウェット実験も対象としている。こうした領域で研究を行うには幅広い知識が必要である。清水研究室での最初の3ヶ月は、こうした研究を始めるための準備期間として位置づけられており、様々な勉強会を通じて様々な知識を習得する。扱う範囲としては生命医科学の基礎(分子生物学、解剖学など)、基礎数学(微分積分、線形代数など)、ウェット実験の知識、機械学習を含む情報科学などと幅広い。清水先生をはじめとする先生方の経験に基づいた説明は非常にわかりやすく、理解の助けとなった。また、学生自身が説明するスタイルで行われるため、学習効率が非常に高いと感じた。さらに5月からはBriefing in Bioinformatics誌を対象とした論文の抄読会が行われ、毎週発表を行った。この経験を通じて、当該分野における論文読解の基礎体力及び発表に関するスキルがついたと感じた。また、ディスカッションや清水先生のコメントを通じて、当該分野における研究を様々な視点で捉えることができた。また、この抄読会とは別に行われるJournal Clubでは対象の論文がCNSなどから特定の分野に囚われずに選ばれる。初めて扱う分野の論文を精読するのは容易ではないが、そのハードルが低くなったと感じている。
また、この3ヶ月間は様々な申請書を書く機会が多くあった。研究提案という形の書類の作成はこれまで経験してこなかったが、研究室の皆様から多くのアドバイスをいただき、納得のいく書類を作成することができた。入学前と比べて文章作成能力も向上していると感じている。
清水研への入学を希望する方には数学・生命科学などの学部レベルの知識は身についた状態で入学することをおすすめする。何もわからない状態で勉強会の場で説明するとなると事前準備に相当時間がかかる。一方で、今行っている分野や研究への知識も深めることも大事である。その分野に関しては研究室のメンバーからはプロとして捉えられ、助言などを求められることも多いからである。
まとめると、清水研での最初の3ヶ月間で新たな分野で研究を行う上での基盤を築くことができたと感じている。当研究室を進学先として考えている方の参考になればと思う。
2024.7.31掲載

AIシステム医科学分野に所属し、最初の3ヶ月が経過した。学部、修士課程、博士課程でそれぞれ異なる研究室に所属した経験を踏まえて、この研究室だからこそ成長できたことを述べたい。
この研究室の素晴らしい特徴は、ジャーナルクラブ (JC) と勉強会である。
JCでは、直近3カ月以内に発表された原著論文を扱う。ただし、あえて、自分の研究テーマに直結しない論文を選ぶ。これは「専門に特化することはいつでもできるが、専門特化でずっとやってきた人が他分野を勉強するのは大変」という考えに基づいている。この方針により、幅広い領域を学ぶ機会が得られ、視野が大きく広がった。さらに特筆すべきは、生命科学と情報科学の融合領域の論文が多く題材となることだ。専門外の論文を読む抵抗感が薄れ、むしろ積極的に取り組むようになった。現代の科学研究において、異分野の知識を統合することの重要性を実感できたのは大きな収穫だった。JCの運営方式も、以前所属していた研究室とは異なっている。従来は担当者が全て説明する形式だったが、本研究室では担当者が背景と方法を解説し、図の解説を学生が担当する。この方式により、ただ受動的にJCに参加するのではなく、論文の細部まで理解する必要が生じ、主体的に読む必要があるため、より深く理解することができた。
勉強会はJCに加えて、週2~3回のペースで実施される。ここでも特定の一分野を深く学ぶのではなく、生命科学や数学、実験手法などの広い範囲を学ぶ。以前所属していた研究室では月に1~2回程度先生が解説する一方的な形式だった。一方で、本研究室では週に2~3回という高頻度で実施される。また、指定された資料を基に学生が主体的に解説する形式を採用している。これにより、単に聴講するだけでなく、自ら学習内容を咀嚼し、他者に分かりやすく説明する能力が養われた。
振り返ってみると、今まで所属した研究室の中では一番教育システムが充実していると感じる。確かに要求されるレベルは高いが、それに応えるだけの支援体制が整っている。この密度の濃さと、幅広い学びの機会は、他の研究室ではなかなか得られないものだろう。
本研究室を志望する人にとって、この体験記が少しでも参考になれば幸いである。
2024.7.31掲載

清水研究室に入学して、最初の3か月で成長できたと感じていることについてまとめる。
研究室に入学してからの最初の3か月は、新しい環境に適応し、多くの挑戦と学びを経験した期間であった。入学してすぐに、BDSCの論文紹介の担当が回ってきて、論文を説明する機会があった。この発表は自分が思った以上にうまくいかず、論文を正確に読み込み、その内容をわかりやすく伝える力が圧倒的に不足していることを痛感した。さらに、専門知識の不足により、発表に対する質問に適切な回答をする力が欠けていることを強く感じた。このように、専門知識の不足を補う必要性を痛感しため、最初の3か月で自己成長するための努力を続けた。
この3か月で、解剖学や生理学といった基礎医学、分子細胞生物学や生化学といった生物学、線形代数や微分積分といった数学、プログラミングや機械学習の勉強など、幅広い分野の基礎を徹底的に学んだ。これらの勉強会を経て、GM(各研究グループでの研究進捗会)やJC(論文輪読会)に参加すると、入学当初は全くわからなかったことが少しずつわかるようになり、さらに聞いたことのある知識が増えていくことで理解にかかる時間が徐々に減っていることに気付いた。また、これら研究室のイベントで行われる清水先生からの「教育的質問」、すなわち一度学んだことを違う場面できかれる経験を通して、学んだ知識の点と点を結びつけ、有機的な理解に繋げることができたと感じている。
この3か月で特に印象に残っているのは、5月から行われたBriefing in Bioinformatics誌を用いた論文の査読会で毎週発表を行った経験である。合計8回の発表をしたわけだが、最初は右も左もわからず、苦労の連続であった。しかし、回を重ねるうちに少しずつ論文読解の基礎体力及び発表に関するスキルが身についていったと感じた。さらには、論文をクリティカルに読む力を身につけることの重要性に気付いた。学部時代は論文を「理解する」ことに多く注力していたが、ただ理解するだけではなく、その論文の売りは何か、新規性は何か、弱いところは何かといった「内容を見極め理解する」力を少しずつ養うことができたと感じている。
このように、最初の3か月は人生の中でも一番忙しいといっても過言ではないほど非常に大変で忙しい日々が続いたが、その努力が確実に自己成長に繋がっていると実感している。大学院の授業やレポートと同時並行で研究室の勉強会やイベントに参加するのは並大抵のことではなかったが、この3か月を経たことで問題解決能力や時間管理能力、さらには発表の経験を通したコミュニケーション能力など、多方面でのスキルアップを感じることもできた。今後も、この成長を基盤にし、研究を頑張っていきたいと思う。
2024.7.31掲載

研究室の数ヶ月の生活を経て気づいたことについて、改めて整理をしたいと思います。
この研究室の最大の特徴は、広範かつ濃密なカリキュラムにあると思います。今年度から開講された「臨床医学エッセンスコース」はその代表例ですが、この勉強会においては週三回、一年間で100回以上にわたって、医師国家試験の試験範囲をほぼ全て網羅するように綿密なカリキュラムが組まれています。学部時代から医学を本格的に学びたかった自分にとって興味深いと思える内容ばかりで、刺激的な毎日となっています。
このコースの他にも、PythonやR、Linuxといったプログラミング言語、ライフサイエンスの知見、さらには有機化学、量子、物理化学をはじめとする科学全般の分野を一通り学ぶ機会が豊富に用意されており、正しい方向性で学習を行うことが可能になっています。
このように、通常では到底不可能なペースで様々な短期間で知識を身に着けることができますが、学習できることはそれだけにとどまりません。
私はこの期間を通じて、周りがまだ誰もやっていない新たなプロジェクトを実現し、かつ世の中に還元される形でアウトプットをするには自分がどのような能力を身につければよいのかについてのヒントを先輩方から吸収させていただきました。
それは例えば、常に自分を更新し、湧き出た発想を分かりやすく伝えることができるある種の優しさを身に着けることなのかもしれません。もしくは、周りと違う方向を向く逆張り力なのかもしれませんし、そもそも周りがどこへ向かおうとしているかという時代を把握する客観性を持つことなのかもしれません。もっと簡単なことで言うと、後輩がついていきたいと思ってもらえるように日々の言葉一つ一つを意識してみたり、未来を語るマインドを常に持って行動したりすることかのかもしれません。はたまた、それら自分の必要な能力や不足している要素を見極め、それを修正しようとする意志なのかもしれません。
私は今後、これらのことを意識しながら、学部時代からの目標であった現状の医療ではできない何かをやり遂げ、人助けを実現するということを達成するために、引き続き頑張りたいと思います。
2024.7.31掲載
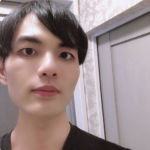
清水研に入学してから早くも3ヶ月が経過しました。この期間に成長できたことを記していきます。ご一読いただければ幸いです。
私が入学して最初に体感したのは、研究に対する基礎体力を養うための勉強会の重要性です。研究を進めるにあたって医学の知識は必要不可欠なものであり、最初に「人体の構造と機能」といった知識を短期間で学ぶことが求められました。個人的には臨床医の先生方からみた視点や疾患について基本的なレベルをカバーするため非常に勉強になりました。また清水研の勉強会は自らが学んだことを他のメンバーに説明する形式で進行します。主体性や分かりやすく説明することが必要であるため、初めは伝える難しさに直面しました。これを経て、同期たちの説明の仕方を真似たり、原稿を準備したりで沢山調べることができたため結果的に知識が自分のものへ身に付いたと感じております。
さらに清水研に入ったことで、Journal Clubや実践編といった論文を精読し、内容を説明する機会が増えました。最初は論文の内容を理解することが難しく、分からない単語や図表に苦戦しましたが、pre-JCという論文の疑問点を解消する勉強会に私は沢山助けられました。初めは論文を読んでも分からないことだらけで、それぞれ単語の意味を調べるだけで精一杯で各figureが何を示していて、どのような意図があるのか。何故この実験をしているのかまで読み取ることができませんでした。しかし、pre-JCでは経験豊富な先輩方や異なるバックグランドよりそれぞれ強みを持つ同期たちとディスカッションを通して学ぶことができ、自身では持っていなかった着眼点から実験の意図した部分を学ぶことができます。個人的には先生方や先輩方には教えていただくばかりで、ご迷惑をおかけしていることは十分承知していますが、この勉強会によって計画書を書く際の文献読み等に役に立ち、研究における基盤を形成できていると実感しています。これらの勉強会を通して以前よりも圧倒的に文献を読む量が増え、少しずつではありますが、図表の意味やこの結果を通してどんなことを示したいのかを理解できるようになりました。
バイオインフォマティクスを始めとした新しい領域に飛び込み、0からスタートすることは難しいと思います。分からないことがあっても、投げ出さずに時間をかけて勉強すれば、どこかで必ず理解に繋がっていくと思います。バックグランドが違うために現段階では不安なことも多いかもしれませんが、一研究者として成長できる当研究室を進学先の一つとして検討してくだされば幸いです。
2024.7.31掲載
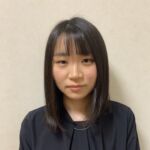
2023年度 (1期生)
当研究室に出入りして3ヶ月ほど経過して体験したこと、そして半年前から変化したことについてまとめる。当研究室や東京医科歯科大学大学院に進学を考える方々の参考になればと思う。
「研究」と言われて、どのようなものを思い浮かべるだろうか。おそらくプログラミングを書いたり、ピペットを使ったり、そんなことを思い浮かべるだろう。これらを「研究」と定義するのであれば、清水研で研究が始まるのは7月からである。それまでの3ヶ月は大学の授業と当研究室の勉強会が中心になる。清水研の目指す研究に必要な学問領域は複数にわたっている。医学を含めた生命科学、情報学、そしてそれを支える数学が必要になり、それぞれから派生した多数の分野の知識が必要になってくる。他にも、bioinformatics誌に掲載された論文を週1ペースで紹介、論文に出てくる図表の読み方のレクチャー (レクチャーとはいえ説明は学生が全て行う) を受ける。それら研究を始めるのに必要な体力や知識を叩き込まれるのが入学後最初の3ヶ月間ということになる (もちろんその後も続くが)。このような理由により研究を始めるのは7月に入ってからになる。しかしながらこの3ヶ月で一番の変化はこれら勉強会によるものである。論文等を読んでいてわからない箇所を調べて、それを説明する単語がわからなくて、それを調べたら…、という無限ループの経験をした方は多いと思うが、これら勉強会を経た今、このループの回数が明らかに減っていることを実感している。これら勉強会は新たに必要な知識を得るという目的もあるが、個人的にはすでに持っている断片的なぼんやりとした知識を繋ぎ合わせるという目的に近かったと感じている。したがって、全く0からというのは相当ハードになるだろう。私自身バックグラウンドは生命科学で、情報や数学は虫喰い的に勉強しており系統的に学習したことがなかった。それらを、まとめ上げること時間にすることができたのは今後間違いなく自分の武器になって行くと感じている。一つ悔やまれるのはもう少し大学の基礎レベルの数学を勉強しておけばもっと得られるものがあったと感じている。おそらく大学院生として入学を希望している方の多くは全部系統立てて学習してきました。というわけではないだろう。入学前にそれらを完璧にやってくることは必須ではない (もちろん可能なら是非頑張って欲しいですが) より良い学習期間とするためにも「全くわからない」という状態はおすすめしない。幸いにも現在はやる気さえあれば書籍やインターネットである程度の情報にアクセスできるようになっているので、ぜひ色々活用してほしい。基礎となる勉強は概してその有用性に気が付きにくいと思うが、何をやるにしても「いしずえ」となるから基礎であるのだと4-6の3ヶ月間で改めて感じている。もし、もう一度自分が入学前にまとまった時間が得られるのであれば情報・数学分野の基礎をやり直したい。当研究分野を志す方には狭くて尖った領域の勉強ではなくて、是非幅広いベーシックな勉強をしてもらえると、有意義な大学院生生活が送れることを保障する。
2023.7.22掲載

清水研究室に入学してから最初の3か月で成長できたことについてまとめる。当研究室への進学を検討している方々の参考になればと思う。
清水研究室に入って最初の3か月間は、清水研の教育プログラムの一環である集中勉強会を通して研究に必要な基礎知識とスキルを徹底的に身に着けることを目指す。4月は基礎的なバイオインフォマティクスの知識を学ぶ事前勉強会「概論編」に加え、生命科学分野の学部の出身でない大学院生のための、生命科学と解剖学の基礎的な知識を学ぶための集中勉強会が行われる。私自身バックグラウンドは経済学であるため、入学時点では生命科学の知識はほとんどなかったが、これらの勉強会を通して研究に必要な基礎的な知識が身につけることができた。
5月と6月の2か月間は、Bioinformatics誌の最新号に掲載された論文を週に一本選び、内容をスライドにまとめて紹介する事前勉強会「実践編」が行われる。紹介する論文は自由に選べるため、バイオインフォマティクス分野の様々な領域の研究に触れ、最新の研究で使われている手法の知識を深めることができる。短期間で数多くの論文を紹介することによって、論文を読み込む力、建設的に批判する力、そして何より重要な、論文の内容を伝える力を身に着けることができると感じた。論文に書かれていることをただ理解するだけでなく、どの部分がキモなのか、そしてどの部分が最も弱いのかを見極めるスキルは先行研究のサーベイを行う上で必要不可欠となる。また、週一回のプレゼンのフィードバックを通して、スライドの作り方や、難解な論文中の手法の要点を簡潔に、わかりやすく伝える力が徐々に身についたと感じた。いくら素晴らしい研究を行っても、その内容を伝える力がなければ価値が落ちる。事前勉強会「実践編」は研究者に求められる様々なスキルの土台を築いてくれる。
清水研究室に大学院生として入学することを希望している方には、入学までに最低限の数学と統計学の素養を身に着けておくことをおすすめする。具体的には多変数関数の微積分、線形代数、統計検定2級レベルの知識を備えていることが望ましい。これらの知識があれば、集中勉強会やJournal Clubの論文などで目にするバイオインフォマティクスの手法のほとんどを本質的に理解することができ、より効果的な学習期間となるだろう。
最初の3か月で行われる集中勉強会の膨大な内容を大学院の授業や、Journal Clubなどの他の清水研の行事の準備と平行して学ぶことは決して容易ではない。振り返ってみると、清水研での最初の3か月間はこれまでの人生で一番忙しかったと言っても過言ではないと思う。決して楽ではないが、清水研には経済学部出身の私でも、3か月で新しい分野の研究のスタートラインに立てるような教育プログラムが用意されている。本気で研究者を目指すなら、ぜひ当研究室を検討してほしい。
2023.7.31掲載

